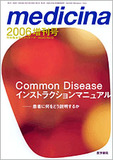バックナンバー ( 閲覧可 )
- 63巻(2026年)
- 62巻(2025年)
- 61巻(2024年)
- 60巻(2023年)
- 59巻(2022年)
- 58巻(2021年)
- 57巻(2020年)
- 56巻(2019年)
- 55巻(2018年)
- 54巻(2017年)
- 53巻(2016年)
- 52巻(2015年)
- 51巻(2014年)
- 50巻(2013年)
- 49巻(2012年)
- 48巻(2011年)
- 47巻(2010年)
- 46巻(2009年)
- 45巻(2008年)
- 44巻(2007年)
- 43巻(2006年)
- 42巻(2005年)
- 41巻(2004年)
- 40巻(2003年)
- 39巻(2002年)
- 38巻(2001年)
- 37巻(2000年)
- 36巻(1999年)
- 35巻(1998年)
- 34巻(1997年)
- 33巻(1996年)
- 32巻(1995年)
- 31巻(1994年)
- 30巻(1993年)
- 29巻(1992年)
- 28巻(1991年)
- 27巻(1990年)
- 26巻(1989年)
- 25巻(1988年)
- 24巻(1987年)
- 23巻(1986年)
- 22巻(1985年)
- 21巻(1984年)
- 20巻(1983年)
- 19巻(1982年)
- 18巻(1981年)
- 17巻(1980年)
- 16巻(1979年)
- 15巻(1978年)
- 14巻(1977年)
- 13巻(1976年)
- 12巻(1975年)
- 11巻(1974年)
- 10巻(1973年)
- 9巻(1972年)
- 8巻(1971年)
- 7巻(1970年)
- 6巻(1969年)
- 5巻(1968年)
- 4巻(1967年)
- 3巻(1966年)
- 2巻(1965年)
- 1巻(1964年)
文献閲覧数ランキング( 1月19日~1月25日)
- 第1位 腎機能の推移をみる重要性とその方法について教えてください 中澤 純 medicina 63巻 1号 pp. 17-21 (2026年1月10日) 医学書院
- 第2位 どのような患者に非ステロイド型MR拮抗薬を選び,どのように導入していますか? 山内 真之 medicina 63巻 1号 pp. 69-73 (2026年1月10日) 医学書院
- 第3位 CKD患者におけるRAS阻害薬の使い方について教えてください 服部 洸輝 medicina 63巻 1号 pp. 57-61 (2026年1月10日) 医学書院
- 第4位 腎臓のうっ血が腎エコーでわかると聞いたのですが,具体的に教えてください 谷口 智基 medicina 63巻 1号 pp. 32-37 (2026年1月10日) 医学書院
- 第5位 造影剤腎症(ヨード,ガドリニウム)の最近の考え方を教えてください 耒田 善彦 medicina 63巻 1号 pp. 133-137 (2026年1月10日) 医学書院
- 第6位 無症候性高AMY血症をみたらどうしたらいい? 田村 弘樹 medicina 62巻 5号 pp. 640-643 (2025年4月10日) 医学書院
- 第7位 腎臓と塩の最近のトピックについて教えてください 鳥光 拓人 medicina 63巻 1号 pp. 44-47 (2026年1月10日) 医学書院
- 第8位 閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)を鑑別に入れるべき状況—OSASの多彩な表現型を押さえる 杉山 華子 medicina 61巻 6号 pp. 882-885 (2024年5月10日) 医学書院
- 第9位 急性腎障害(AKI)の診断,腎代替療法のタイミング,具体的な透析処方について教えてください 藤﨑 毅一郎 medicina 63巻 1号 pp. 138-143 (2026年1月10日) 医学書院
- 第10位 特集を読む前に あなたの理解度チェック! medicina 63巻 1号 pp. 12-16 (2026年1月10日) 医学書院