Japanese
English
原著
一酸化炭素による膜拡散能力(DM)及び肺毛細血量(VC)測定の意義について
Clinical Significance of the Measurement of the Membrane Diffusing Capacity (DM) and the Pulmonary Capillary Blood Volume (VC) by the CO breath Holding Technique
金上 晴夫
1
,
桂 敏樹
1
,
白石 晃一郎
1
,
馬場 健児
1
,
田中 元直
1
,
尾形 和夫
1
Haruo Kanagami
1
1東北大抗酸菌研究所
1The Research Institute for Truberculosis and Leprosy, Tohoku University.
pp.637-645
発行日 1962年9月15日
Published Date 1962/9/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1404201134
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
I.緒言
1915年Krogh1)によつて初めて測定されその後約40年の間かえりみられなかつた肺拡散能力の測定はその後1951年Riley2)らによりO2肺拡散能力が,又1954年Forster3)らによりCO肺拡散能力の簡単な測定法が発表されるに及んで肺拡散能力測定の臨床的意義は次第に解明され,肺胞毛細管ブロック症候群4)5)の診断のみならず或は肺気腫の診断6)に或は肺気腫と気管支端息との鑑別6)7)に,或は肺癌の予後判定8)に,或は先天性心疾患特に心房中隔欠損9)10)11)12),肺動脈狭窄の診断12)に,肺拡散能力測定の重要性が次第に認識される様になつた。しかしながら我が国においては1958年以来金上,桂等によるCO肺拡散能力測定の意義についての一連の報告2)7)8)12)13)14)15)16)17)18)をみるほかは僅かに二,三19)20)の報告をみるにすぎない。
さてこれ迄測定された肺拡散能力(DLのは二つの因子をもつている事がその後明らかにされた。即ち一つは肺胞膜の真の拡散能力(DM),即ち膜因子と呼ばれるものと,他の一つは肺毛細血管中の全血液量がCOと結合してCOHbを形成する速度即ち赤血球因子と呼ばれるものである。膜因子DM,は肺胞毛細管膜の有効表面積と膜のガス透過性及び膜におけるガスの溶解性に比例して膜の厚さに反比例する。
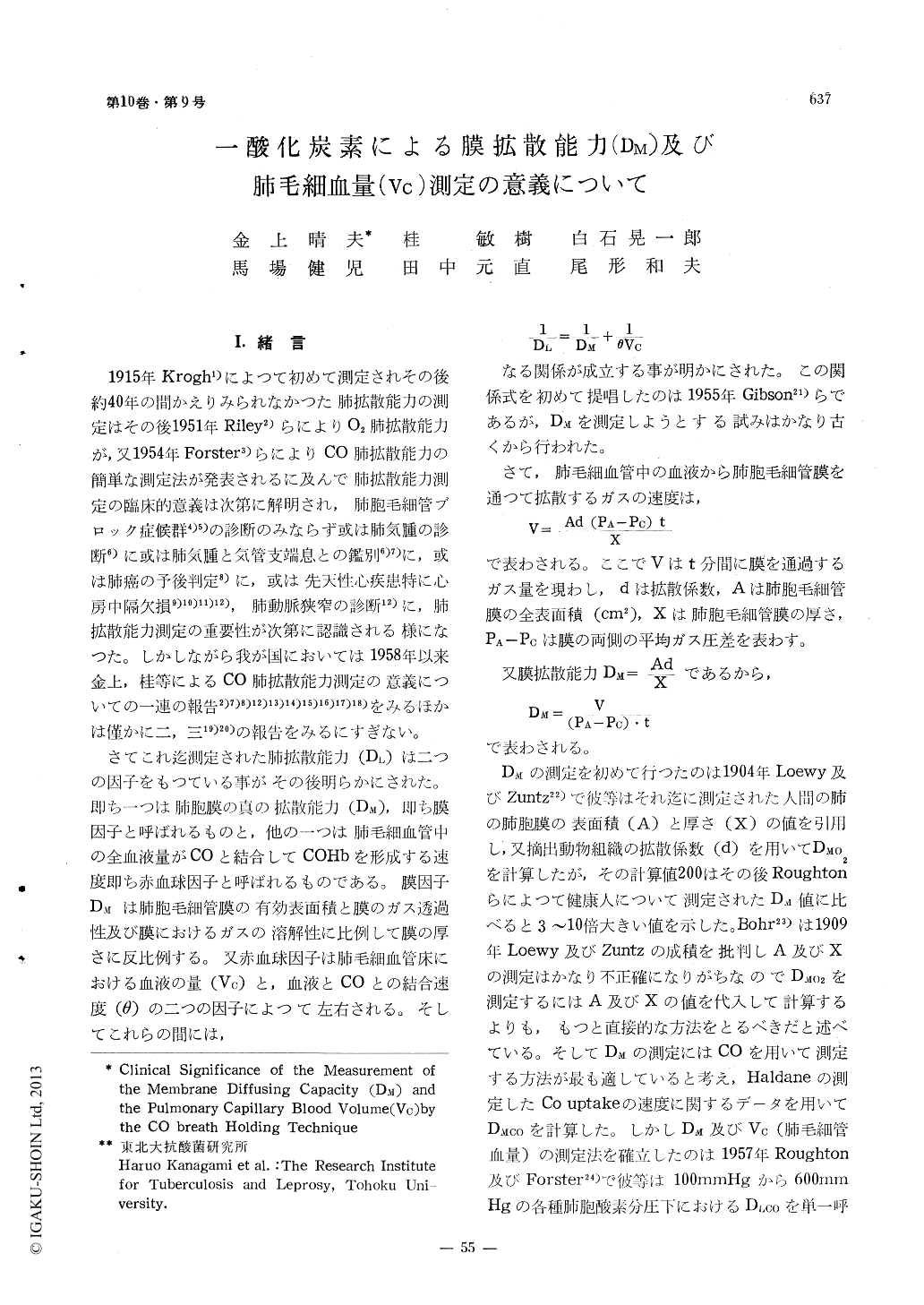
Copyright © 1962, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


