- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
教授パラダイムから学習パラダイムへの転換によって、教育の場における主体は、教師から学習者へと変わることが求められてきた。このような学習者主体の教育というと、例えば看護教育における実習やアクティブラーニングを取り入れた授業など、学生の活動を中心に据えた教育が想起される。しかし、このような教育の場において真に学習者が主体となっているといえるのは、学習者による能動的・自律的な学びがそこで実現してこそではないだろうか。それが仮に理想論であったとしても、少なくともわれわれ教員は、そのような学びが実現するよう、教育の場において学生を支援していくことが望まれる。
では、学習者が主体となることが目指された場での教育の評価は、どうあるべきであろうか。評価の目的には、①学生の最終成績を出すため(評定)、②教育内容や教育方法の改善へとフィードバックするため、③学生の学習改善に資するため、といったものがある。このうち、学習者が主体となることが目指された場では、3つ目の、学生の学習改善に資する評価が、より重要となるであろう。というのも、この評価をうまく生かすことで、学生の能動的・自律的な学びを支援できる可能性があるからである。そして、このような支援を実現するためのツールの1つが、本稿で紹介するeポートフォリオ(=電子化されたポートフォリオ)である。
文部科学省の調査〔令和4(2022)年度〕によれば、日本では、半数近くの大学で学習ポートフォリオが導入されている1)。また、そこで利用されているeポートフォリオは、市販のものから独自開発のものまで、多種多様である。その中で、本稿では、大阪公立大学(以下、本学)で活用している独自開発のeポートフォリオを取り上げ、そこでどのような考え方に基づいて、どのような学習評価が行われているのか、また、その評価結果をどのように可視化して学生の気づきを促し、能動的・自律的な学びへつなげようとしているのかについて紹介する。加えて、本学eポートフォリオの拡張機能の1つであるEnglish Portfolioについても簡単に触れ、eポートフォリオが持つ可能性について示したい。
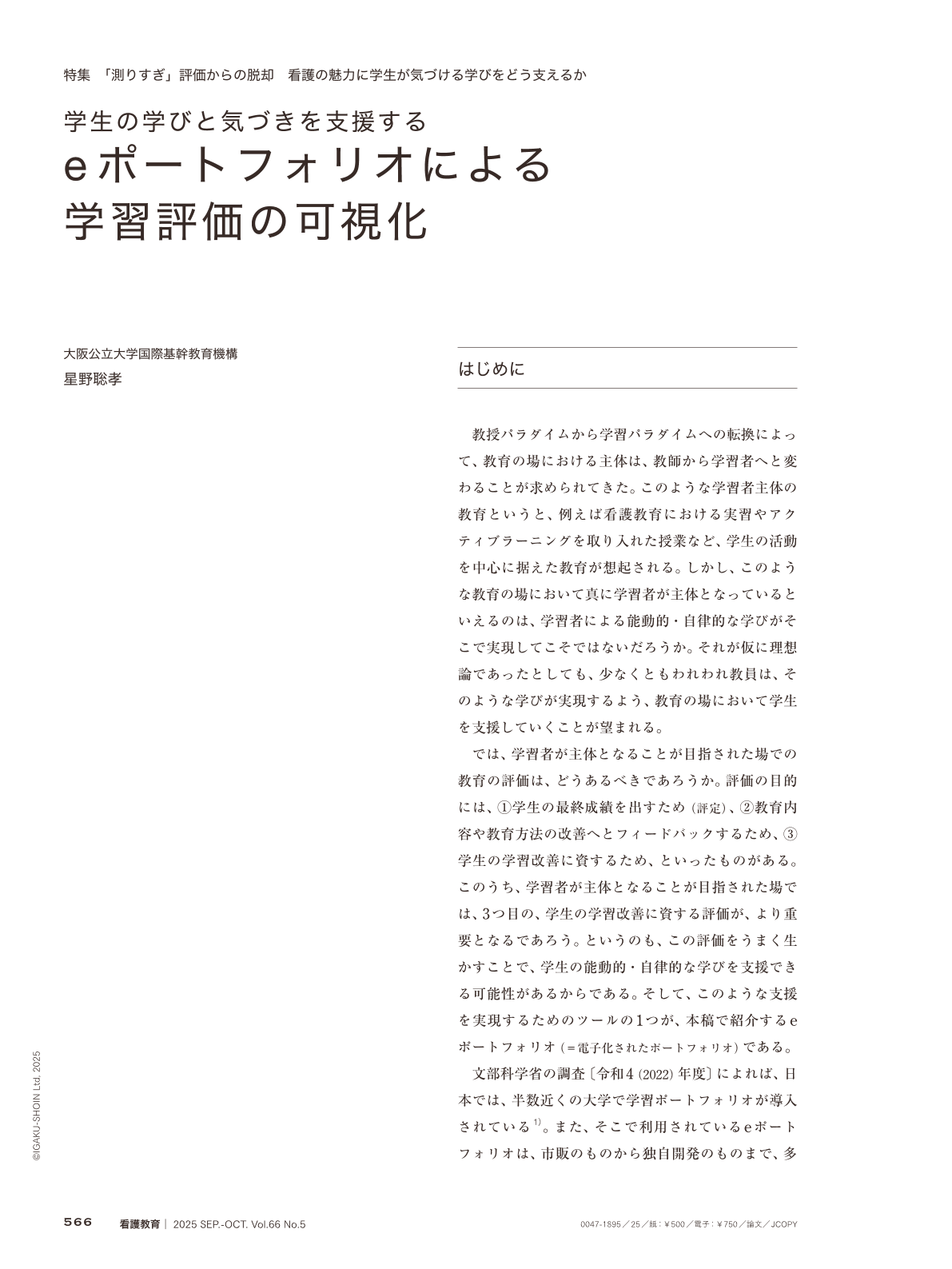
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


