特集 「測りすぎ」評価からの脱却—看護の魅力に学生が気づける学びをどう支えるか
看護実践の複雑性と評価の再考
大貫 守
1
1愛知県立大学教育福祉学部教育発達学科
pp.558-565
発行日 2025年10月25日
Published Date 2025/10/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.004718950660050558
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
近年、高齢化の進行や医療に対するニーズの多様化に伴い、自宅や施設など病院とは異なる環境で医療が行われたり、個人が複数の疾患を抱える中で、個に応じた医療の提供が求められたりするなど、看護職が向き合う対象の多様性や複雑性が増してきている。この中で、令和4年(2022)年度から導入された看護教育の新カリキュラムでは、この多様性・複雑性に対応した看護を創造する能力の育成が求められてきた。具体的には、学習者が自分自身で物事を考え、状況に応じて学習した知識や技能を統合する力を育成することが望まれている。
ここで、看護師に望まれていることは養成所や大学での学びを臨床現場へと転移させることである。転移とは「ある領域で習得した知識をその領域とは異なる領域に活用すること」1)を指す。だが、看護教育の場面において、学生に授業で教授した知識や技能であるにもかかわらず、総合的な演習や実習において実際に使う場面になると、学習者がそれらを相手や目的に応じて活用することができないといった状況に直面することも少なくない。
本稿では、看護教育において知識や技能の活用を促すために、「深い」理解をどのように育て、評価していくのかという点について考えてみたい。
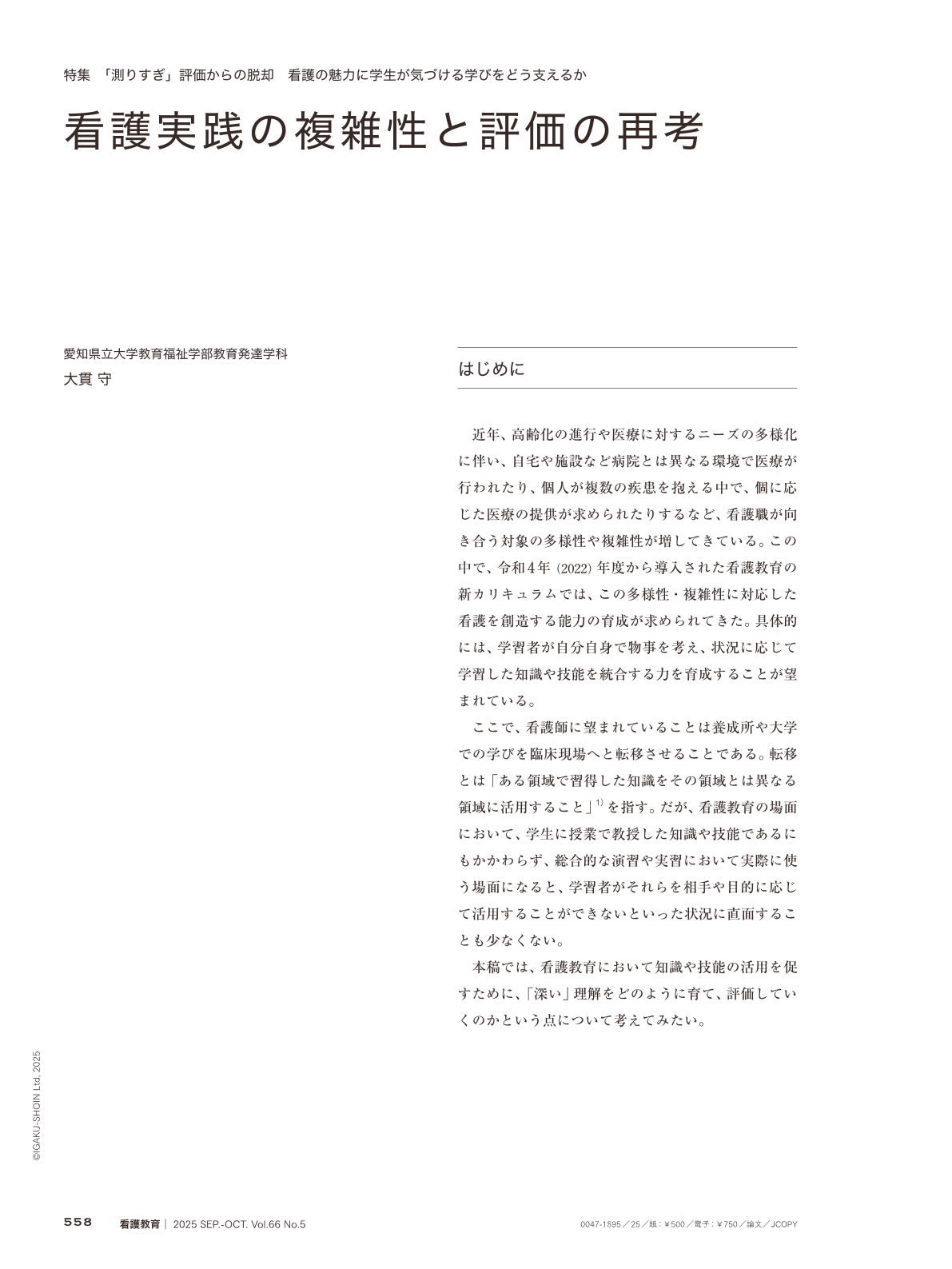
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


