特集 「信じたい」という心理―心の病から陰謀論まで
信じることの病理の複雑さとあいまいさについて―支配観念
石垣 琢麿
1
1東京大学大学院総合文化研究科
pp.714-718
発行日 2024年11月10日
Published Date 2024/11/10
DOI https://doi.org/10.69291/cp24060714
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
I はじめに
信じることの病理とそこからの回復を支援するという,きわめて臨床実践的なセクションの冒頭としてふさわしいかどうか疑問だが,支配観念というあいまいな病理現象について取り上げたい。同じセクションで神経性やせ症,自己愛性パーソナリティ障害,神経発達症のように,臨床家がよく出会い,しかもきわめて重要な臨床的テーマが解説されるので,一つくらいはニッチなテーマも許されるだろう。
精神病理学では,「了解可能だが異常な思考=二次妄想」という概念がある。そこには妄想様観念(パラノイア:paranoid ideations)だけでなく,従来は神経症のカテゴリーに入れられてきた精神疾患の強い病的な信念も含まれる。たとえば強迫症における病識を欠いた強迫観念,社交不安症におけるきわめて強く歪んだ対人イメージ,神経性やせ症における摂食,体形,体重増加への強い忌避感,醜形恐怖症における病的な身体認知などは,妄想ではないにせよ常識では理解できない場合がある。それらを統合する異常思考の概念として支配観念(overvalued ideas)が第二次世界大戦前から提唱されてきた。しかしながら,各国の精神医学とその背景文化によって現象のとらえ方が異なるため,世界的に統一された定義や見解というものは未だ存在しない。そのため,支配観念は「信じることの病理の複雑さとあいまいさ」に相応しいテーマだと考えた。
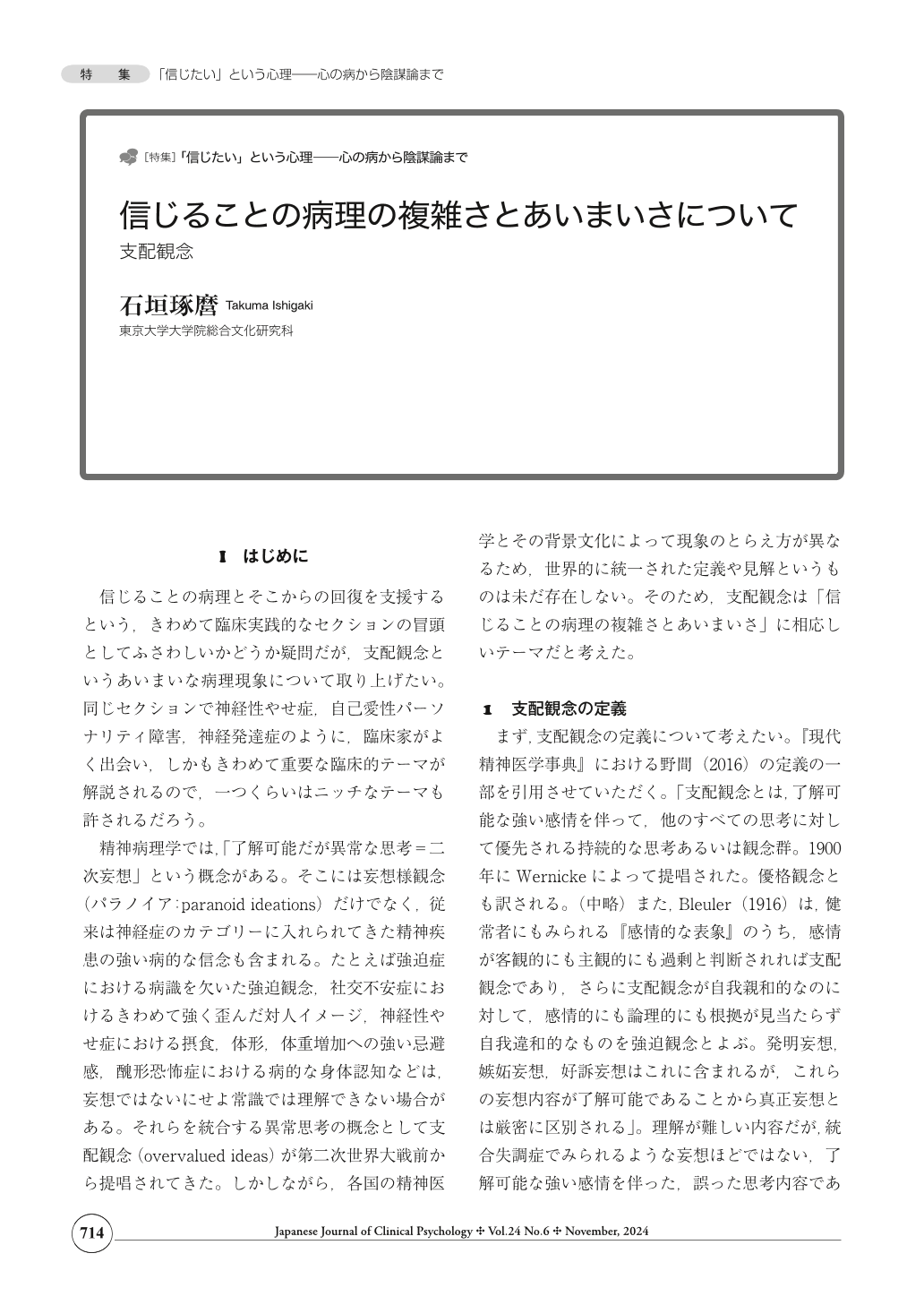
Copyright© 2024 Kongo Shuppan All rights reserved.


