- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
Ⅰ はじめに―奇異な内容を信じる人たちは特殊な存在か
信じることに関する特集にあたり,この特集テーマを取り上げた理由について,筆者の臨床体験や研究上の関心を語ることによって説明したい。筆者の研究対象のなかで大きな割合を占めてきたのは,精神症(psychosis)の妄想,妄想的な信念,およびそれらに対する認知行動療法である。当初は筆者も,妄想は特殊な心理現象だと考えており,あくまでも臨床的な問題としてとらえていた。しかしながら,疫学調査の発展によって,妄想的な信念を含む精神症様体験(psychotic-like experiences : PLEs)とよばれる現象が,一般人口において広く存在することが徐々にわかってきた。心理発達のプロセスからも予想されるように,PLEsは青年期に体験率が増加し,その後psychosisやその他の精神疾患に移行する群も存在するが,移行しない群,症状が消失してしまう群もある。PLEsに類似した現象は,青年期だけでなくすべての年齢層で,すでに1960年代から指摘されていた(Strauss, 1969)。こうした大標本調査で用いられる尺度は,psychosisの妄想から選ばれた,常識から逸脱した奇異な思考内容を列挙したものである。それら奇異なことを信じている人たちは,臨床家が想像する以上に数多く存在しており,信じている内容や対象を理由に精神科を受診したこともなく,カウンセリングを受けたこともない。彼らを丁寧に診察すれば,何らかの診断カテゴリー,たとえば統合失調症スペクトラム障害やパーソナリティ障害のどれかに分類されるかもしれないが,社会的にも対人的にも問題が生じていない場合は,事例化することもなく,臨床家とは一生遭遇しないだろう。
現在では,PLEsと自殺企図や薬物依存との関連が注目されており,公衆衛生の観点からは看過できない心理現象だと考えられているが(たとえば,Yates et al.(2019)),別の見方をすれば,世の中には多様な人が共存しているというひとつの例であり,奇異な思考内容を信じるに留まり,いわゆる病的プロセスに入りこまないことは,ある意味ではその人の健康さ,心理的強さを表しているということもできよう。しかし,psychosisに移行しないとしても,他者と共有されず共感も得られないような信念を心のカプセルに入れて,社会のなかで生活するというのは,つらいことや難儀なこともあるだろう。現代社会のトレンドになっている陰謀論は,かつてはそのようにカプセルに入れられて息ができなかった信念たちが,SNSの力を借りて蠢き出した結果ではないかと想像してしまう。
一方,精神疾患全体を見渡すと,精神医学的には妄想のカテゴリーに入れられないが,何らかの強い,たいていはネガティブな内容の信念を有する場合は多い。うつ病,神経性やせ症,強迫症,醜形恐怖症,社交不安症などの非精神症(non-psychotic)の人たちが有する自己と他者(世界)に関する信念を,統合失調症の妄想と鑑別するのは難しいことも多い。うつ病でも強迫症でも,一般的にはありえないと考えられる思考内容をきわめて強く信じていることが病的である根拠だとされる。たとえば,神経性やせ症で体重が30kgを切っても「私は太っている」と固く信じることや,強迫症で「赤信号で止まったら決まった単語を言わないと必ず不幸が訪れる」と信じることは妄想とどこが異なるのだろう。筆者にはJaspers的な精神病理学に基づいて論を展開する能力はないが,なぜ彼らがそうした信念を,了解を超えて強く抱くようになるのかよくわかっていない。また,その思考内容を奇異なもの,常識から逸脱しているものと,何を基準に定義できるのか。さらに,彼らのなかにはその信念が「他の人からちょっとおかしいと思われてしまうかもしれない」ととらえている人もいるが,「他の人がなんと言おうと疑う余地がない」と考える人もいる。つまり,思考に対する各個人の確信の程度はさまざまであり,そのときの精神状態や置かれた状況によっても変化する。自らの状態を病的か否か判断する能力である病識という概念を用いれば,これまでnon-psychoticの人たちは十分な病識を有すると考えられてきたが,必ずしもそうとは言えないことが医学的常識になってきた。たとえばDSM-5で,強迫症の診断に際して病識の程度を明記させるようになった背景には,non-psychoticの人たちが包含する多様さに注意が向けられたことも影響しているだろう。
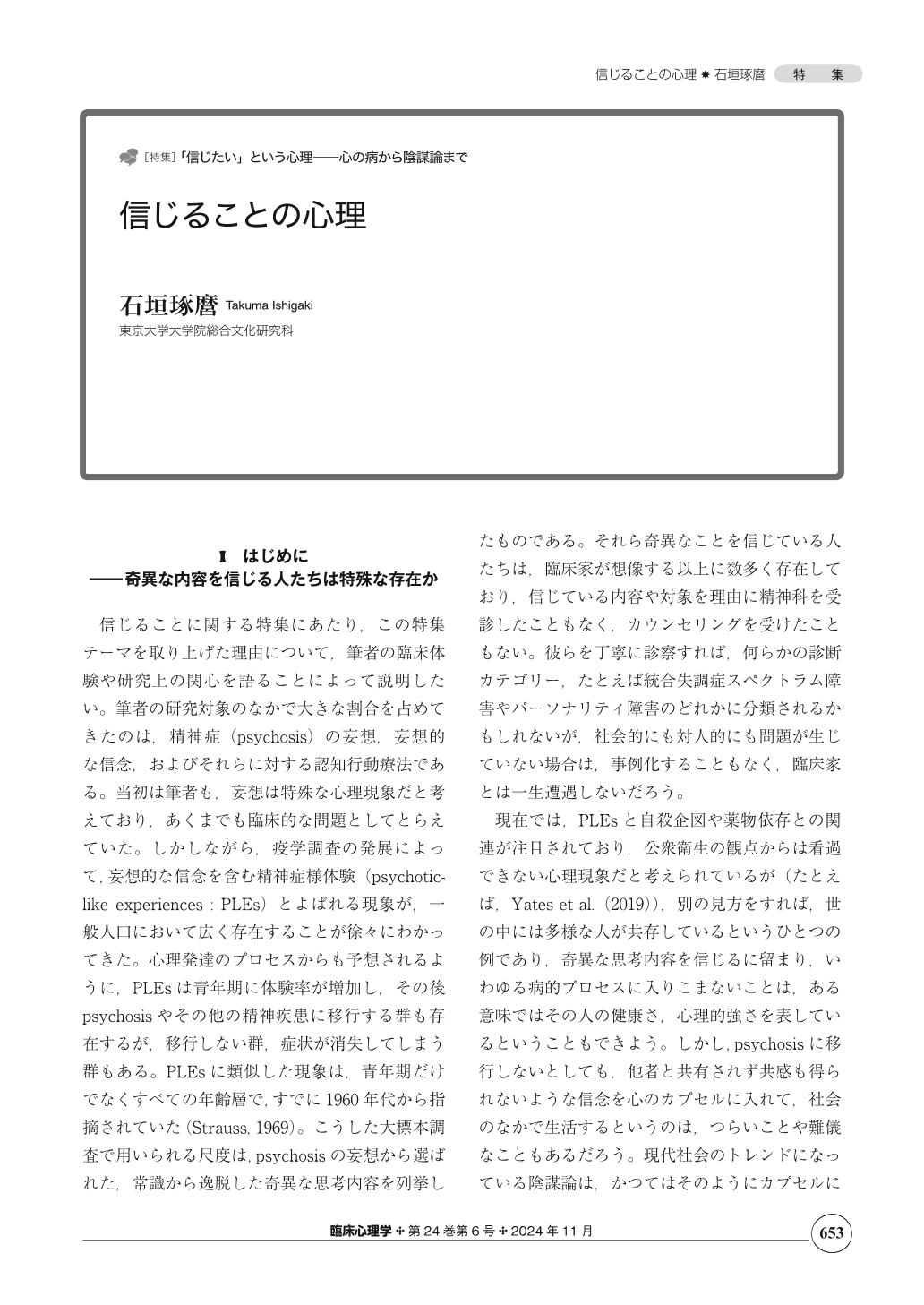
Copyright© 2024 Kongo Shuppan All rights reserved.


