- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
I はじめに
近年,職場のハラスメントに関する問題は労働者のストレス要因の大きな部分を占めるようになっている。例えば,精神障害・自殺に関する労働災害認定で最も多いのがハラスメント関連項目である。しかし,労働災害の認定基準にハラスメントに関する項目が追加されたりと,被害者を救済する動きがある一方で,ハラスメント加害者に対しての直接的なアプローチは少ない。ハラスメント発生後の事後措置として懲戒処分が行われるケースはあるが,加害者に対するそれ以外の再発防止対策は未だ発展途上と言える。
職場のパワーハラスメント(パワハラ)の防止対策が事業主(大企業)に義務化されたのは2020年6月のことである。その後,中小企業にも,2022年4月から防止対策が義務化された。しかし,対策が義務化される前も後も,ハラスメント問題対応者から最も多く寄せられる質問は,「ハラスメント加害者に自覚してもらうにはどうすればよいのか」「どうすれば加害者に自分で気付いて行動を改めてもらえるだろうか」である。ただ,残念ながら,ハラスメント加害者が自ら自分自身の言動に気付いて態度を改めることは難しい場合が多い。
なぜなら,ハラスメント行為をしていたり訴えられたりした人は,ハラスメントをしている自覚や悪気がないことが多いからである。逆に言えば,自分の言動が他者に対しどのような影響を与えるのかが正確に理解できていなかったり,悪意がないからこそ,ハラスメント加害者となってしまっているとも言える。それだけでなく,むしろ自分は組織に貢献している,部下を熱心に育て上げているという自負を持つ者も多い。
例えば,過去2年間にパワハラで訴えられたことのある管理職19名を対象にインタビュー調査を行ったオーストラリアの研究(Jenkins et al., 2012)では,なんと参加者の9割が「これまで誰に対してもパワハラをしたことがない」と回答している(残りの1割は「ごくたまにパワハラ行為をしたことがある」と回答)。そして参加者全員が,指摘されたパワハラ行為に対して「合理的なものだった」「管理職としての仕事を全うしただけだ」と説明したのである。
ではなぜ,ハラスメント加害者はこのような思い込みを持ってしまうだろうか。本稿では,ハラスメントの種類と定義について整理した後,ハラスメント加害者の心理としてどのようなことが研究でわかっているのかを解説する。
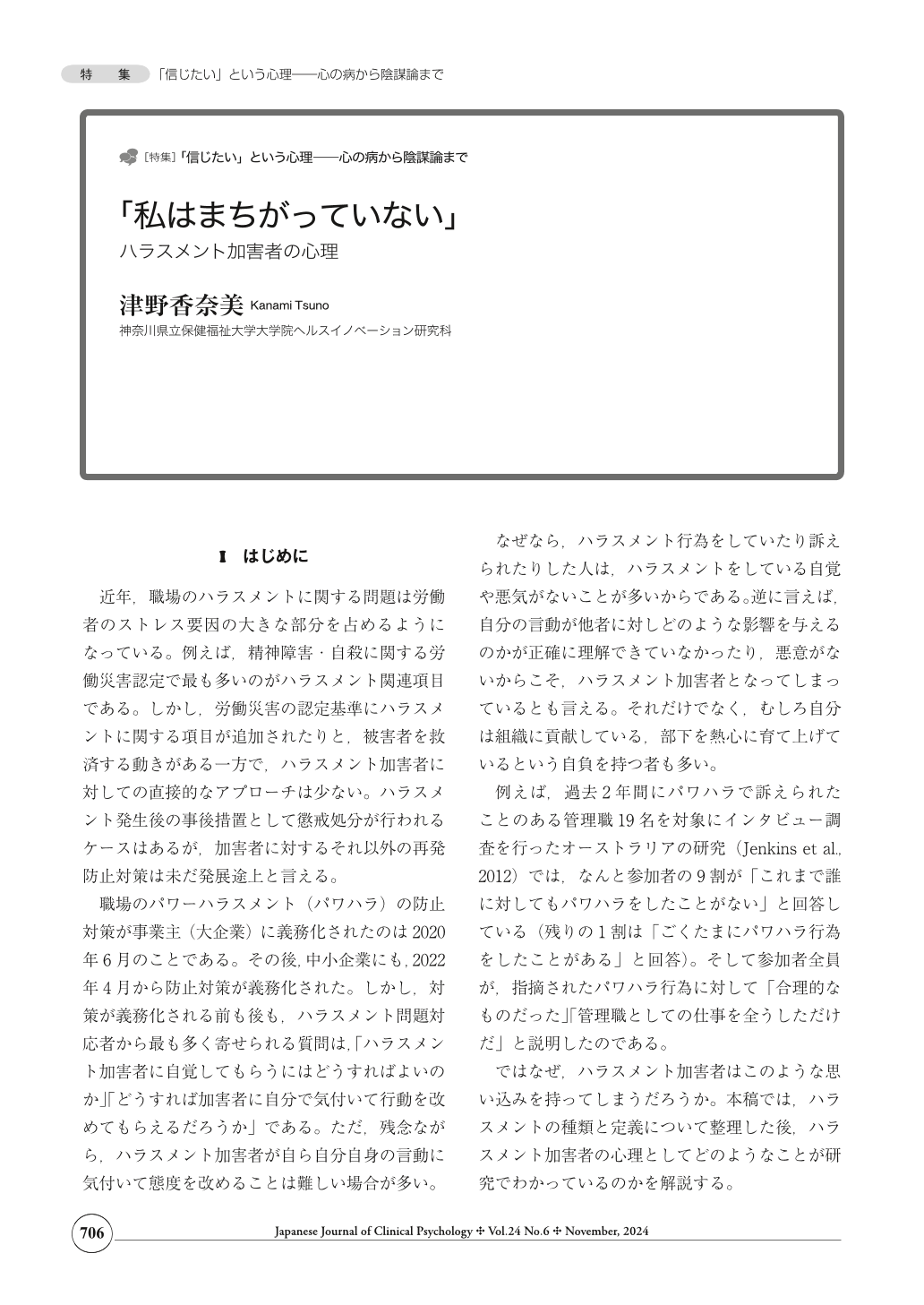
Copyright© 2024 Kongo Shuppan All rights reserved.


