- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
I はじめに
ストーカー(以下,ST)行為とは,「特定の者に対する恋愛感情その他の行為の感情が満たされなかったことに対する恨怨の感情を満たす目的で,特定の相手やその家族等に対して,付きまとい,待ち伏せ,押しかけなどを行うこと」であり,表(次ページ参照)に含まれる行為が規制対象となっている。
2000(平成12)年に制定されたST規制法により,嫌がらせ行為の段階で罪に問うことが難しかったそれまでの状況を大きく変えることができた一方,情報技術の急速な発達が,行為形態の多様化を生み出し,法律が追いついていない現状がある。2021(令和3)年の改正ST規制法において,ようやく元交際相手などの自動車等にGPS機器をひそかに取り付け,位置情報を把握する行為や,相手から拒否されてもなお文書を送り続ける行為が規制対象となったところである。
こうした規制行為の拡大・強化が行われるなかではあるが,全国の警察に寄せられるST相談は,この10年余りは2万件を推移しており,付きまといなどを禁じる「禁止命令」は2023(令和5)年に1,963件と法施行後最多となっている。
増加するST事案を受け,被害者支援や加害者対策の在り方について検討し,内閣府,警察庁,文部科学省等関係省庁が連携して取り組みを推進するための総合的な対策「ストーカー総合対策」(2015(平成27)年3月策定)がまとめられ,ST行為者による被害実態把握のための調査研究,加害者が抱える問題にも注目した対策の推進等が項目として盛り込まれている。他方,被害者の約4割は20代の若者たちである状況を踏まえ,2018(平成30)年5月,徳島県警察本部と徳島文理大学が連携し,官学共同研究を行うことになった。
筆者はその研究チームの一人として,大学生を対象にしたST被害の実態把握調査,大学生の親密な関係に関する意識調査,そしてST事案の被害者と加害者の性格類型調査や加害者面接調査を実施し,ST行為へと発展する過程を被害者,加害者の両面から臨床心理学的知見に基づいて検討した。
目的は,なぜST行為に及ぶのかというメカニズムを明らかにし,若者世代の予防教育と加害者治療へつなげることであった。ここでは,そこで得た知見から,加害者たちがなぜ信じられるはずの関係において,相手を裏切るような行為を行ったのか,彼らが何を信じていたのか,また信じざるを得なかったのか,筆者の考えを述べてみたい。ただし,加害者を擁護するためではなく,加害者のそれを考えることが,被害者を生まないことにつながるとの考えからである。
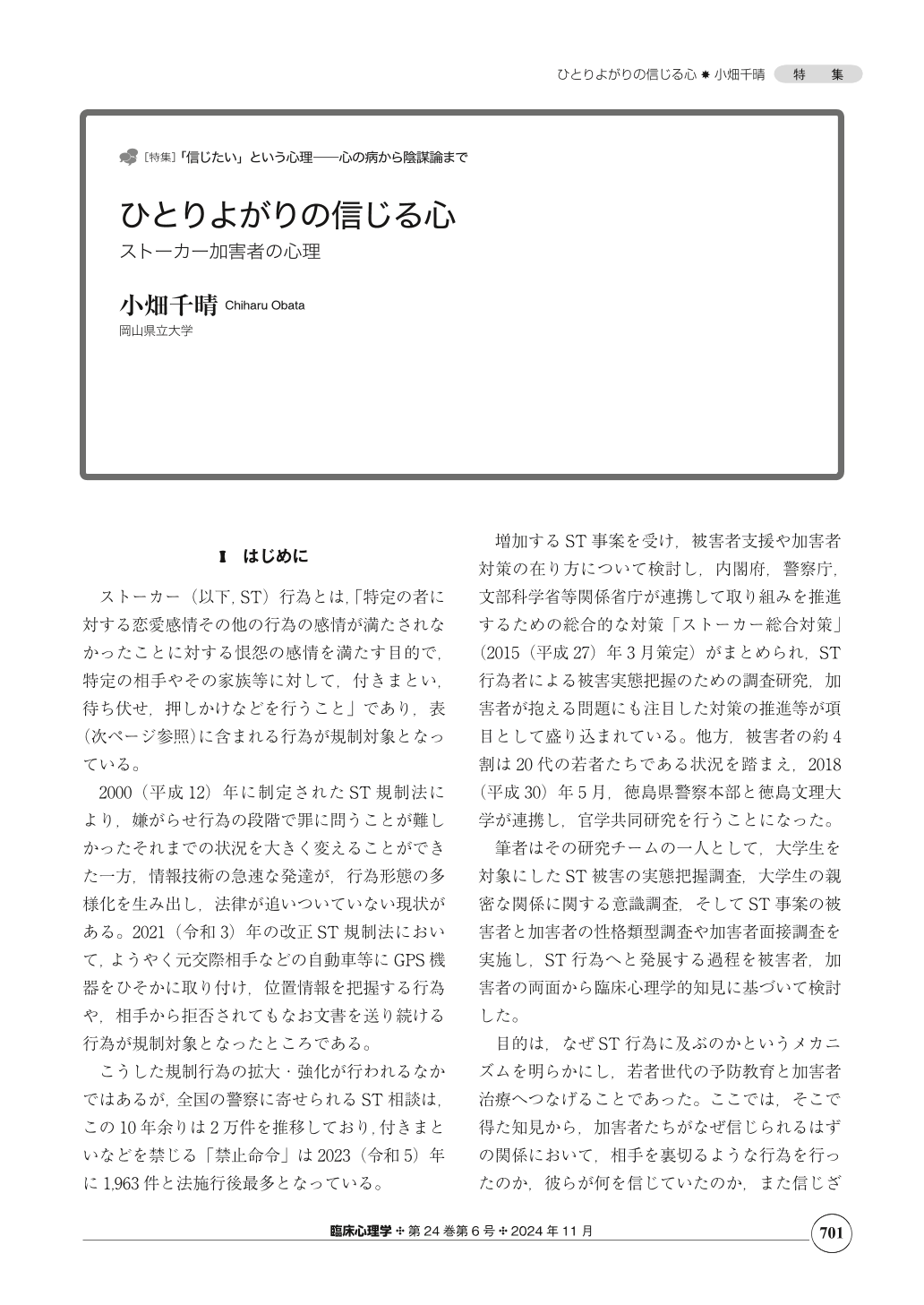
Copyright© 2024 Kongo Shuppan All rights reserved.


