特集 大規模災害時の食と住に関する感染制御と予防衛生
4.災害食はどうあるべきか
仁科 淳良
1
,
平野 義晃
1
,
松吉 ひろ子
1
1東海学園大学健康栄養学部
pp.26-31
発行日 2025年9月25日
Published Date 2025/9/25
DOI https://doi.org/10.34449/J0108.09.01_0026-0031
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
災害食(図1)とは,地震,津波,台風などの自然災害や,戦争,パンデミックといった社会的災害が発生した際に,被災者が一時的に生活を維持するために摂取する食料を指す1).これには,長期保存が可能で,加熱や水が不要な食品,栄養バランスに配慮された食品,さらには心のケアをも考慮した「温かみのある食事」も含まれる.一般的には,非常食や備蓄食とも呼ばれ,個人や家庭,自治体,企業などが災害に備えて保有することが求められている.災害時には物流の停止,ライフラインの断絶,避難生活の長期化などにより,通常の食事が困難となる.したがって,災害食は単なる「食べ物」ではなく,生存に不可欠なインフラの一部として捉えるべきである.また,災害直後の「応急期」,数日後からの「応急復旧期」,その後の「復興期」に応じて,求められる災害食の形も変化していく.
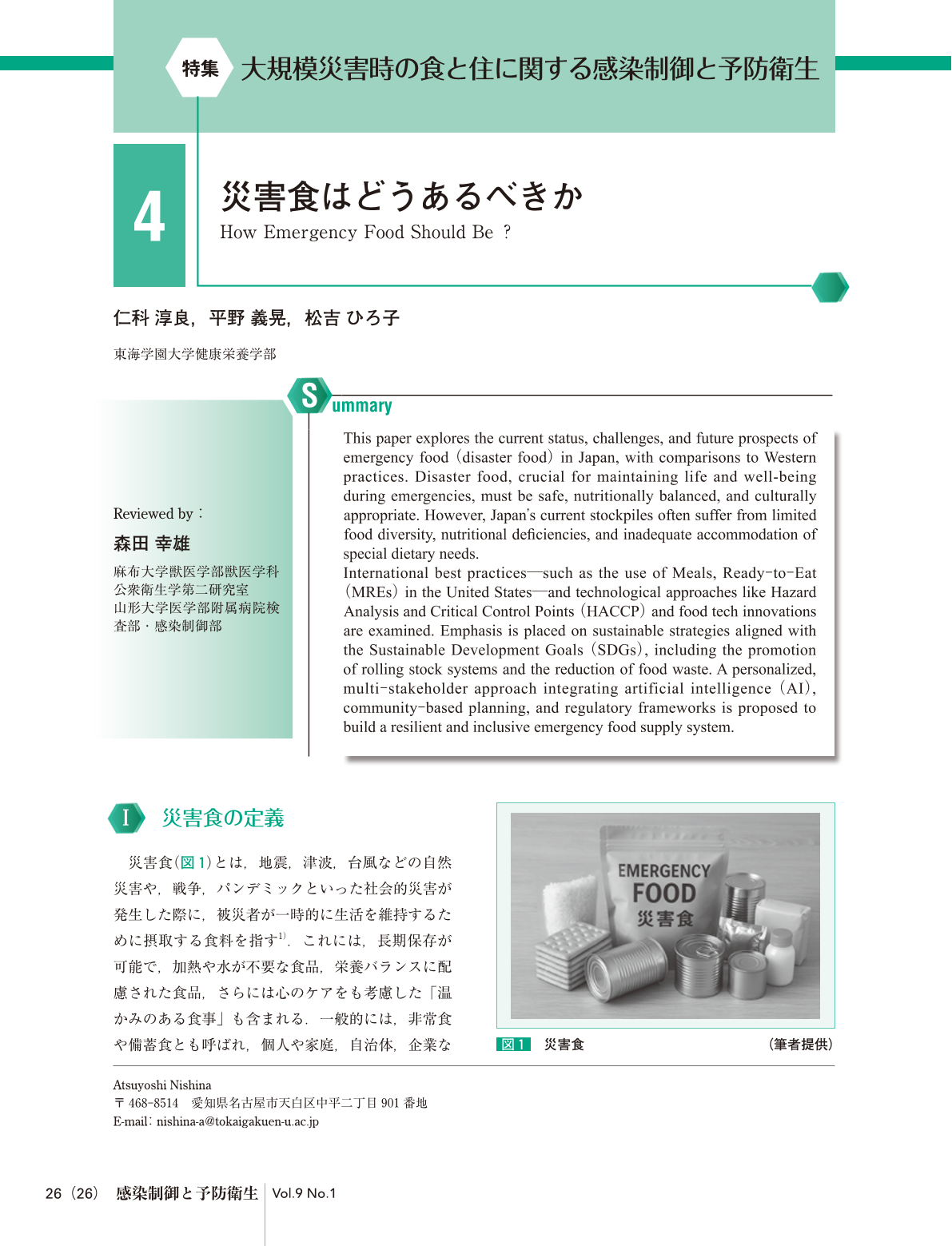
Medical Review Co., Ltd. All rights reserved.


