連載 〈教育〉を哲学してみよう・4
主体が立ちあがるとき:アクティブ・ラーニング再考(1)
杉田 浩崇
1
1広島大学 教育学部
pp.938-941
発行日 2019年11月25日
Published Date 2019/11/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1663201361
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
現在、大学教育でも学校教育でも、アクティブ・ラーニング(主体的・対話的で深い学び)が重要だと言われている。教授が教壇に立ち、受講生がその話を静かに聞いたり、板書を写したりする。そういった伝統的な大学の知識伝達型の講義スタイルが見直されつつある。改訂された学習指導要領では、「何を知っているか」ではなく「何ができるか」へと知識・技能のイメージを転換し、児童生徒が知識・技能を具体的な場面で活用したり、未知の問題を解決するために駆使したりすることのできるよう工夫することが教師に求められている。その核となったのが、大学ですでに必要性が言われていたアクティブ・ラーニングである。具体的な授業方法までふみ込んだ点に今回の学習指導要領の特徴があると言われる。
実際、大学でのFDや学校教育での研修では、ペアやグループでの活動、PBL(problem based learning)、プロジェクト学習などの体験型教育の講習がさかんになされている。しかし、ときに活動をするだけで終わり、なんとなくやった感だけが残る場合も少なくない。そもそも伝えたい内容や身につけるべき知識・技能に応じて、授業方法が異なっていてもいいはずである。どのような活動が効果的なのかは教育方法学や教育心理学の研究成果を待つとして、この連載では「アクティブ・ラーニング」の考え方そのものを問い直してみたい。今回はその第一歩として、「考える」ということを考えてみよう。
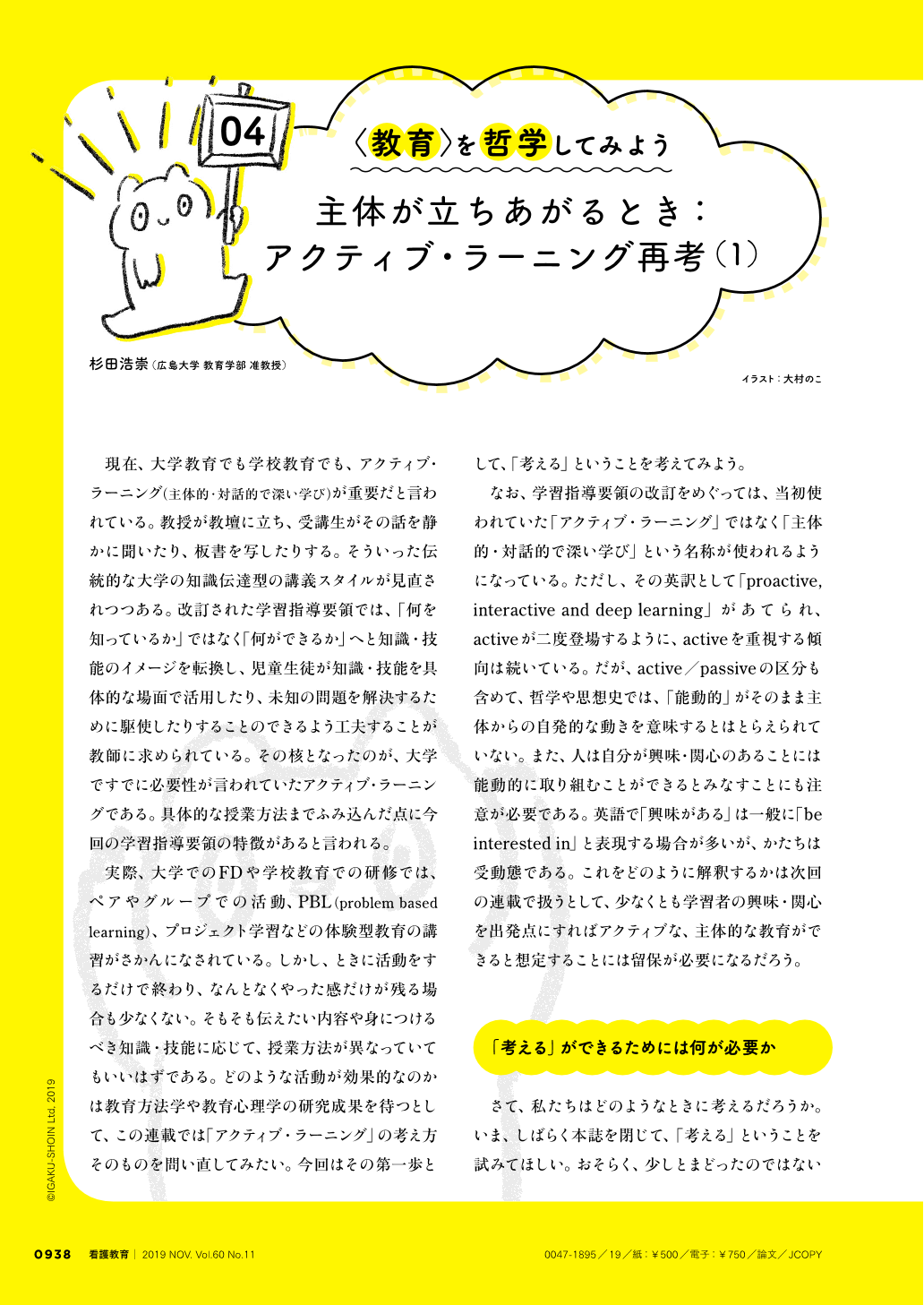
Copyright © 2019, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


