Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
はじめに
失語症研究の方法としては,個々の研究目的とも関連して,特定の専門領域での理論と技術を適用した種々のアプローチ(例えば,言語学的,実験音声学的,言語病理学的,その他)が試みられている.
しかし,失語症が大脳の病変に由来する言語行動の破綻ないし変容であるかぎり,また失語症研究の重要な目標の1つが言語行動の神経生理学的メカニズムの解明にあるかぎり,大脳病変を完全に切り離した失語症研究はありえない.その意味で,脳と行動脚注1)との関係についての系統的な検索を目標とする科学としての神経心理学1,2)は,失語症研究のいわば必然的な理論的枠組を提供するものといえよう.
事実,100年以上にわたる失語症研究の歴史をふりかえると,その主流をなしてきたのは,言語症状から脳の病態機構を推測する,すなわち脳と言語との関係を究明する,神経心理学的アプローチにほかならない.こうした脳と言語(行動)との関係のとらえ方も,幾多の変遷を経て今日に至っている.Gallの骨相学から始まった大脳局在論はBrocaを経て19世紀後半にその黄金時代を迎えるが,やがてこの局在論への反省および反論の時代へと移行する.そして現代は,損傷部位と言語症状との対応に再び大きな関心が集中する局在論的指向への回帰の時代といえそうである.
無論,近年における神経学・神経科学の発展には目をみはるものがあり,生体における損傷部位の同定の精度にも著しい改善がみられている.また,言語症状の捉え方も,より系統的かつ詳細なものとなりつつある.したがって,脳-言語の対応関係の同定も,以前に比べてより確かなものとなってきたような印象を受ける.しかし,果たして本当にそうであろうか.
最近のいわゆる神経心理学的研究をみると,特定の言語症状(群)(心理学的レベルの現象)と脳の局在病変(神経・生理学的レベルの現象)との間に,あたかも一対一の対応関係を想定しているかのような,いわば,かつての局在論の現代版ともいえそうな考え方に根ざしているのではないかと思われるアプローチが少なくないように見受けられる.このような想定が妥当性を欠くものであることは,過去100年余りの知見からも明らかである.局在決定それ自体は,障害された行動の神経・生理学的説明とはなりがたく,ましてや,その心理学的説明とはなり得ない.脳と行動との関係とはどういうことなのかをあらためて吟味する必要があるように思われる.
本稿では,こうした観点に立ち,失語症への神経心理学的アプローチの現状における問題点を整理すると共に,脳における言語の仕組みの究明を,より実り多いものとするための研究の方向を探ってみることにしたい.
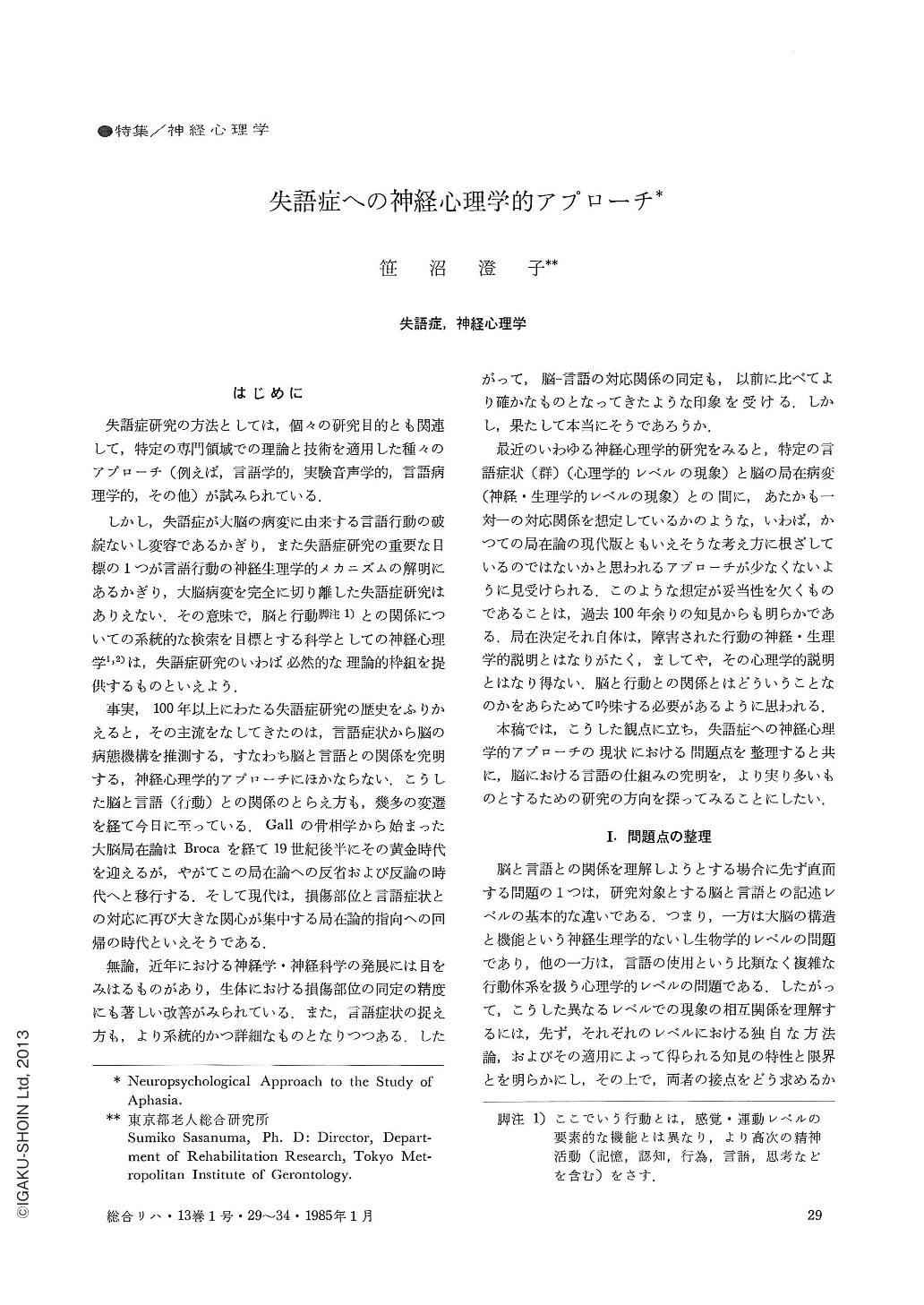
Copyright © 1985, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


