- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
リカバリーは,もともと1980年代前半に身体疾患や身体障害において注目されていた概念であったが,徐々に1980年代後半から精神疾患においても注目を集めるようになり,現在までさまざまな観点から注目を集めている。こうした方向性は,精神疾患の実体験を有するメンタルヘルスサービスのコンシューマーやクライエントが,論文や雑誌への投稿,もしくは書籍出版などを通じてその経験を記述し,そこからリカバリーがメンタルヘルス領域で影響力を持つようになっていったことに端を発する。例えば,以下に挙げたAnthony(1993)の提案によるリカバリー志向の精神科医療に関するビジョンは,臨床上示唆に富む内容であると同時に,従来の精神科医療が機能してきたスキームからの逸脱をそのサービスを提供する人々に促しているかのように映る。
リカバリーに注目したメンタルヘルスシステムの基本仮説(Anthony, 1993)/1. リカバリーは専門的介入がなくても生じうる/2. リカバリーの共通した土台は,その必要性を信じその人のそばにいてくれる人の存在である/3. リカバリーのビジョンは精神疾患の原因に関するセオリーとして機能しない/4. 症状が再発したとしても,リカバリーは生じうる/5. リカバリーは症状の頻度や期間を変化させる/6. リカバリーはまっすぐな道のりのように感じられない/7. 時に,疾患による結末からのリカバリーの方が,疾患そのものからのリカバリーより困難である/8. 精神疾患からのリカバリーは,その人が実は精神疾患ではなかったことを意味しない
看護学においては,1971年にドロセア・E・オレムが発表したオレム看護論において,セルフケアという概念が看護実践における中心的な概念として提唱されるようになり,それをパトリシア・R・アンダーウッドが精神科看護学においてさらに発展させた,オレム-アンダーウッド・セルフケア看護モデルがある。近年では,こうした看護学の土台の上にチャールズ・A・ラップのストレングスモデルを取り入れた看護実践の提案などもある。このように看護実践においては,従来から病理を中心とした介入だけではなく,その人の強みやリソースに注目した実践が提唱され,積み重ねられている。この点で,上述のリカバリーの基本仮説との近接性は高い職種である。こうした看護業務において,2020年に発表されたリカバリーを目指す認知療法は新たにどういった展開を精神科看護学にもたらす可能性があるのか。
この治療の中心的な開発者の一人であるAaron T. Beck(以下その業績に敬意を込めてBeck先生とする)は,認知行動療法はリカバリーとの親和性が高いとしながらも,2011年に認知療法をリカバリーに適応していくという,当時初めての講演を依頼された際に,改めて「リカバリーとは?」と疑問を持ったという。ベック研究所のウェブサイトからの記事によると,当時のBeck先生は,ベック研究所とオーサーエバンス率いるthe Philadelphia Department of Behavioral Health and Intellectual Disabilities Services(DBHIDS)との提携関係のもとで,認知行動療法の普及を米国におけるプライベートな臨床実践から,多様なコミュニティセッティングへと拡大することに取り組み,そこで従来の認知行動療法と同等の成果を確認していた(Creed et al, 2016)。その過程において,取り組みの対象を共同開発者であるポールグラントらと一緒に,重篤なメンタルヘルス状態の実体験を持つ人々へと,さらに広げていった。このようにCT-Rは,ベック研究所の認知行動療法が米国のメンタルヘルスにおける多様なセッティング,そして診断横断的な幅広い治療対象へと展開していく過程の中で発展した治療として捉えることができる。言い換えれば,ベック研究所の認知行動療法そのものが,リカバリーを目指して発展していく過程をCT-Rを学ぶ体験から垣間見ることができる。
ここでは,こういった視点を取り入れながら,CT-Rを日本の精神科訪問看護や精神科入院病棟において取り入れていくための教育実践を行ってきた筆者の経験を検討してみたい。特に注目したいのは,現場の最前線において,リカバリーモデルをどのように看護実践と関連した医学モデルに統合していくのかという,CT-Rの観点である。
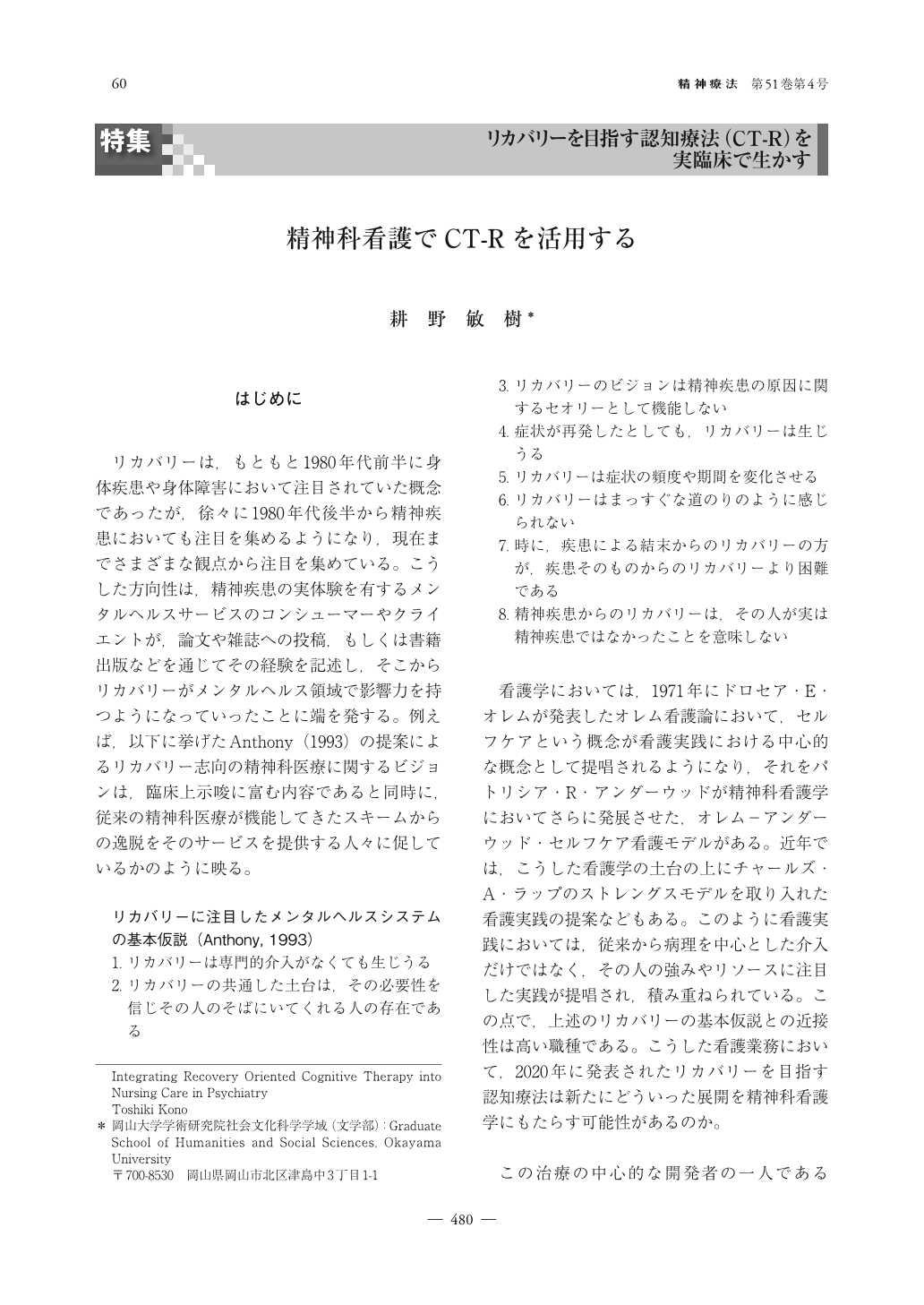
Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.


