- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
当院では,症例の診立てにおいて,認知行動療法の症例概念化を臨床に活用してきた。従来の症例概念化は,個人のスキーマに注目する縦断的概念化,症状の悪循環モデルに基づく説明的概念化(横断的概念化),さらには非適応的な認知・行動パターンを捉えた記述的概念化(横断的概念化)を中心に行われてきた。これらの手法においても,患者本人の強みや適応的スキーマに一定の言及がなされることはあったものの,主たる焦点は一貫して,症状やネガティブ・非適応的な側面に置かれていた。このアプローチは,症状の軽減・除去を主眼とする医療モデルに合致し,臨床家にとっては親しみやすいものであった。多職種で治療にあたる場合も,各職種が専門的視点から本人の症状や脆弱性に着目して介入を行っていた。その結果,個別最適化された介入がなされる一方で,各職種間に一貫性が乏しくなるという課題も生じていた。
しかし,治療抵抗性を示す慢性統合失調症など,症状の改善が困難な個人に対しては,従来のアプローチでは症状や脆弱性の評価に留まり,具体的な介入戦略へとつながらない現状があった。特に精神科病院では,長期入院患者が多く,効果的な治療的介入を見出すことが困難な状況が続いていた。
こうした背景の中,日本にも紹介されたのがリカバリーを目指す認知療法(Recovery-Oriented Cognitive Therapy:CT-R)である(Beck, 2021)。CT-Rは,認知行動療法を基盤にAaron T. Beckらによって開発された,重度の精神障害を抱える人々のエンパワメントとリカバリーを促進するアプローチである。CT-Rでは,従来型の症例概念化をさらに発展させた枠組みとしてリカバリーマップを用いる。リカバリーマップでは,精神症状などの「チャレンジ(Challenges)」にのみ焦点を当てるのではなく,適応モード(Adaptive Mode)と呼ばれる「その人らしさ」や「ポジティブな自己体験」を重視する。そして,アスピレーション(Aspirations),すなわち夢・希望・生きがいといった要素を明確化し,それを中心に据えて治療を展開していく点が大きな特徴である。
多職種が関わる際には,本人のアスピレーションをチーム全体で共有し,それを実現するために各職種がどのように専門性を発揮できるか,という観点から介入戦略を練る。これにより,介入に一貫性が生まれ,より効果的な多職種連携医療の実現が期待できる。
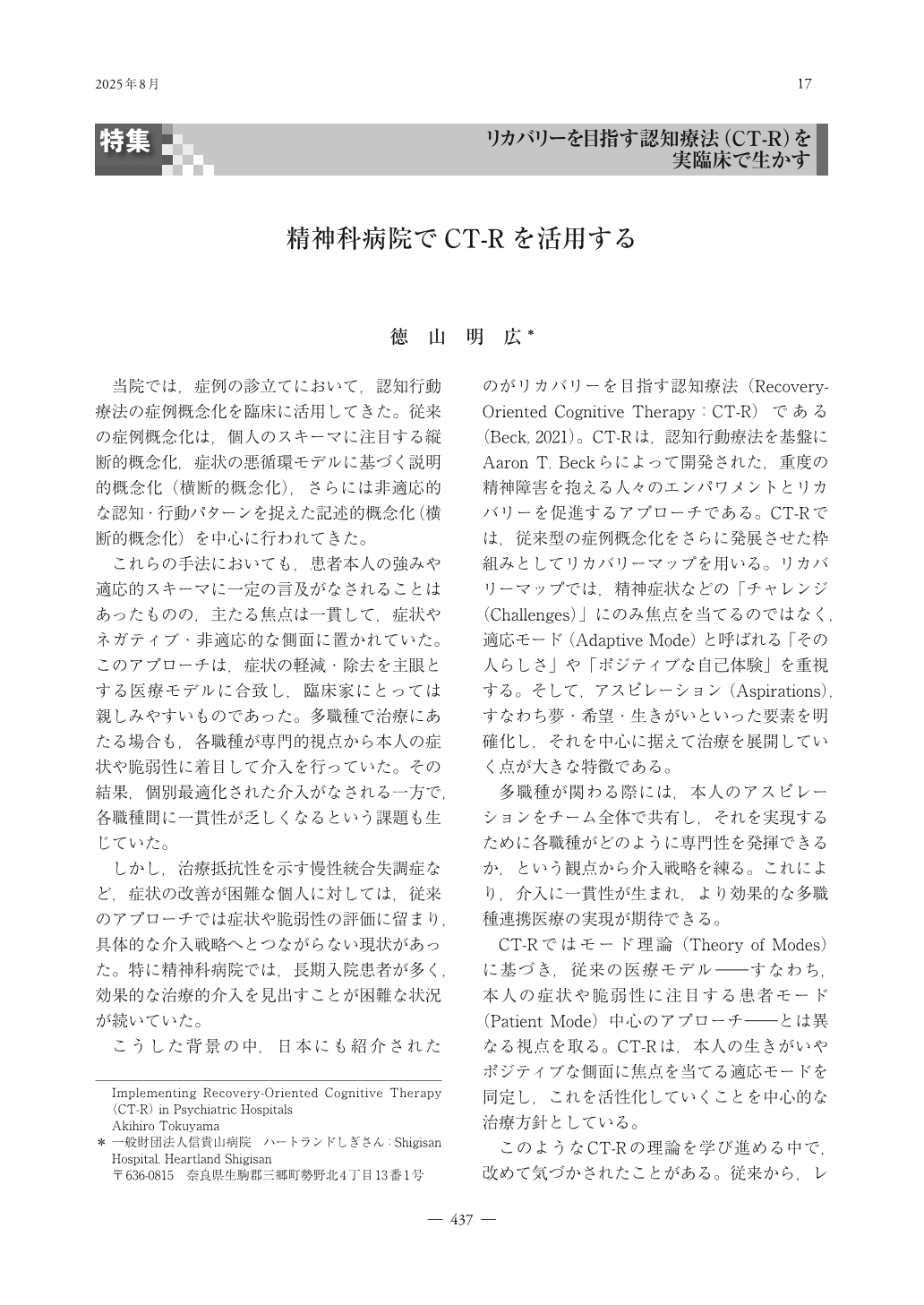
Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.


