- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
I はじめに
子どもたちが抱えるトラウマやアタッチメント形成不全は,学校において,時に子どもたちの「荒れ」の問題として顕在化する。このことにいち早く気づき,学校ぐるみで取り組みを進めてきたのが,大阪市立生野南小学校・田島中学校である。生野南小学校は,約1割の子どもたちが児童養護施設から通ってくるという状況にあり,2010年当時は,子どもたちの暴力や暴言などの深刻な「荒れ」に直面していた。しかし,生活指導,人権教育,教科指導などさまざま取り組みによって,「荒れ」は克服されていった。その後,当校の先生方が臨床心理学や社会福祉などの知見を学び,子どもたちのトラウマにアプローチしようと2016年度から開発し始めたのが「『生きる』教育」である。
「『生きる』教育」とは,子どもたちが直面する「人生の困難」を解決するために必要な知識を習得し,友だちと真剣に話し合うことで安全な価値観を育むことをめざす教育である。子どもたちにとって一番身近であり,心の傷に直結しやすいテーマをも授業の舞台にのせ,社会問題として捉えなおすとともに,授業の力で子どもたち相互にエンパワメントを生み出し,個のレジリエンスへつなげることがめざされている(小野ほか,2022,p.12)。
2018年度には,子どもたちの進学先である田島中学校においても,「性・生教育」として実践が始まった。2022年度には生野南小学校・田島中学校ともう一校の小学校が統合されて田島南小中一貫校となったものの,現在も「『生きる』教育」は継続的に実践されている。
両校の取り組みについては,すでに複数の書籍(今垣ほか,2024;大久保ほか,2025;小野ほか,2022など)で紹介されている。また西澤は,当校の実践を日本におけるトラウマ・インフォームド・エデュケーション(以下,TIE)として評価している(小野ほか,2024,p.15)。しかしながら,両校の実践のどのような点がTIEとして評価できるのかについては,十分に検討されていない。そこで本稿では,「『生きる』教育」プログラムの概要を紹介するとともに,そこにどのようなトラウマ研究の知見が織り込まれているのかについて検討する。
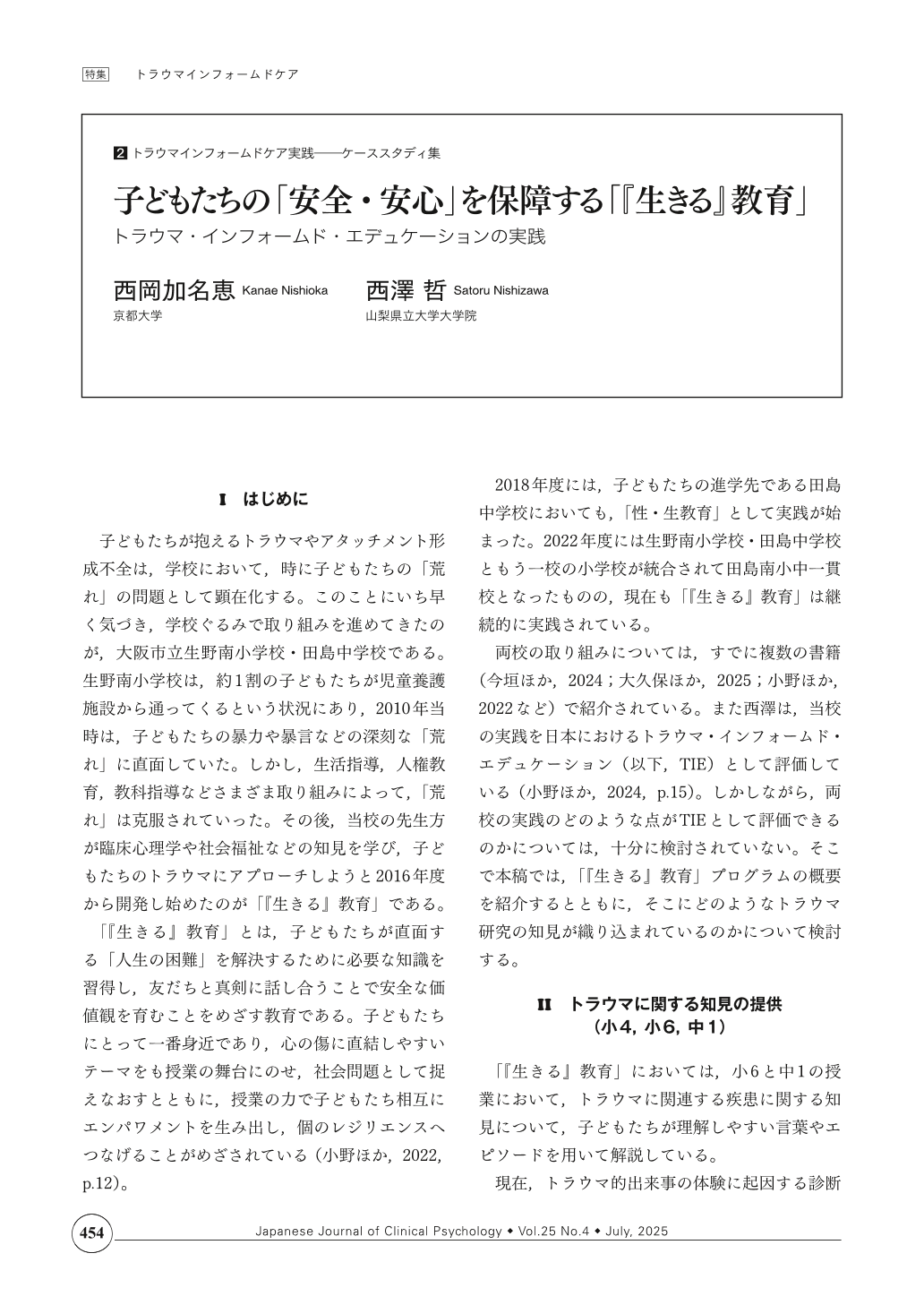
Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.


