- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
“言葉というものは発せられるときにすでに意は固定されていて,絶対といっていいほど伝達される側もその意のまま受け取ります。しかし,音楽は相対的に感受され,その意は心の内から生まれると思います。
更生というものも他から強要されるものでは無く,最終的には自分の内から生じるものだと僕は思います。ですからこの音楽活動ではこれまでには無い部分(内からなるもの)が満たされました”
これは,筆者が加害者の心理臨床において「大切な音楽」を媒介としたナラティヴ・アプローチを行ってきたなかで出会った,ある少年受刑者によるメッセージである。彼は“言葉”と“音楽”とを両極にあるものとして捉えており,司法のさまざまな手続きを経て刑務所に行き着いた彼にとって,まさに法的な言葉による“絶対的な”意味世界のなかに生きているということになるのかもしれない。
この“言葉”と“音楽”の対比を,Bruner(2002/ 2007)が示した「法的ナラティヴ」と「文学的ナラティブ」という2つのナラティヴに置き換えて考えてみたい。「法的ナラティヴ」とは,過去の現実の記録であり,一方,「文学的ナラティヴ」とは,日ごろなじんだ慣習や期待を覆し,現実を「仮定法化」するナラティヴ,あるいは可能なるもの,象徴的なものを見ようとするナラティヴである。少年にとって“言葉”は,絶対的な意味がすでに外から与えられた「法的ナラティヴ」そのものであり,一方で“音楽”は,イメージなど心の内に基づいた“言葉”で表しにくい出来事を指す。すなわち,「文学的ナラティヴ」という“言葉”の“音楽”的な側面にあたると考える。Bruner(2002/2007)が,これら2つのナラティヴは,ひとかたまりのパンの半分のように記憶と想像力との不安定な結合によって存在すると述べたように,両者はいわば共存的関係にあると筆者は考える。
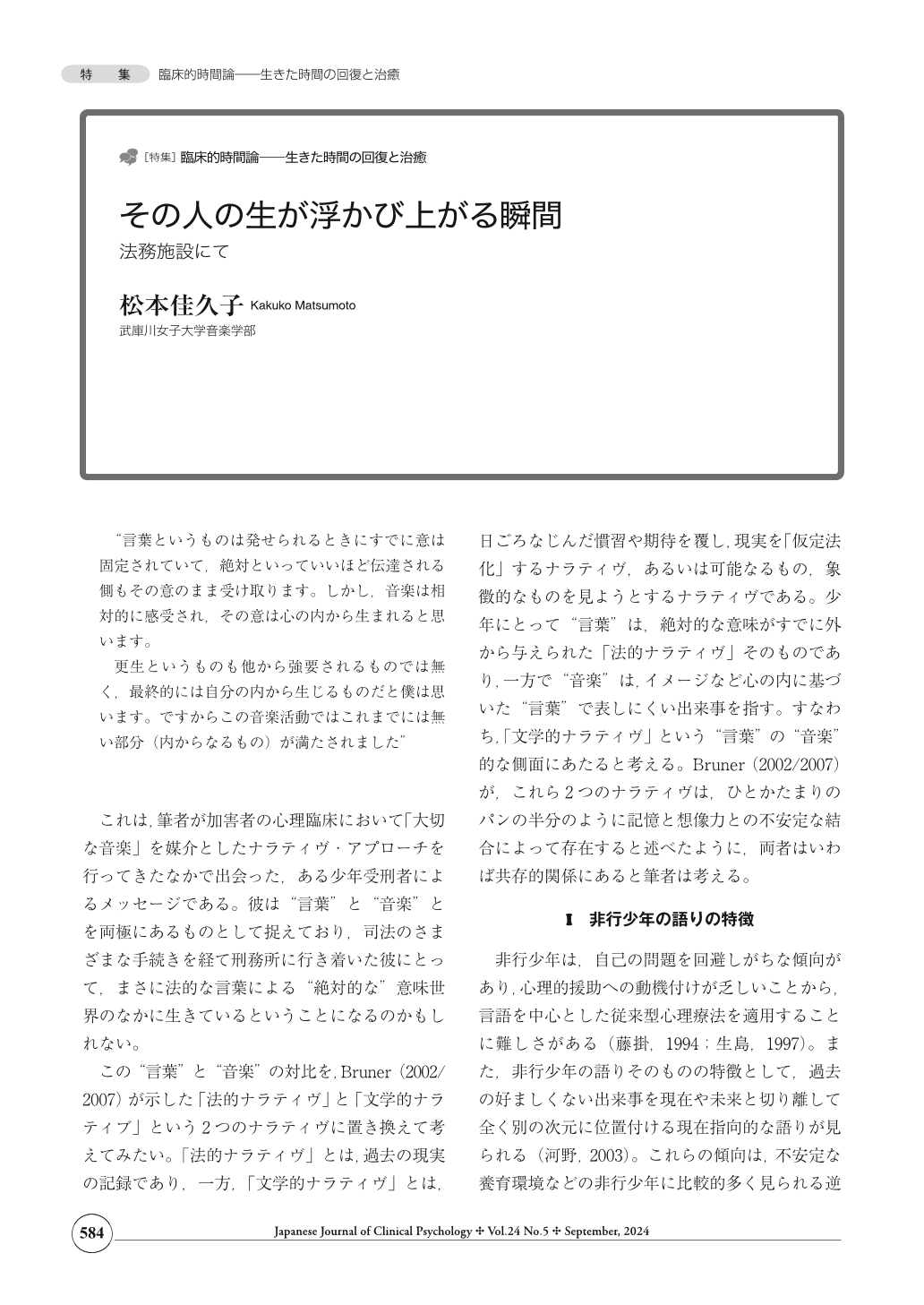
Copyright© 2024 Kongo Shuppan All rights reserved.


