特集 臨床的時間論―生きた時間の回復と治癒
「なじみの関係」が生み出すE系列の時間―認知症を有するいちさん(仮名)との会話
田崎 みどり
1
1長崎純心大学
pp.589-595
発行日 2024年9月10日
Published Date 2024/9/10
DOI https://doi.org/10.69291/cp24050589
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
I はじめに
認知症高齢者が示す,誤認であっても親近感や同類感に支えられた関係性を,室伏(1985)は「なじみの関係」注1)と称した。認知症高齢者と「なじみの関係」をつくることは問題行動の解消やQOLの向上,円滑なケアの提供等に役立つとされ(室伏,1985, 1998),看護・介護領域では認知症高齢者にアプローチする際の第一歩と捉えられている。
修士課程に在籍していた時,筆者は介護保険のデイケア(以下,DC)でフィールドワークを実践し,さまざまな利用者と関わる機会を得た(木下,2003;田崎,2022)。当時から「なじみの関係」は自明とされていたが,筆者にはなぜそのような関係性が生じるのか不思議でならなかった。
そこで筆者は,DC利用者いちさん(80代・女性,仮名)注2)との会話において「なじみの関係」が構成されるプロセスを臨床ナラティヴアプローチの観点から検討した(田崎,2022)。またそのプロセスと野村の時間論(2010, 2012, 2015, 2018, 2020)を用い,E系列の時間がいちさんの「主観的な時間」の回復につながることを示した(田崎,2023)。
「いま」の構成は,現在を維持するだけでなく「過去」や「未来」を構成する(田崎,2023)。E系列時間の構成には,「いま,ここ」を支えることにとどまらない意義がある。会話やダンスなど,E系列の時間にはさまざまなものがある(野村,2010, 2012, 2015, 2018, 2020)が,臨床実践における報告は少ない。本論ではいちさんとの会話場面をE系列時間の視点から捉え,その意義について検討する。
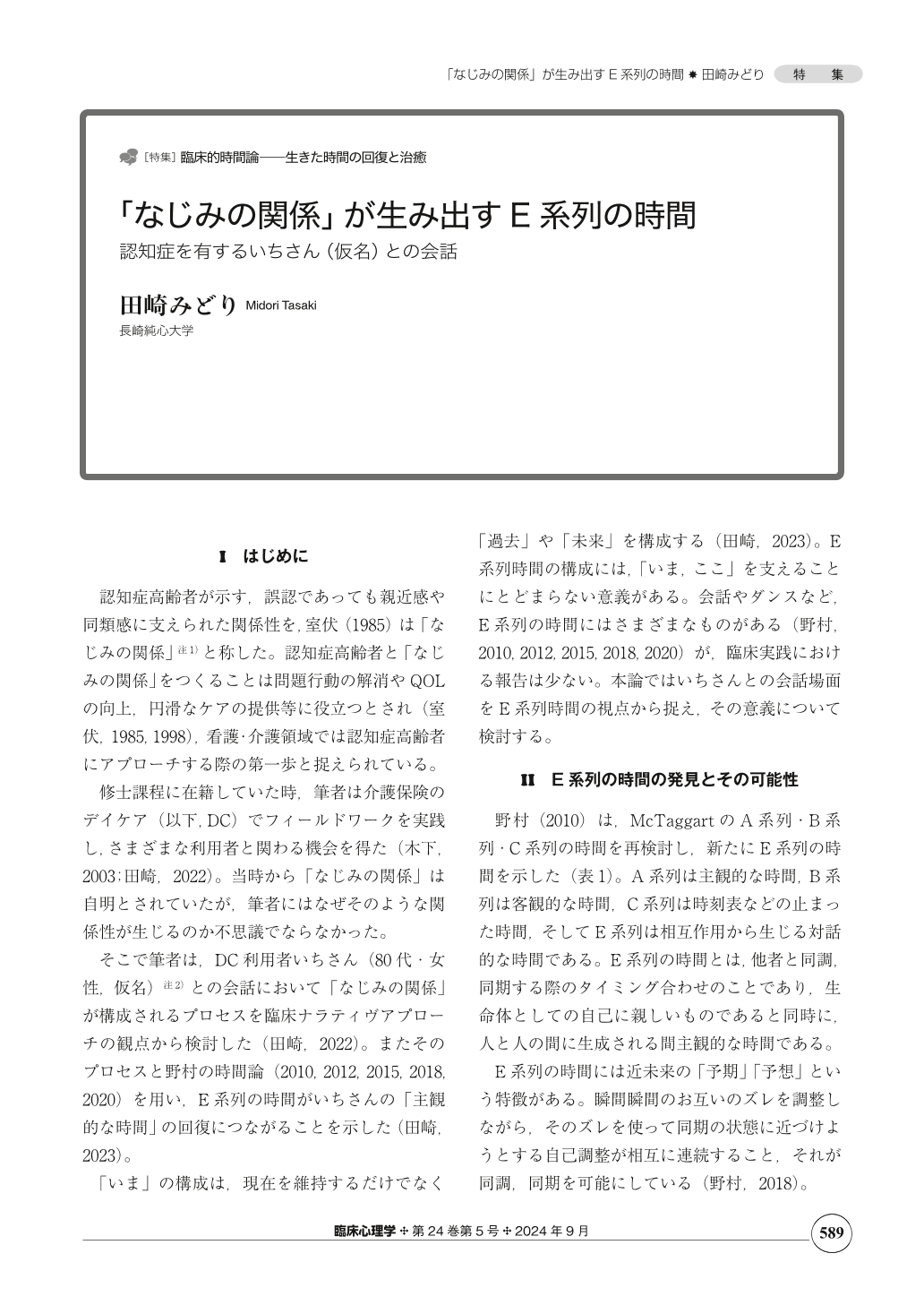
Copyright© 2024 Kongo Shuppan All rights reserved.


