- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
I 地域の時間,施設の時間
病院から地域への移行が進められるにつれて精神障害者に対する地域生活支援が次第に整えられ,これまでは精神科病院に長期に入院するしかなかった重度の精神障害者も地域で生活し支援を受けられるようになった。しかし,「地域」とは単に場所のことではない。少なくとも,私たちが精神医療・福祉を改革していくための実践の場として「地域」という時には,そうである。そこには病院や施設とは違う生き方があり,すなわち異なった人生の「時間」がある。私たちが人間としての生活を営む場所としての地域というものを考えれば,そこには生活する個々人の幾多の選択があり決断がある。それは放恣な自由ということではない。選択し決断することは新たな状況の束縛を引き受けることであり,そこからまた選択と決断をはじめる。その繰り返しを生きることが,地域で生活するということである。
その個人の選択と決断が生み出すのが,各々にとっての「時間」である。誰にとってもその人生は,その折々の選択と決断を起点として語られるものだ。自らの人生の変化も,生物学的・物理学的・客観的時間ではなく,連続する選択と決断の内実の変化として感じられるだろう。選択と決断を奪われた場所に,固有の人生の時間はない。
ひるがえって「施設」ではどうであろうか。施設とは,精神科病院,刑務所,高齢者施設,児童施設などのようなすべての時間をそこで過ごすことになるハードな施設から,学校や会社のように,ある時間をそこで強制的に過ごすことになるが生活の場は各人の家庭にあるものまで,幅が広い。これらには後述する施設としての特性の濃淡がある。ここでは,地域との対照を明確にすることと,地域精神医療と時間というテーマに限るために,精神科病院施設を中心に論を進める。
精神科病院は本来は言うまでもなく「病院」であり,そこは病気の治療という目的に限定される一時的滞在の場である。ところが,日本の精神科病院の実情は違っており,平均在院日数が277日,1年以上入院患者が60%,5年以上入院患者は30%以上を占めている現実がある。これは,30万人におよぶ精神科病院入院者の多くにとって,そこが病院ではなく施設であるということである。
このような人生の長い時間をそこで過ごさざるを得ない精神障害者にとって,精神科病院はGoffmanの言うところの「全制的施設」である(Goffman, 1961/1984)。全制的施設とは「生活の全局面が同一場所で同一権威に従って送られ」,「構成員の日常活動の各局面が同じ扱いを受け,同じ事を一緒にするように要求されている多くの他人の面前で進行」し,「毎日の活動の全局面が整然と計画され,一つの活動はあらかじめ決められた時間に次の活動に移」り,「様々の強制される活動は,当該施設の公式目的を果たすように意図的に設計された単一の首尾一貫したプランにまとめあげられている」ことを特徴とする施設である。
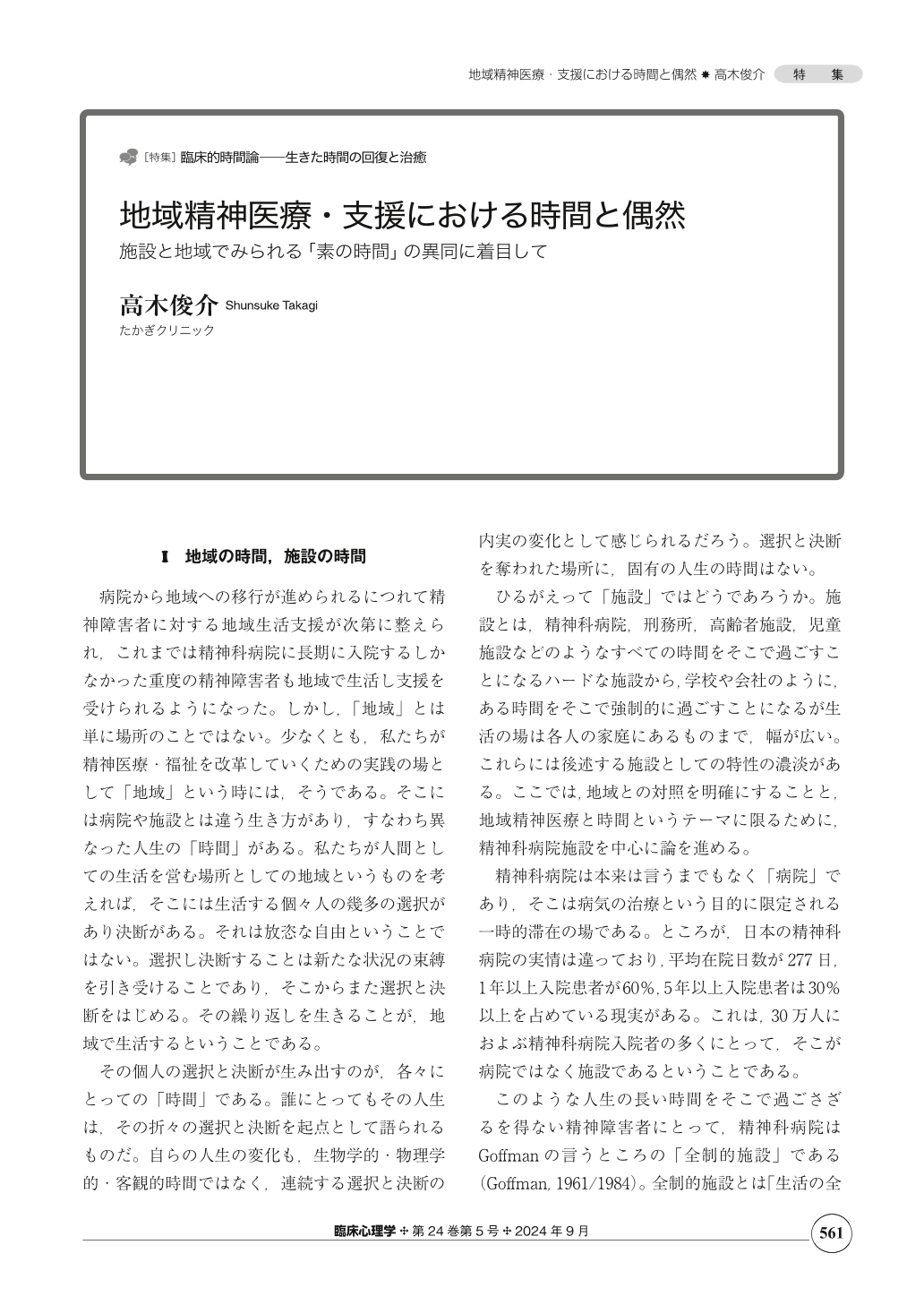
Copyright© 2024 Kongo Shuppan All rights reserved.


