- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
「臨床の多様な場面で,クライエントと出会い,同行する時間は心理臨床独自の質をもつ」(本特集・森岡正芳論文)
この「多様な場面」として,まずは病院臨床や学校臨床といった,多様な臨床領域が連想されます。他にも,年代,性別,主訴といったクライエントの多様な属性も思い浮かびます。
しかし,多様さはそれだけではありません。「地域性」という基本的な要素もそのひとつです。47の都道府県ごとや,山間部,沿岸部といった自然条件ごとに独自の地域性があり,それに応じた心理支援が展開されている実情があります。その中でもひときわ地域性が強く現れるのが,離島をはじめとする他とは隔離された僻地の臨床実践ではないでしょうか。
私は,約10年前に,夫の仕事の都合で沖縄県の石垣島に住むことになり,そこで2年間臨床実践を行う機会を得ました。当時,島に在住する臨床心理士は私一人だったため,スクールカウンセラーをはじめ,病院での心理検査業務,適正就学指導の発達検査業務,乳幼児健診の発達相談,警察の被害者支援カウンセリング,研修講師など,ひとつの自治体で必要とされる心理臨床の現場をほぼ一人で回っていました。
内地の都市部から沖縄県の離島に移って体感した地域性の違いは,鮮やかなコントラストをなしていました。都市部では当たり前になっている心理臨床の基本的枠組みも,離島ではそのままの運用は難しいことの方が多く,戸惑いと葛藤の日々でした。加えて,私が勤務した頃は,島の心理臨床萌芽期でした。数年在住していた前任者が2名おり,私は島に住む臨床心理士としては3人目。そのため,初めて継続的に臨床心理士が入る現場も多く,「カウンセラーって何?」という問いに答えながら,まずは存在を知ってもらうことが最優先となる時期でした。また,スクールカウンセラー業務は,沖縄県で中学校全校配置がスタートして間もなくの時期だったため,私だけでなく学校側も,スクールカウンセラーをどのように受け入れていくか,心理支援をどのように展開していくか,試行錯誤の段階でもありました。
そのような文脈では,「今ここから,どのようにクライエントの未来を生み出していくか」という時間の問題は,「守られた面接室の場で,適切なアセスメントを行い,面接を重ねた先に未来がある」ものとは限りませんでした。言い換えれば,離島の地域性と,心理臨床萌芽期という要素は,クライエントと共にいる時間に大きな影響を与えたのです。
そこで,当時の臨床実践の中心だったスクールカウンセラー業務を軸にしながら,離島という地域性に基づく「臨床的時間」の特質について考えてみたいと思います。
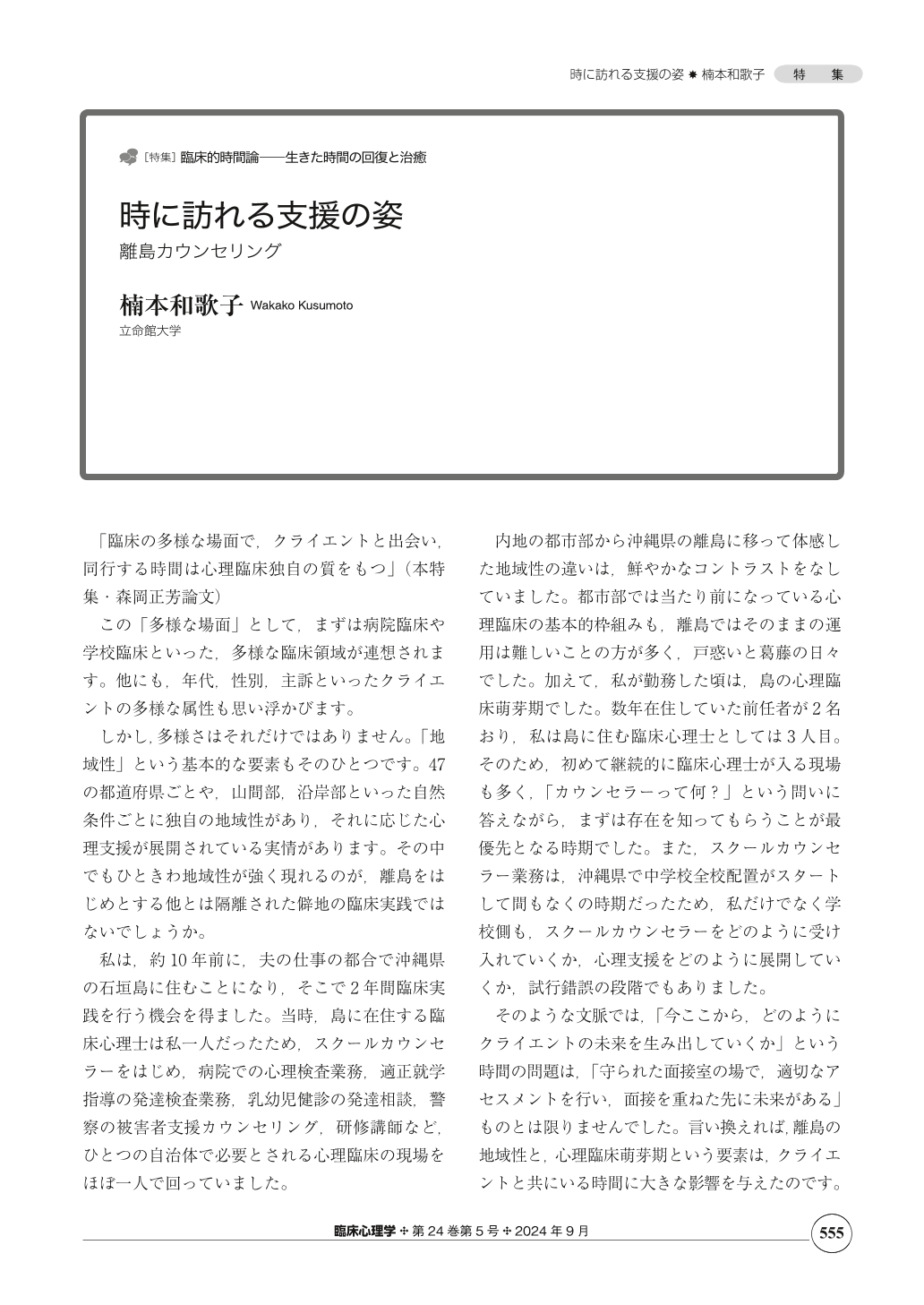
Copyright© 2024 Kongo Shuppan All rights reserved.


