- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
I はじめに
2005年「第12回多文化間精神医学会が佐々木勇之進会長(福間病院理事長)のもと,さる6月10~11日の両日にわたり福岡市のアクロス福岡で盛大に開催された。比較的天候にも恵まれ,「多文化共存共生の条件」をメインテーマに,多文化間精神医学会としては過去最大の650名の参加があった」注1)。この学会前日6月9日に,江口重幸と下地明友と私は樽味伸と歓談の場を持った。遺稿集『臨床の記述と「義」―樽味伸論文集』(星和書店)では,2005年7月10日,33歳で亡くなったとある。亡くなる1カ月前に私は樽味と再会しアクロス福岡近くの喫茶店に行ったことになる。その時,思いもかけないことが起きた。樽味は発表パワーポイントの入った記憶媒体USBを九州大学に忘れてきたと言うのだ。当時は前日に学会事務局にUSBを提出する原則があった。我々にしたら話したいことが山ほどあったのにUSBを取りに帰る樽味を待つ時間の方が長くなる喫茶店滞在となった。十分な歓談の時間は次の機会に必ずあると考え直して,翌日の樽味の発表のために時間を削る礼儀を守った。だから樽味の訃報は我々側が勝手にしていた約束が反故になった後悔を伴うものとなった。「次はゆっくりと話せるはずじゃなかったのか」と。翌日の樽味の発表「抗うつ薬で自己を語る―苦悩の慣用表現はどのように変容するのか」では,患者がSSRIを,まるで外車のディラーに来たように次から次に自分で主治医の樽味に注文する姿が出され,ディスチミア親和型うつ病「受療者」の様子が軽快に示された。笑いも聴衆から起きた。しかしこのうつ病の型の変化が病前性格論内で議論されてはならない。樽味は医学研究科大学院生として何とかエビデンスを取る苦労をしていると聞いていたが,それとは違う苦労をしていた気もする。当時,モダンからポストモダンへと変化するという大袈裟な物語をあげつらうことが(今も精神科医の代表で言うと内海健の態度に見られる)垣間見られたが,樽味は「対人恐怖」から「社会恐怖」へと恐怖症が変わるという具体的な変化に着目し,彼なりの内因性の考察を開始した,その苦労が襲っていたのだろう。それがここでの仮説である。Tellenbachが『メランコリー』(1976)で示す粘り強い記述を,樽味はディスチミア親和型うつ病型に関する論文でも参照している。メランコリー型うつ病をインクルデンツ(自分を閉じ込めるという布置)とレマネンツ(Kierkegaardがいう意味で自己存在の本来性を求める決断を怠った負い目という意味で「自己自身に遅れをとること」)の面から規定しようとしたTellenbachの所作は樽味にも必ず想起されたはずだ。つまり単なる内(エンドン)因性ではなく,エンドン・コスモス因性精神病として考えたのだろう。「人間と世界の相克(コヘレンツ)が乱れて,生命的事態が根底から不可能になるような障碍が存在する」というTellenbach(1976)に適う所作を取るつもりだったのだ。それが樽味の死により止まったことを江口は絶望的に語ることがある。だが現在の愛着障害関連の研究の発展で言うなら,明治期からの伝染病対策的強迫的母性衛生主義(日本には精神科病院を作らないで経費が伝染病対策に回された)はメランコリーの連鎖を産む,その代わりに戦争からの復興や高度成長期まではあらゆる関係は強迫的母性衛生主義に収まる。社長が親というような風味が時代に存在するようになる。ポストモダン化によるネグレクトの発生が強迫的母性衛生主義の後に生じることは今となると自明である。ネグレクトの連鎖の理由は,経営陣と組合の裏で提携した親子関係が機能を果たす代わりに,今や組合が崩壊し小泉内閣以降は非正規雇用が増え,人生の先輩後輩による一種のスポ根的「焼き入れ」場面だけが文脈から切り離されて代行されてしまうことによる。エンドン・コスモス因性から見ると,克服するものがない者に克服の追求を行えば類親子関係ではなく類先輩後輩に変わる。以上は,虐待の発生論から気づけることだが,樽味はまさに精神科臨床でこの変化の中に入りエンドン・コスモス因性として自らを考察しつつ「施療」していた。樽味(2004)はneglected anxiety disorderからneglected distressへの変化に着目している。対人恐怖症は内在化されており「克服するべきもの」として存在するが,社会恐怖は外在化され「治してもらうもの」として存在すると樽味は明確に書いている。中井久夫も指摘した時代精神の自責から他罰への変化である。「素の時間」も以上のような意味でエンドン・コスモス因に関わってないはずはない。ただこの対人恐怖から社会恐怖への変化があっても「素の時間」の書かれた時代は,まだ精神分裂病という呼称の時代であり,頑なに固まった制度に取り囲まれている時空間の精神科病院での出来事に樽味は直面していた。よってこの時期,2000年より前に樽味の働いた閉鎖病棟では,対人恐怖の克服の自責ドライブから精神分裂病を発病して,あくまでその後,孤独に閉鎖病棟にneglectedされた人々の姿を描いている。もちろんスタッフの側では,そのような内面化した強迫性を克服することから解放されて治してもらうべく外在化を既に経験した人がいたかもしれない訳だが。その後,現代社会にneglectedされた人々の問題として自責から他罰へ大きく時代精神が変わる中の臨床の姿の変化を,樽味なら外から眺望していないで描かざるを得なかっただろう。
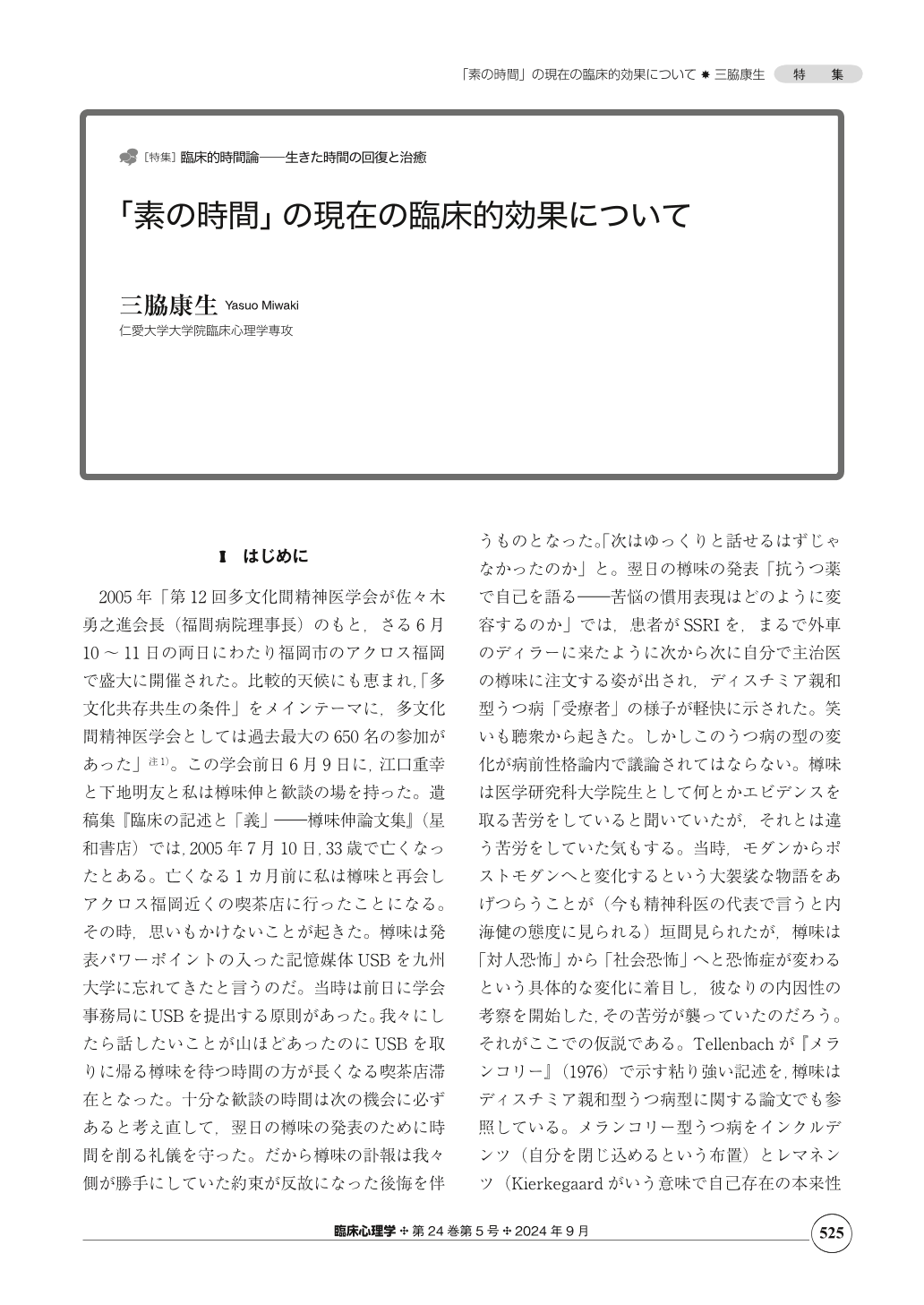
Copyright© 2024 Kongo Shuppan All rights reserved.


