Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
- 参考文献 Reference
内容のポイント Q&A
Q1 What? 学習障害とは?
文部科学省の定義では「学習障害とは,基本的には全般的な知的発達に遅れはないが,聞く,話す,読む,書く,計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すものである」とされている.一方で,医学的定義(DSM-5-TR)では「聞く・話す」能力の困難はコミュニケーション症群,「読む・書く・計算する・推論する」能力の困難は限局性学習症に分類されている.
Q2 Who? リハビリテーション診療を要する子どもにはどのような特徴があるか?
読みに困難を抱える子どもは,就学前の年長時の段階でも文字への興味を示さないことが多く,就学後に音読の困難や逐次読み(1文字ずつ読むたどたどしい読み方)が続くことで気づかれることが多くある.書きの困難については,カタカナ(例:ツ・シ・ソ・ン)の線の向きや運筆方向が習得しにくいこと,学習量が増える小学校2,3年生頃に漢字の習得が難しくなり気づかれることが多い.
Q3 When? Where? いつから,いつまで実施するのが適切か(時間と場所)?
学習障害は,その学習に関する症状からも就学後に気づかれることが多いことが特徴である.小学校高学年でようやく医療機関に相談に来る場合もあるが,この時点では既に学習性無力感に陥っている場合も多い.よってできるだけ早期からの学習支援が必要である.また小学校で受けられた適切な学習支援が中学校にも引き継がれていく必要があり,また高校入試等における合理的配慮の申請にも,医療機関としてその都度かかわっていくことが求められる.
Q4 How? どのように評価し,リハビリテーション診療を行うべきか?
学習障害の定義からも知的発達に遅れがないことを確かめる必要があり,WISC-ⅤやKABC-Ⅱといった知能検査の実施が必要となる.また知的能力と学習の習得状況を比較する必要もあるため,KABC-Ⅱの習得検査やSTRAW-Rを実施する必要がある.さらに読み書きが困難な要因を知るには,音韻認識能力,自動化能力,語彙力,視覚認知能力等の検査を実施する必要がある.
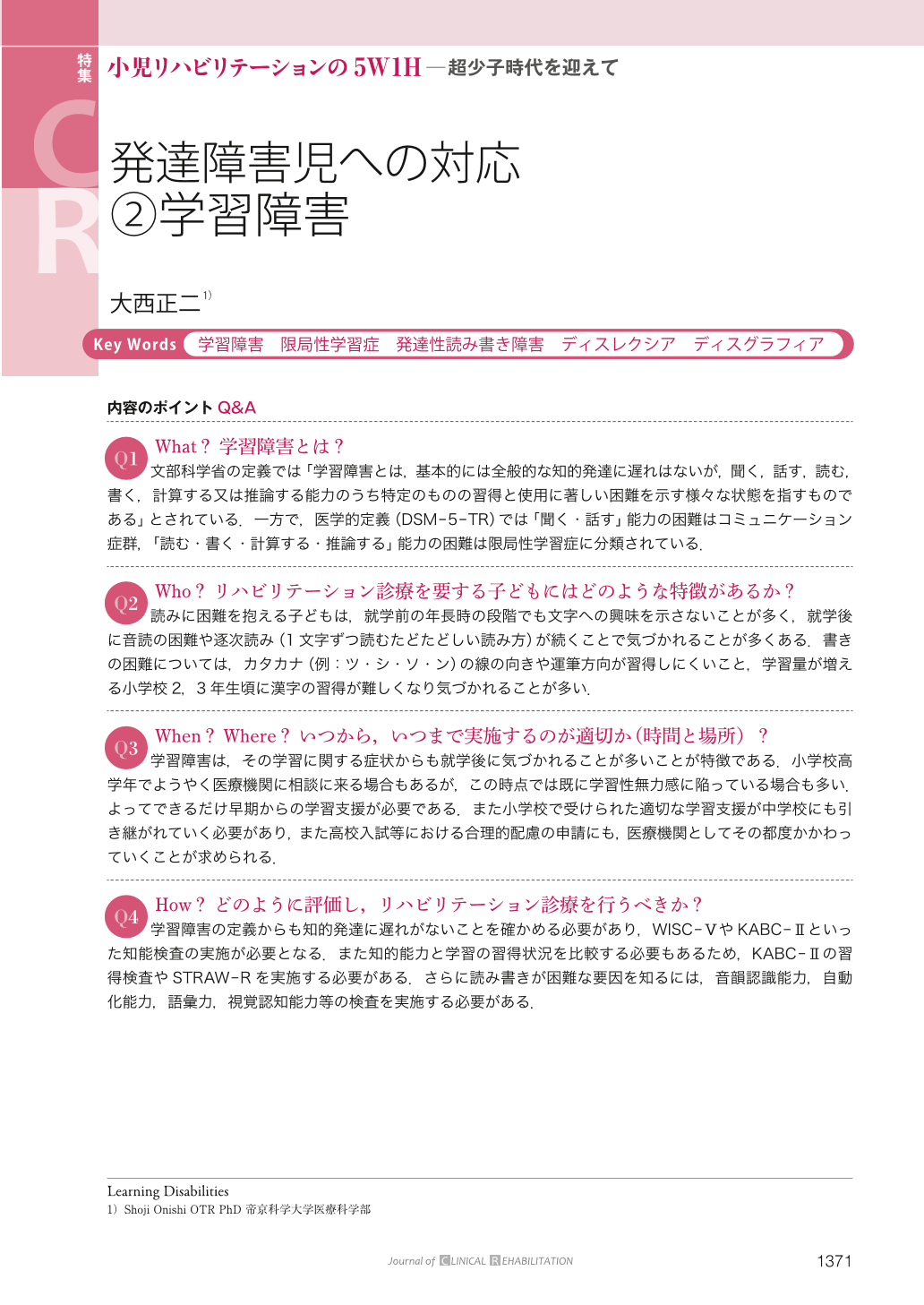
Copyright© 2025 Ishiyaku Pub,Inc. All rights reserved.


