連載 食塩にまつわる新知見TOPICS②
食塩摂取量が増えると飲水量は減少する?
-ナトリウム利尿による水喪失と尿素による水保持
北田 研人
1
Kento Kitada
1
1香川大学医学部 薬理学
pp.230-234
発行日 2025年8月1日
Published Date 2025/8/1
DOI https://doi.org/10.32118/cn147020230
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
連載初回となる前回は,健康なヒトでも体内のナトリウム量は一定ではなく,食塩摂取量にかかわらずリズムをもって体内ナトリウム量は変動しており,皮膚や筋肉などの組織がそのリザーバーとして機能しているという新概念を概説した.これらの概念は,主にナトリウムの体内動態に着目したものであった.連載2回目となる今回は,ナトリウムと体内で密接に関連する「水」の動態,とくに食塩摂取量の変化が飲水量や尿量に与える影響について,新たなTOPICSを紹介する.
「塩辛いものを食べると喉が渇き,水を多く飲む」,「過剰に摂取した水とナトリウムは,腎臓からのナトリウム利尿によって排泄され,尿中ナトリウム排泄量と尿量も増える」というのは,現在の一般的な概念であろう.実際に,ナトリウムは生体内の主要な浸透圧物質であり,尿中で増加したナトリウムは浸透圧により水を引き込み,利尿を起こし,尿量を増加させると理解されている(いわゆる「ナトリウム利尿」).しかし,これらの概念もまた,第1回で概説したナトリウムバランスの旧来の考え方と同様に,主に短期間の実験に基づいて確立されたものである点に留意が必要である.とくに,食塩摂取後の短期的な口渇感と,長期間にわたる実際の24時間飲水量は必ずしも一致しない,という点がポイントである.それでは,Mars500 studyのような長期間のナトリウム・体液バランス研究では,食塩摂取量の変化に対して,飲水量や尿量はどのように変動したのであろうか.
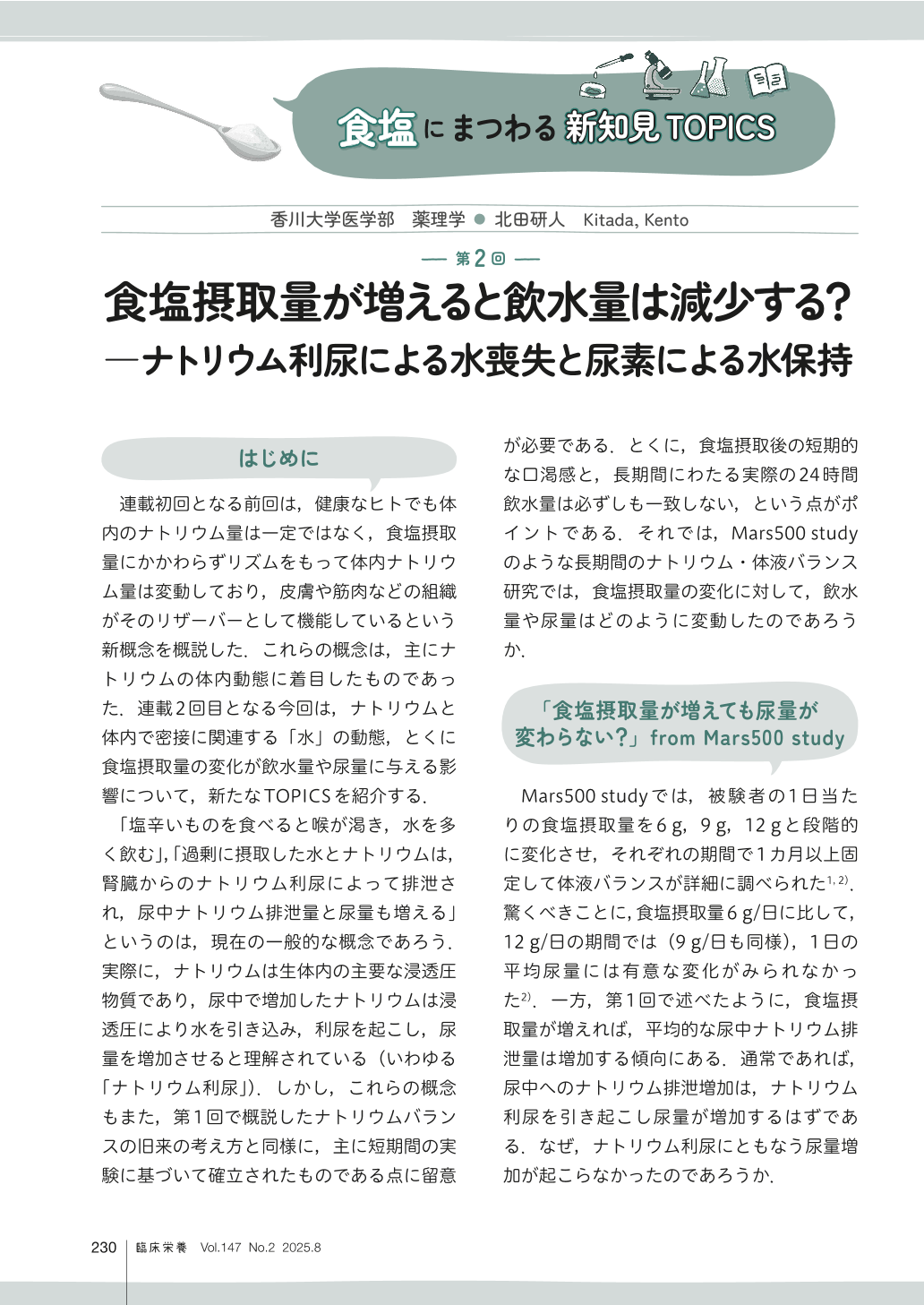
Copyright © 2025 Ishiyaku Pub,Inc. All Rights Reserved.


