連載 EBN実践につなげる! 栄養疫学研究最新トピックス⑥
随時尿を使用する食塩摂取量評価に関する最近の動向
上地 賢
1
Ken Uechi
1
1東京科学大学大学院 保健衛生学研究科 公衆衛生看護学分野
キーワード:
減塩対策
,
食塩摂取量
,
妥当性評価
,
24時間蓄尿
,
随時尿
Keyword:
減塩対策
,
食塩摂取量
,
妥当性評価
,
24時間蓄尿
,
随時尿
pp.108-113
発行日 2025年7月1日
Published Date 2025/7/1
DOI https://doi.org/10.32118/cn147010108
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
日本において食塩の過剰摂取は公衆衛生上の主要な課題である.食塩の過剰摂取は血圧の上昇と,引き続く循環器血管,脳血管疾患の発症と関連する.減塩はその降圧効果によりこれらの疾患発症に予防的に働くことも知られている.「国民健康・栄養調査」の結果によると,2010年以降の日本人集団の平均食塩摂取量は10 g/日前後で推移している.この値は世界保健機関(WHO)の目標とする5 g/日のおよそ2倍に当たる.
より強力に減塩対策を推し進めるうえでも食塩摂取の現状,過剰摂取に至る背景の詳細な調査が欠かせない.日本人成人男女を対象とした疫学調査では,食塩の主な摂取源である食品は調味料類であった1).食卓や調理中の調味料使用などの個人の食行動に由来するもの,加工食品を摂食することによるものが摂取量全体のおよそ50%ずつを占めると推定されている1).したがって,減塩対策が効果的であるためには,個人の減塩行動の促進に加え,それを可能とする環境の整備,減塩された加工食品の開発・流通といった社会環境の変化を含む必要がある.
このような現状を踏まえると,現状の把握や対策の評価のためには個人や集団の食塩摂取量を正確に把握することが重要となる.本稿では,従来の食事調査ではなく生体指標である尿を用いた測定方法について整理し,とくに随時尿を用いた方法にまつわる近年の議論を紹介したい.
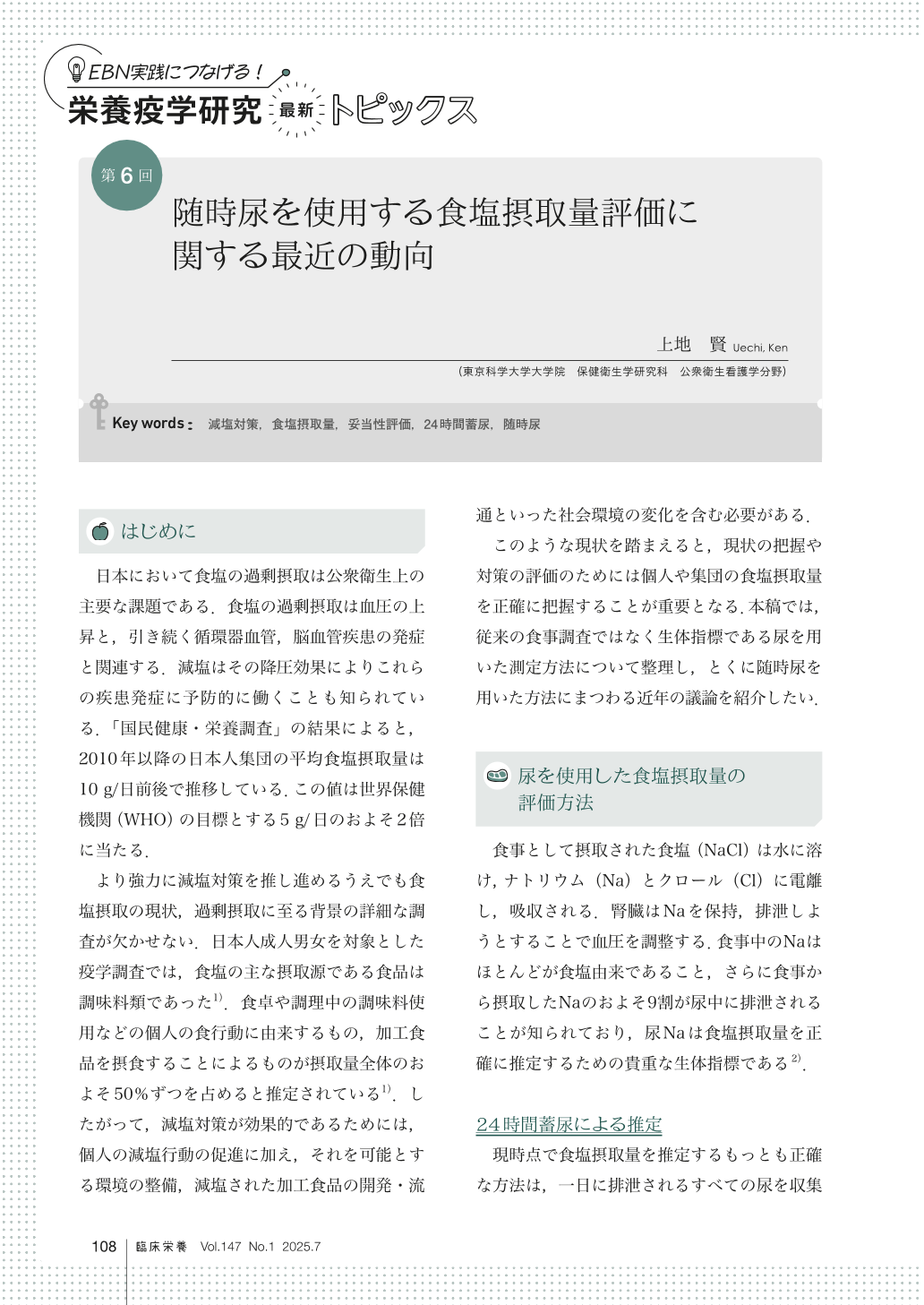
Copyright © 2025 Ishiyaku Pub,Inc. All Rights Reserved.


