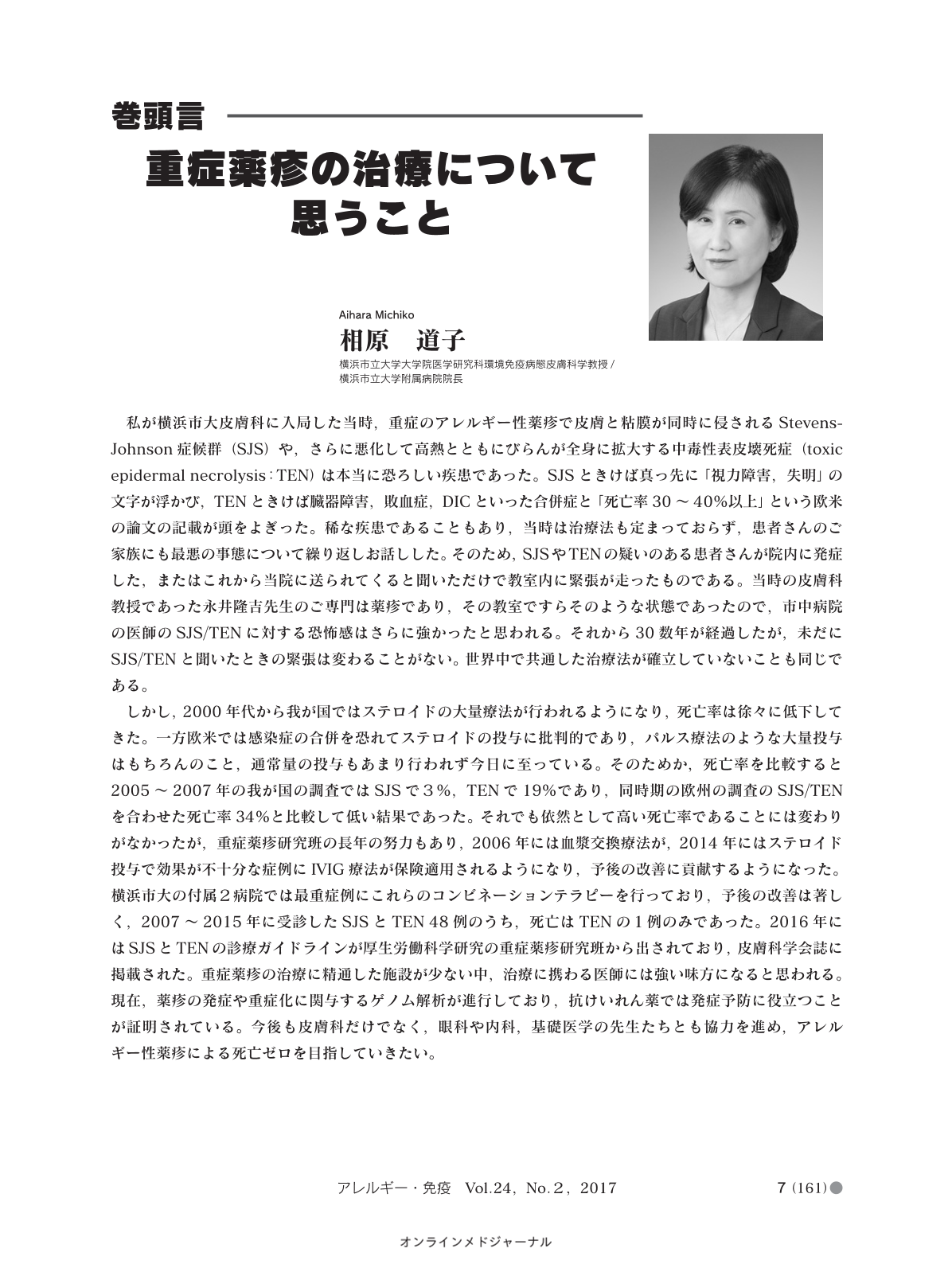- フリーアクセス
- 文献概要
- 1ページ目
私が横浜市大皮膚科に入局した当時,重症のアレルギー性薬疹で皮膚と粘膜が同時に侵されるStevens-Johnson症候群(SJS)や,さらに悪化して高熱とともにびらんが全身に拡大する中毒性表皮壊死症(toxic epidermal necrolysis:TEN)は本当に恐ろしい疾患であった。SJSときけば真っ先に「視力障害,失明」の文字が浮かび,TENときけば臓器障害,敗血症,DICといった合併症と「死亡率30~40%以上」という欧米の論文の記載が頭をよぎった。稀な疾患であることもあり,当時は治療法も定まっておらず,患者さんのご家族にも最悪の事態について繰り返しお話しした。そのため,SJSやTENの疑いのある患者さんが院内に発症した,またはこれから当院に送られてくると聞いただけで教室内に緊張が走ったものである。当時の皮膚科教授であった永井隆吉先生のご専門は薬疹であり,その教室ですらそのような状態であったので,市中病院の医師のSJS/TENに対する恐怖感はさらに強かったと思われる。それから30数年が経過したが,未だにSJS/TENと聞いたときの緊張は変わることがない。世界中で共通した治療法が確立していないことも同じである。 しかし,2000年代から我が国ではステロイドの大量療法が行われるようになり,死亡率は徐々に低下してきた。一方欧米では感染症の合併を恐れてステロイドの投与に批判的であり,パルス療法のような大量投与はもちろんのこと,通常量の投与もあまり行われず今日に至っている。そのためか,死亡率を比較すると2005~2007年の我が国の調査ではSJSで3%,TENで19%であり,同時期の欧州の調査のSJS/TENを合わせた死亡率34%と比較して低い結果であった。それでも依然として高い死亡率であることには変わりがなかったが,重症薬疹研究班の長年の努力もあり,2006年には血漿交換療法が,2014年にはステロイド投与で効果が不十分な症例にIVIG療法が保険適用されるようになり,予後の改善に貢献するようになった。横浜市大の付属2病院では最重症例にこれらのコンビネーションテラピーを行っており,予後の改善は著しく,2007~2015年に受診したSJSとTEN 48例のうち,死亡はTENの1例のみであった。2016年にはSJSとTENの診療ガイドラインが厚生労働科学研究の重症薬疹研究班から出されており,皮膚科学会誌に掲載された。重症薬疹の治療に精通した施設が少ない中,治療に携わる医師には強い味方になると思われる。現在,薬疹の発症や重症化に関与するゲノム解析が進行しており,抗けいれん薬では発症予防に役立つことが証明されている。今後も皮膚科だけでなく,眼科や内科,基礎医学の先生たちとも協力を進め,アレルギー性薬疹による死亡ゼロを目指していきたい。