- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
付帯研究29
死別後悲嘆・複雑性悲嘆に伴う生産性低下(労働損益)
細川 舞⁎1,藤澤 大介⁎2,伊藤 正哉⁎3,中島 聡美⁎4,竹林 由武⁎5
⁎1岩手県立大学看護学部/がん看護専門看護師,⁎2慶應義塾大学 医学部 医療安全管理部,⁎3国立精神・神経医療研究センター 認知行動療法センター,⁎4武蔵野大学 人間科学部,⁎5福島県立医科大学 医学部
はじめに
悲嘆(grief)とは,「身近な原因に対する正常で適切な悲痛な反応.症状は自己限定的で,時間の経過とともに徐々に落ち着く」と定義されている1).悲嘆は,愛する人を失ったことへの自然な反応であるが,ごく一部の人々にとっては強い悲嘆が持続し,その症状は日常生活の継続にも影響を与えてしまうといわれている2).死別後に一定期間経過しても持続していて医学的関与が必要となる悲嘆は,複雑性悲嘆(complicated grief:CG)と呼ばれ,ICD-11 (2019)やDMS-5-TR (2022)で遷延性悲嘆症(prolonged grief disorder)として精神障害に位置付けられた3).複雑性悲嘆が健康に及ぼす影響は日本でも実証されているが,それに伴う社会的コストについては明らかにされていないため,CGが社会活動に与える影響を明らかにすることは重要である.
付帯研究30
終末期がん患者を介護する家族の介護休暇および介護休業制度の利用状況とその利用を阻害する因子(バリア)に関する調査
田中 雄太⁎1,関根 龍一⁎2
⁎1秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻看護学講座臨床看護学分野,⁎2亀田総合病院疼痛・緩和ケア科
はじめに
国民調査では,治らない病気になったら自宅で最期を過ごしたいと答える人が54.6%と半数を超えるが1),わが国のがん患者の在宅死亡率は,全国平均で8.3%と依然として低率である2).条件が揃えば優れたケアを受けられる在宅緩和ケアだが,がん患者が自宅で最期を過ごせない理由として,“介護を担う家族に負担をかけたくない”という回答が全体の約80%と最多であった1).
2022年の全国調査では,介護をしている者のうち仕事をしている割合は58%と増加傾向である3).高齢の両親を介護する若年および中年世代は,なんらかの定職に就き社会経済を支える役割を担う.今後,少子高齢化がさらに進み,介護の担い手不足はいっそう深刻となり,仕事と親の介護との両立がごく普通の時代が訪れるだろう.介護休暇や介護休業の制度は仕事と介護との両立に有力な解決策と見込まれているが,介護をしている雇用者322万人のうち,介護休業などの制度を利用している人は37万人であり,制度利用率は11.6%にとどまっている現状がある3).
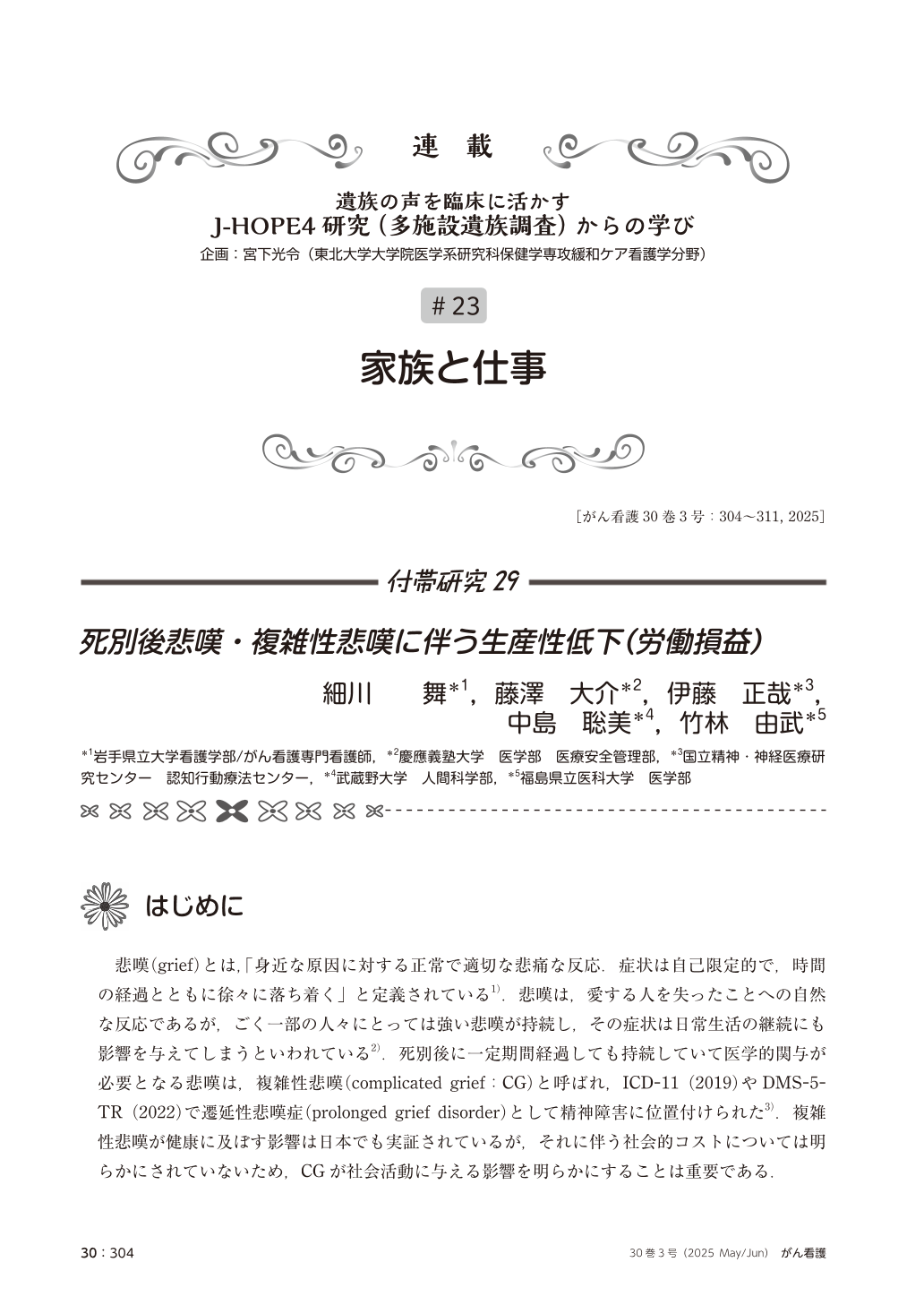
© Nankodo Co., Ltd., 2025


