- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
- サイト内被引用
はじめに
私は,自分ではずっと科学者のつもりでいたのだが,「科学とは何か」というような問いには,全く無関心であった。もともと,自分のしていることは科学なのであるという,全く根拠のない自信だけはあったのだが,よく考えてみると,この質問に答えるのはかなり難しい。結構ありがちな回答として,「科学とは真理の探究である」とか「科学とは現象の背後にある法則や因果関係を客観的に明らかにすることである」とか,なんとなくいってしまいそうである。本当に,科学とは真理や法則を明らかにするものなのだろうか。
かなり前から,若者の理科離れが進んでおり,科学技術立国である日本の将来が危ぶまれている。しかし,そもそも「科学とは何か」という,教育や学問の最も基盤となるような話が,日本の学校教育では教えられていないのではないだろうか。少なくとも私の経験では,「科学とは何か」を教えられた記憶はないのだが,これは一般的にそうなのだろうか。
岩田(2008)は,「日本では小中高の理科教育にせよ,大学・大学院教育にせよ,『科学とは何か』『科学的に考えるとはどういうことか』という議論がきちんとされ,教育されていることは希有である」と指摘している。仮に教育している学校があったとしても,それほど多くはなさそうである。
そこで今回は,わかっているようでわかっていないわりには,ちゃんと考えたことのない「科学とは何か」を考えてみたい。当然のことだが,科学哲学なる学問分野があることからもわかるように,これまでに多くの科学論が存在する。ここでそれらを網羅的に紹介しても,本連載の目的には沿わないと考えられる。大事な点は,「質的研究は科学なのか」という問いに,明確に答えが出せるような考え方を説明することである。したがって,ここでは池田清彦氏による構造主義科学論(池田,1988,1998,2007)に主に基づいて,必要に応じてほかの文献を参考にしながら,「科学」とは何かを考えてみたい。
構造主義科学論による「科学」の説明には,多様な表現が用いられているが,以下の言説は,科学の本質を述べたものと考えられるので,それらについて説明を加えていきたい。すなわち,
1)科学はオカルトが大衆化した所から生じた(池田,2007,p.12)
2)科学は真理をではなく同一性の追求をめざす(池田,1998,p.13)
3)科学とは,現象を構造によってコードし尽くそうとする営為である(池田,1998,p.106)
4)科学は見えるものを見えないものによって言いあてようとするゲームだ(池田,1998,p.106)
5)すべての科学理論は,何らかの不変の同一性によって,変なるものをコードする構図になっている(池田,1998,p.114)
などである。
はじめはわかりにくい表現かもしれないが,これを読んだ後では,このような構造主義科学論の考え方が,現実の科学者の研究活動や内容をよく言い当てていると思えるように解説できればと考えている。
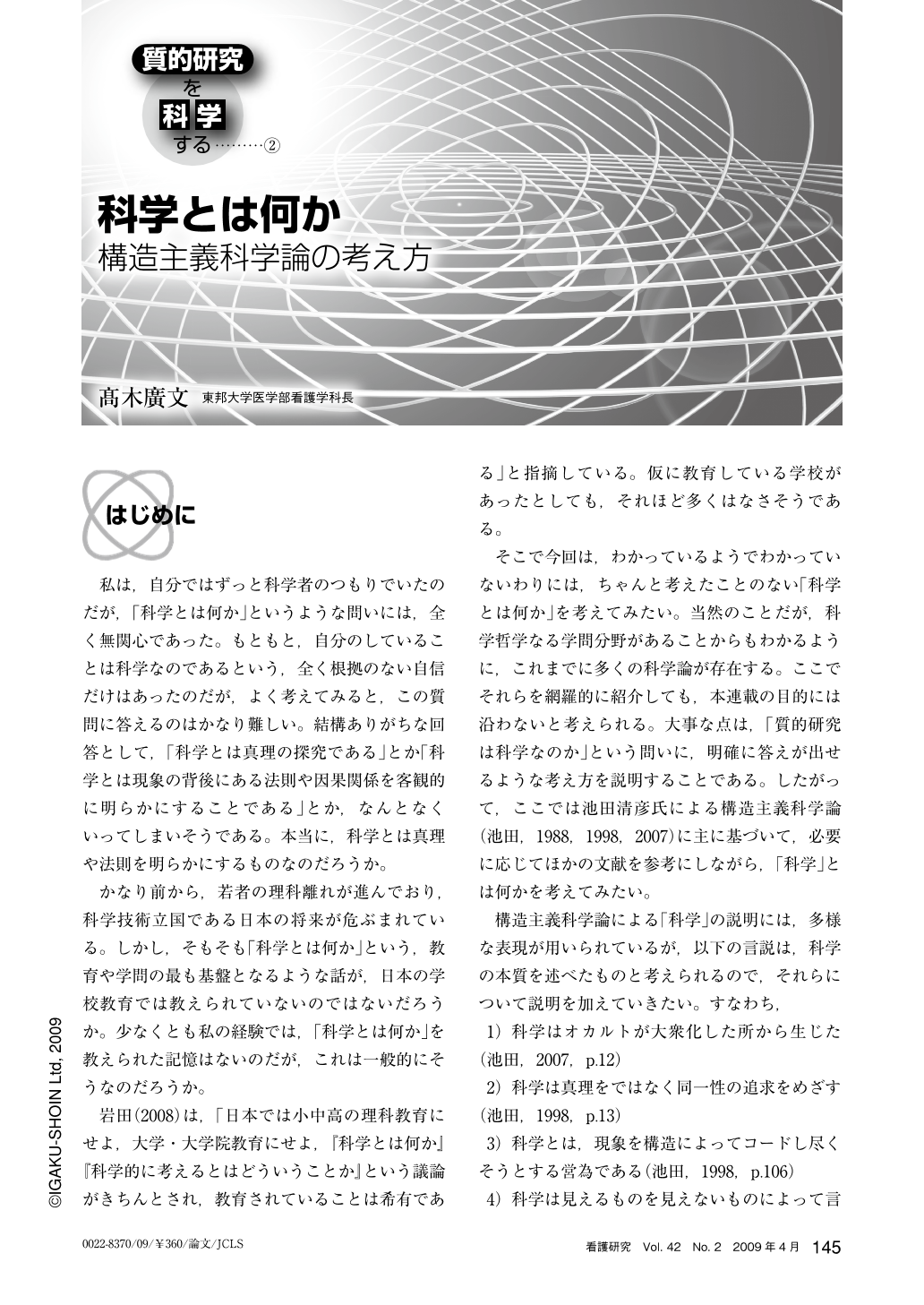
Copyright © 2009, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


