- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
エリザベス・キュブラー・ロスの死の受容過程説について
2004年8月末の朝刊にキュブラー・ロス女史の訃報が小さく掲載された。女史は1926年の生まれなので享年78歳となる。今日のターミナルケア思想の基礎となった『On death and Dying(1969)』(邦訳:川口正吉『死ぬ瞬間』読売新聞社,1972)の他,『続死ぬ瞬間』『死ぬ瞬間の子どもたち』など著書は数多いが,自叙伝的な『Wheel of Life(1997)』を最後に彼女についての大きな報道は途絶え,その功績はすでに過去のものとなりつつあった。『Wheel of Life』の邦訳『人生は廻る輪のように』(角川書店,1998)の訳者上野圭一氏の後書きによれば,彼女は度重なる脳卒中の発作に見舞われ,彼の面会の求めに対してマネージャから「K歟uler-Ross is dying」という返事があったということであるから,彼女をすでに故人と錯覚していた人も多かったのではないか。しかし,ターミナルケアに長く関わる者にとってキュブラー・ロスの名前と業績は今も偉大である。最初の著書『On death and Dying』に接したときの衝撃は今も忘れ難い。
第二次大戦後,先進国の死因として急増し始めた「悪性新生物(癌)」は不気味な病であった。発病機序が不明なこと,初期症状がほとんどないこと,治療があまりにも攻撃的であること,さらに終末期の耐えがたい激痛など,癌は医療者にとって対処不可能な疾患として忌み嫌われた。そして,不幸にもこの業病に罹った患者に対しては,その病名や予後を絶対に告げてはならないというのが当時の医療倫理だった。もし病名を告げると患者は絶望し闘病意欲を失うに違いない,ひょっとしたら自殺するかもしれない,と考えたからである。偽りの病名や一時逃れの励ましに医療者は苦しみ,患者は苛立った。医療者と患者の虚しいせめぎあいの中で,癌医療は負のスパイラルに巻き込まれていた。
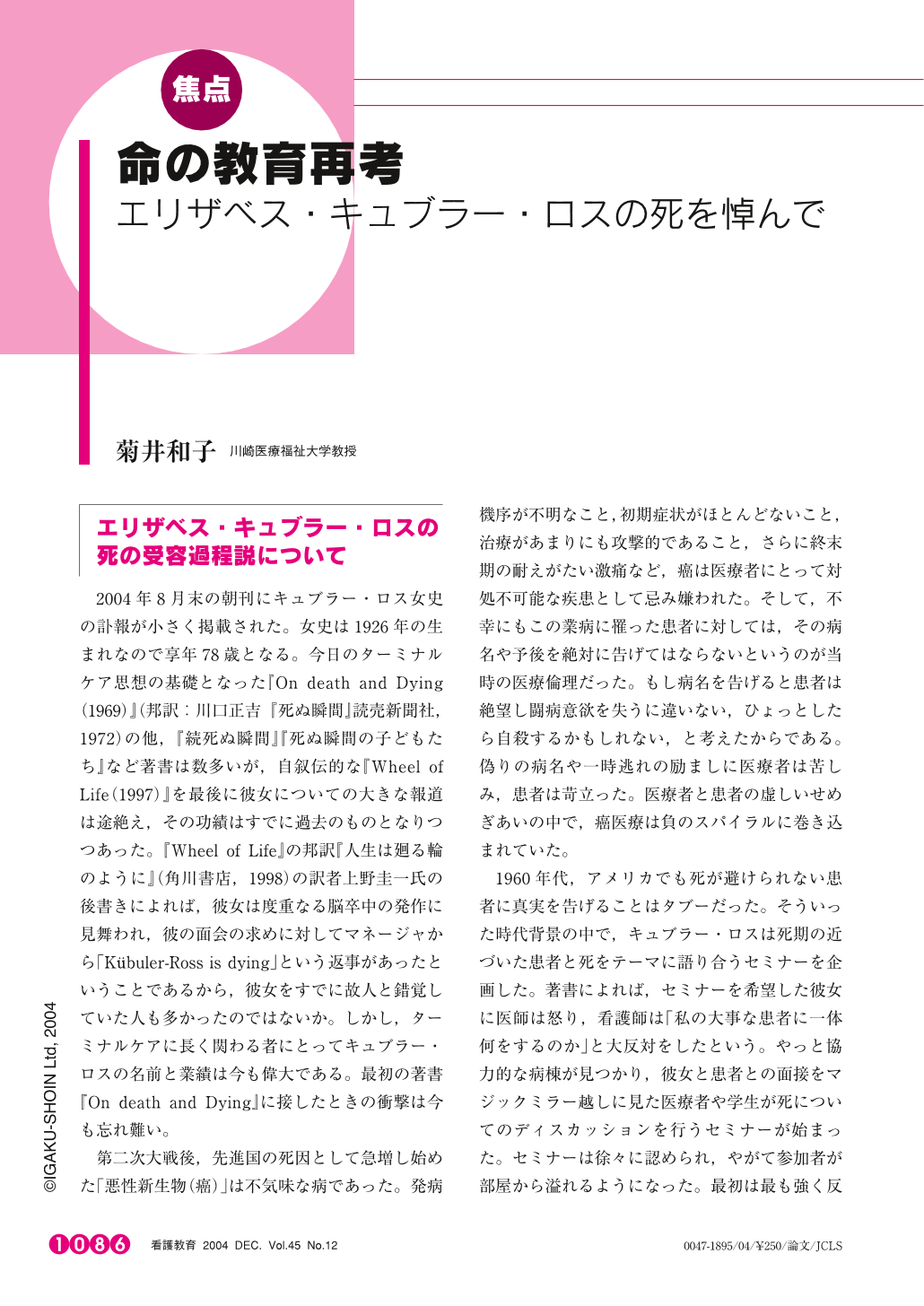
Copyright © 2004, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


