- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
I.はじめに
生化学的手法を用いて癌の診断をしようという試みは古くからなされている。癌細胞は正常細胞の突然変異によつて悪性を獲得したものであり,したがつて質的に異なつた物質が存在し,それを発見,同定することによつて癌の特異的な診断法が確立できるという信念のもとに,ぼう大な実験がなされたが,現在までのところすべて徒労に終わつている。しかしよく考えてみると,悪性とは生物学的な現象であり,それをすぐ質的に異なつた物質に結びつけることは余りにも性急な短絡ではなかろうか。生命現象には閾値が存在する。閾値の範囲内での物質の変動は,生物学的には何らの変化も伴わない。閾値を越えて物質が変動したときに生物学的現象が発現するのである。すなわち物質の量的変化によつて,生物学的には異質な現象が引ぎ起こされるのである。端的な例がトキソホルモンである。この物質は癌細胞に含まれ,宿主に対して,肝カタラーゼの低下,血清鉄の低下などいわゆる悪液質と総称される病態を引き起こす癌毒素といわれている。しかしトキソホルモンは量的には少ないが正常組織にも含まれる。正常動物ではこの物質が量的に少ないため,あるいは細胞内に存在していても細胞の外に出さないような機序があるため悪液質という病態が引ぎ起こされない。ところが担癌生体になるとトキソホルモンの量が閾値を越えるので悪液質が発現すると考えられるのである。そこで癌の診断を生化学的手法を用いて行なうためには,物質の量的な変化―いい換えると正常からの"ゆがみ"―をとらえる必要がある。物質を定量する場合感度のよい方法を用いた方が望ましいことは当然である。酵素反応や免疫反応が物質定量のめやすとして用いられるゆえんである。
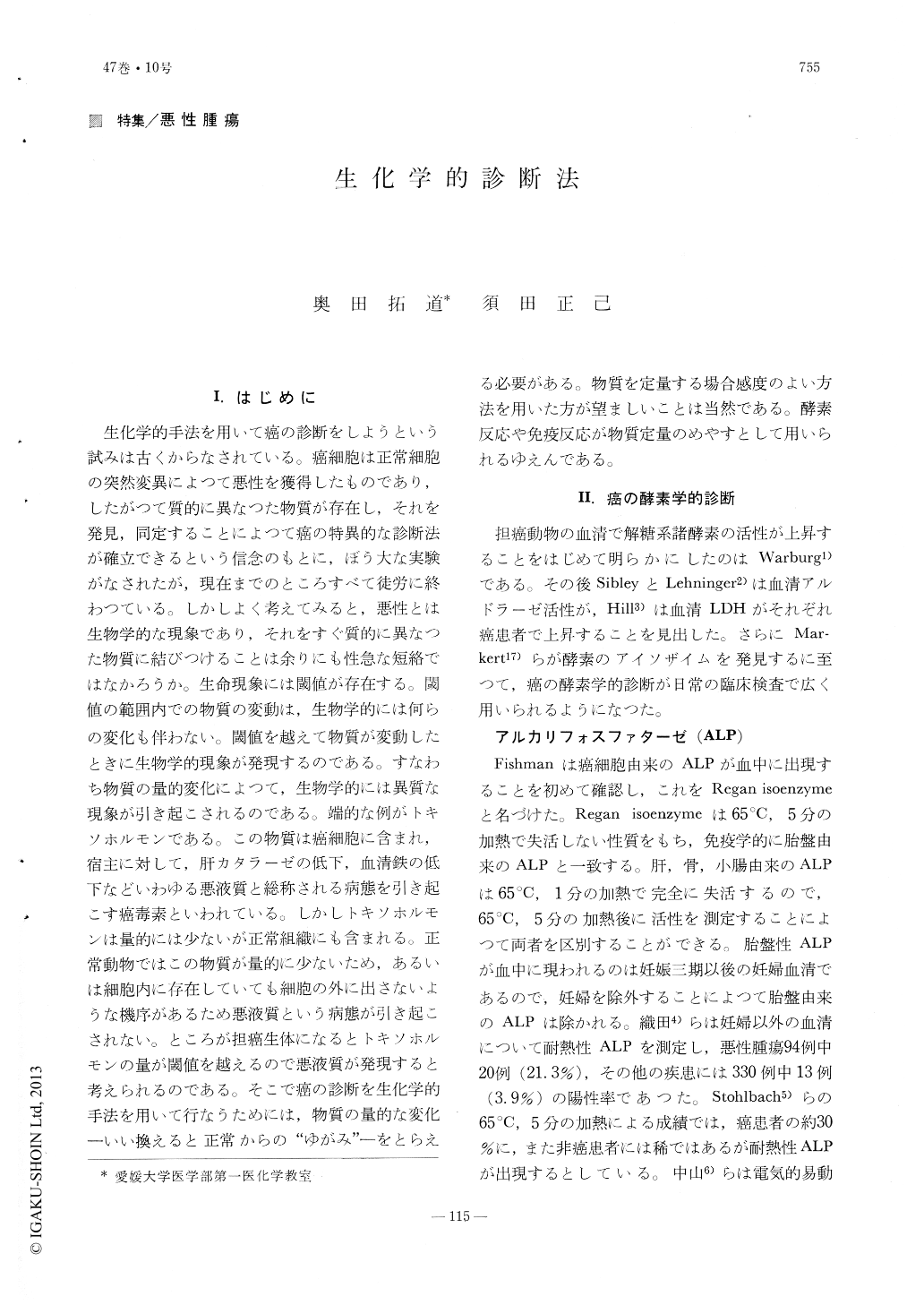
Copyright © 1975, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


