Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
I.序論
大脳の諸構造のうちで,脳梁ほど謎と誤解につつまれてきたものも少い。19世紀末から20世紀初頭にかけ,Dejerine1)〜3)やLiepmannら4)により半球間の連合機能における脳梁の意義はすでに明快に証明されていたにもかかわらず,その後の臨床的観察においては,脳梁自体の症候と,その隣接域の症候とが混同されることが多く,しかも,Dandy5), Van Wagenen and Herren6),次いでAkelaitisら7)〜17)の一連の発表は,古典的脳梁症候群をまったく否定することとなってしまった。このため,1940年代においては,脳梁の役割はほとんど無視されることが多くなり,半ば冗談にせよMcCulloch18)をして,"脳梁は単にてんかんの発射が対側半球にまで波及するのに役立つているにすぎない"とまで慨歎させた。
しかし1953年以後のMyersおよびSperry19)〜23)の脳梁切断動物における巧みな神経心理学的研究によつて,脳梁の意義は再び大きな脚光を浴びることとなつた。彼らの実験に刺激されたGesch—windは,1962年Kaplanとともに24),一例の脳梁損傷例において大脳半球聞の連合機能障害を詳細に検討し,Liepmannら4)の主張した,半球間連合障害における脳梁損傷の意義を再認識した。ついでGeschwind25)は,1965年の論文で連合野皮質の病変,または大脳白質病変によつて生じる大脳皮質問の連合機能障害を,disconnexion synd—rome (註)と名づけ,脳梁損傷にもとつく片側性の諸高等機能障害を,半球問(interhemispheric) dis—connexion syndromeとして理解すべきことを述べた,彼は,翌年Fusilloとともに26),かつてDejerine1)〜3)が報告したのとまつたく同様な"純粋失読"の症例を報告し,脳梁の意義に関するDejerine1)〜3)やLiepmannら4)の考えが全面的に正しいものであることを明らかにした。
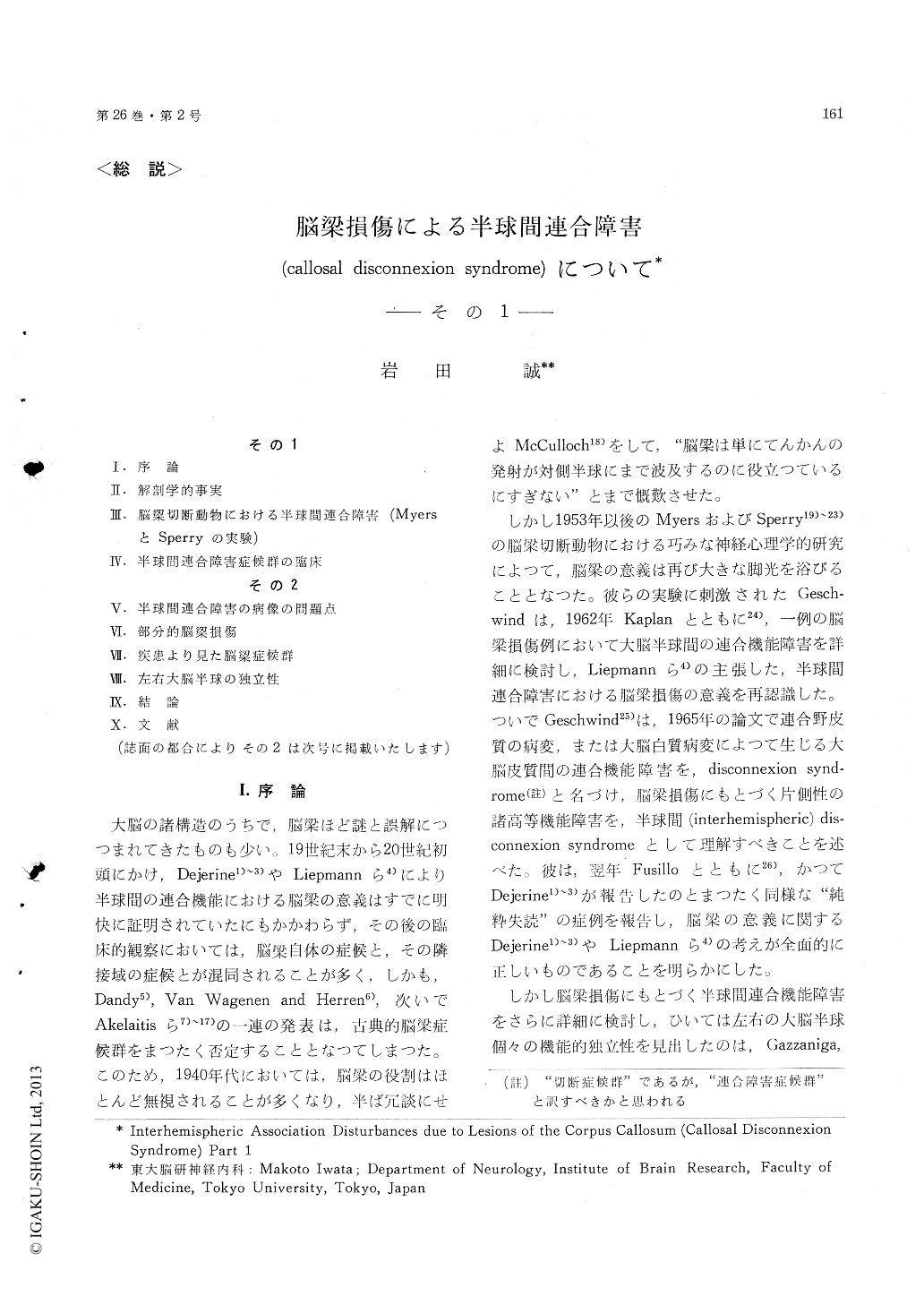
Copyright © 1974, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


