連載 ネガティブ・ケイパビリティを学ぼう! 不確かで曖昧な保健活動を支える力・2
問いにとどまり続ける勇気—実践から考えるネガティブ・ケイパビリティ
氏原 将奈
1
1淑徳大学看護栄養学部看護学科
pp.416-419
発行日 2025年10月10日
Published Date 2025/10/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.134883330810050416
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
日々の保健活動にどう生かす?ネガティブ・ケイパビリティ
前回は、保健師の活動がいかに正解のないものであるかについて述べ、そしてそのような状況で求められる力として「ネガティブ・ケイパビリティ(Negative Capability)」という概念を紹介しました。すぐに結論を出さず、不確かさや曖昧さの中にとどまりながら、相手や状況と丁寧に向き合い続ける力。それは、支援の質を高める土台であり、保健師にとって重要な能力の一つであるということを確認しました。
では実際に、ネガティブ・ケイパビリティはどのような場面で発揮すべきものでしょうか? 保健師の日々の実践には、面接や家庭訪問、健康教育など、さまざまな手法があります。また、児童虐待や精神保健などの領域では、複雑でハイリスクな状況に向き合うことも少なくありません。こうした一つ一つの活動の中で、私たちはどのようにネガティブ・ケイパビリティを生かしていけるのか—今回は、その実践への応用を具体的に考えていきます。
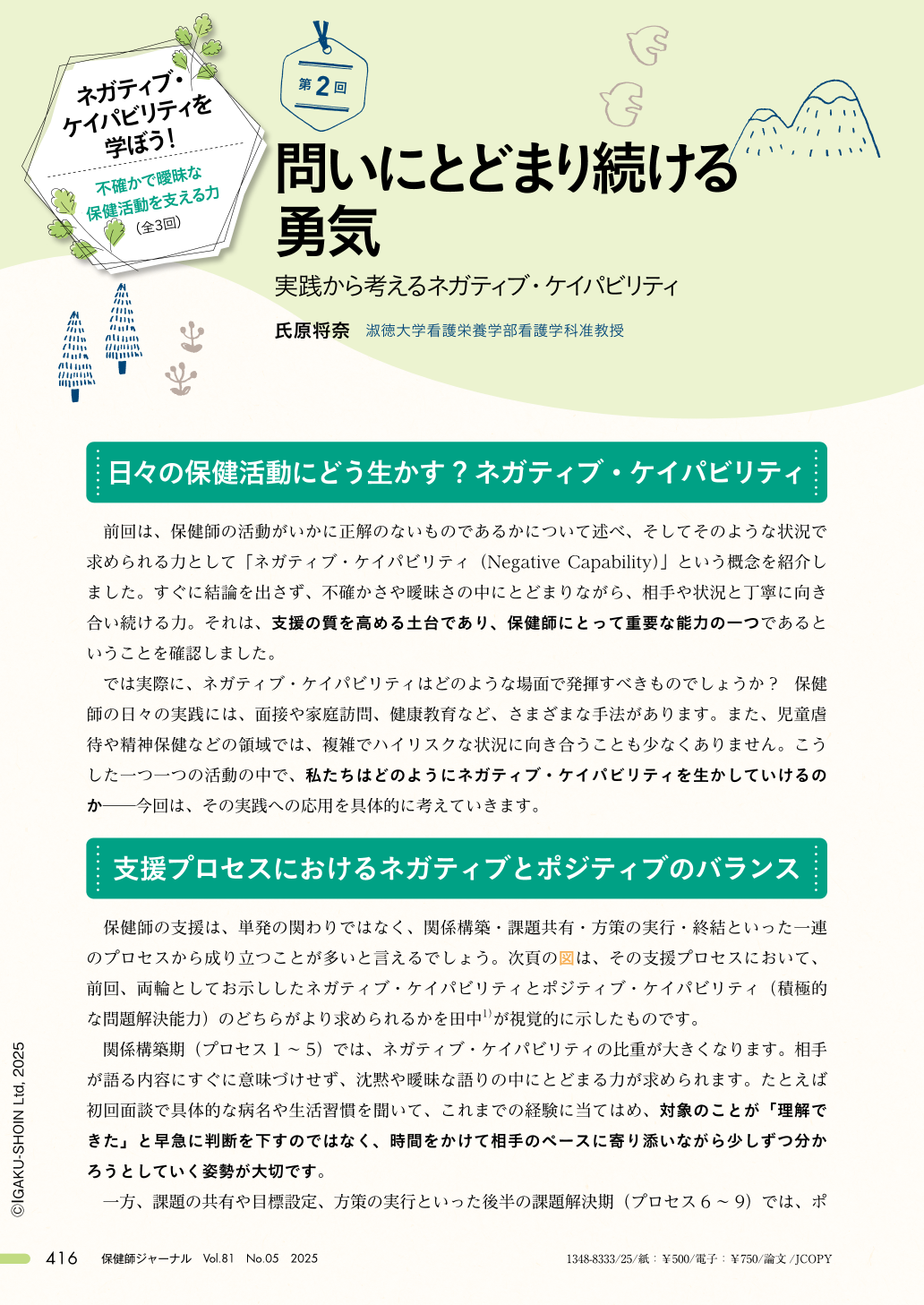
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


