- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
看護基礎教育の大きな課題の1つは、「実践力」をいかに育成し、適切に評価するかにあります。知識や技術は客観的・定量的に評価できる一方、実践力の評価については、客観的な評価を行うことは困難であり、課題の多い状況だといえます。このような中、第5次指定規則改正における別表3「教育の基本的考え方」において、「科学的根拠に基づいた看護実践に必要な、臨床判断を行うための基礎的能力を養う」という文言が付け加えられました。背景には、新人看護師の実践力低下が課題として取り上げられた結果ですが、臨床現場の医療の高度化とそれに伴う入院期間の短縮といった、社会の変化に看護基礎教育が適応できていないことが要因として挙げられます。
この問題に対して、イムス横浜国際看護専門学校(以下、本校)では「ディファレンシャル・ラーニング」注1という演習を行い、臨床知を積み上げ、臨床判断能力の土台を育成する試みを行っています。1つの事例・場面に対して、患者の身体的変化や訴え、家族の要望などの変化を設け、学生が即興でチームで対応し、その様子をスタッツ表(p.583)に記録。さらに、動画を見返しながら、他のチームの演習動画も含め、Good/Bad/Next(p.583)で省察を繰り返す。これによって、さまざまな状況での経験(もしくは擬似的に経験)を臨床知として積み上げ、速い思考である直感的解釈の糧となる臨床知を蓄積させていきます。また、ディファレンシャル・ラーニングは省察にも力を入れているので、同時に分析的解釈や説話的解釈の育成を促すことができます。しかし、効果的な学びには、それを促す評価方法も同時に検討する必要がありました。
本校では領域横断科目として「エンド・オブ・ステージ援助論」(3年次4〜6月)という、緩和ケアを必要とする終末期にある対象への援助方法を学ぶ科目を設けています。ここでは発達段階・疾患の異なる患者の事例を用いて、5回の演習を行います。そこで、授業設計をするにあたって検討したのが、「学生にどのような実践力を身につけてほしいのか、そのためには何を評価すべきなのか」でした。そしてその時、最初に思いついたのが、患者・家族に「共感」できることでした。しかしそれは可視化が難しく、「共感」を表現する方法は多様な解法が考えられました。
本稿では、非認知能力を評価対象に含める意義と、その具体的手法として「スタッツ」による定量的評価、および「Good/Bad/Next」による省察を組み合わせた評価方法を提示し、学生の「共感力」を表面化させる取り組みを紹介しています。この取り組みで、多くの学生が「共感」する力を持っていることを示し、これら非認知能力を教育方法と評価の工夫によって表面化させることで、学生は驚くほどの変化を見せることが理解できました。
その取り組みの一部と、なぜそのような取り組みを行ったのかについてお伝えします。
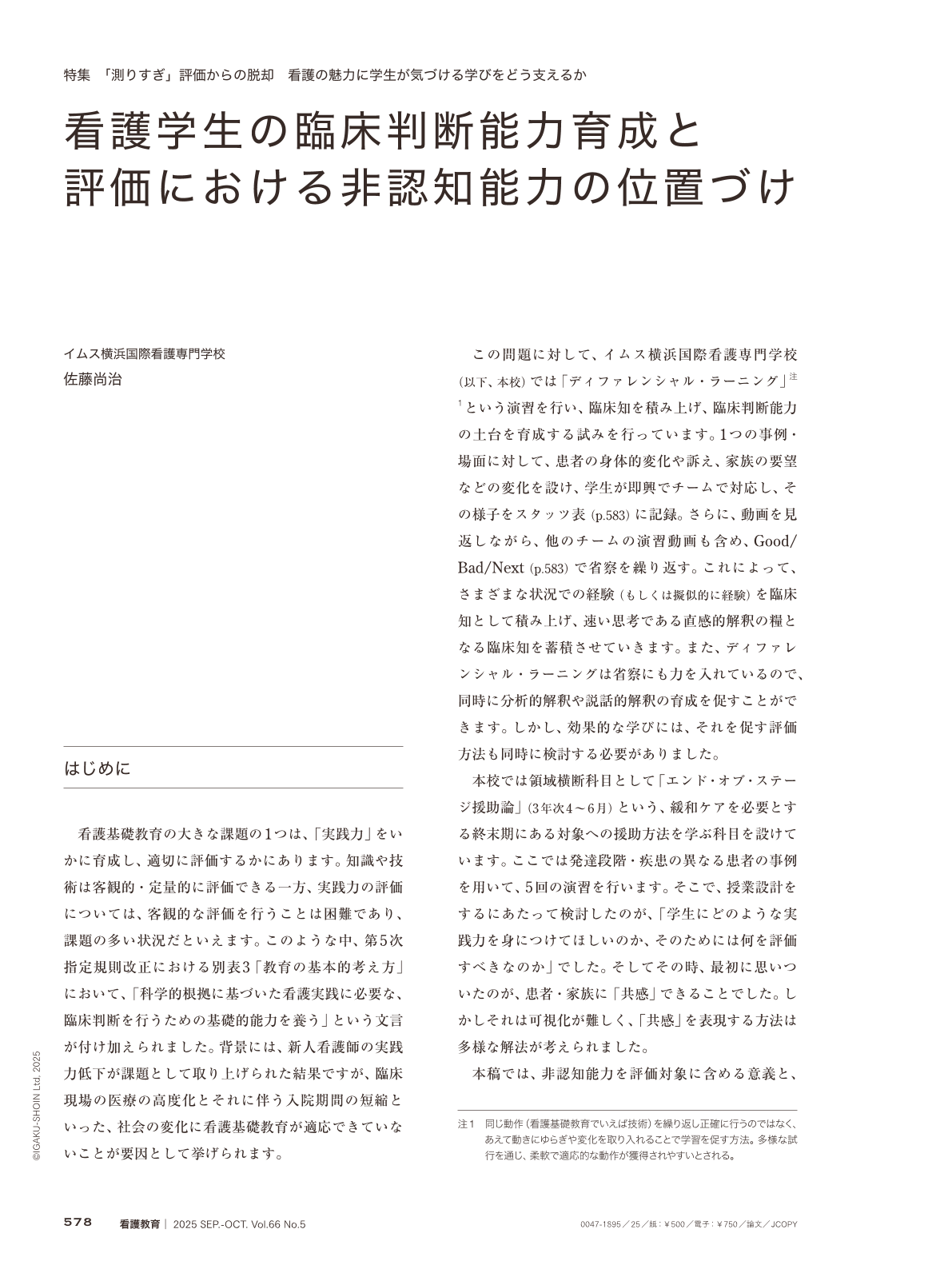
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


