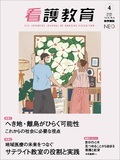- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
多様化する保健医療ニーズに対応するため、科学的根拠に基づいた論理的思考や、複合的な思考が看護基礎教育で重要視されている1)。看護過程は、看護やケアを科学的論理的に思考するための1つの教育方法であり、問題解決技法の技術である2)。一方で、問題解決技法として習得できればよいのではなく、複雑な現象を理解して看護援助を創造するために、複合的な要素を考慮し、直感的な思考や文脈的な思考などを組み合わせて判断する力を育成する必要があるといわれている2)。
横浜創英大学(以下、本学)では、1〜2年次期に看護過程の基礎を学んだ後、3年次前期に各領域の看護過程科目が同時並行で開講される。看護学生にとって看護過程は理解することが難しい科目の1つといわれており3)、特に、看護過程におけるアセスメントは、看護学生にとって困難さを伴うとされている4)。そのため、具体例を示すことや繰り返し練習する機会をつくること、グループワークを活用することなどの重要性が示唆されている4)。また、看護過程を学ぶ初期の1年次では基本的な事項のみ理解し認識は高まるが、その後、認識や自己評価は下がるという結果も報告されている3)。
そこで本学では、領域を横断したワーキンググループを立ち上げて共通理解を深め、学生の看護過程の理解を促進する教授法について検討してきた。萩原らが述べているように、この取り組みは単に領域間を「つなぐこと」のみならず、取り組みを通じて各領域の工夫や相互の関係性を知り、また、それぞれの領域の底流にある共通基盤を見いだすことを意識した5,6)。以下、本学におけるワーキンググループによる学びと、異なる領域間をつなぐ取り組みについて紹介する。
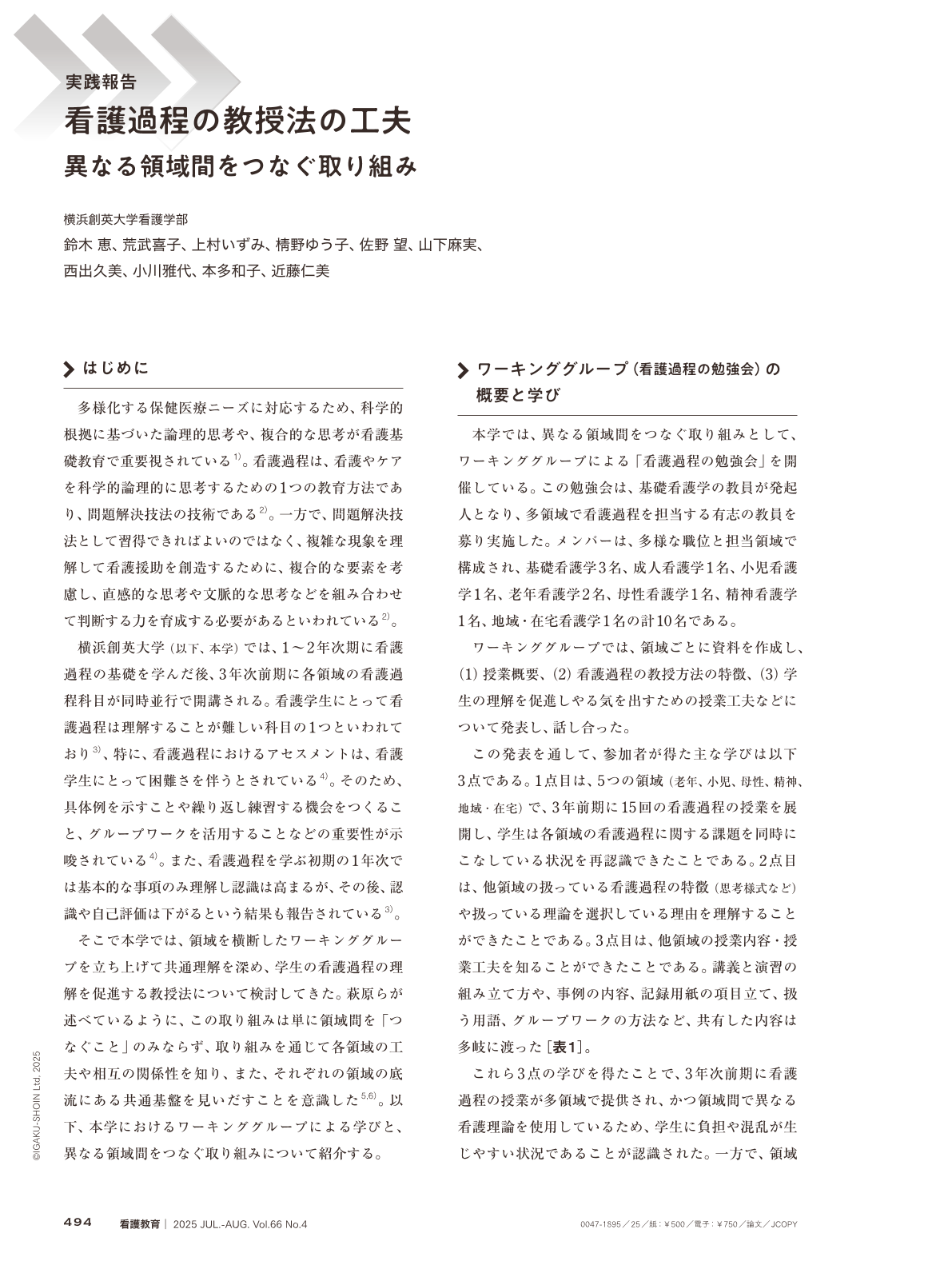
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.