- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
日本社会は1997年にいわゆる山一ショックと呼ばれる甚大な経済危機に見舞われ,翌1998年に年間自殺者が対前年比で35%も増加し,一気に3万人の大台を突破した。年間自殺者3万人は本邦の統計史上始まって以来のことであり,その後,14年間もその状態が続いたのである。当時の自殺率は人口10万対25前後で,世界の中で最高位国に位置するという憂慮すべき状況であった。
厚生労働省が2000年以降,自殺予防対策に乗り出したが,残念ながら短期で結果を出すことはできなかった。それが批判され,もっと広がりを持った自殺予防対策を実現させるために,2006年に自殺対策基本法が施行されるに至った。同法成立の背景には,自殺を社会的な問題としてとらえるNPO法人ライフリンクによる,署名活動を始めとする政治家への働きかけが大きく寄与した。そのためか,この法律で謳われる基本理念では,まず第一に,自殺を「その背景にはさまざまな社会的な要因がある」ととらえ,自殺対策は「社会的な取り組みとして実施されなければならない」とされている。そして,精神医学的問題については,「単に精神保健的観点からのみならず」という表現にとどまり,中心的な課題とはされていない。果たして,「自殺は社会的に追い詰められた末の死だから防がないといけない」という考えだけで自殺予防の論拠足り得るだろうか?
もう10年以上前になるが,筆者は一般の人向けの自殺予防に関する講演を行った。その際,聴衆の一人から「追い詰められた末の死で可哀そうだとは思うが,最後はその人が決めたことだから,仕方ないのではないか」と投げかけられた。これは自殺の自己責任論である。その人の発言に,少なからぬ人たちが頷いているのが見て取れた。自己責任論―自殺予防活動のために乗り越えねばならない壁である。もう一つ,そもそも自殺容認論という大きな壁がある。これらの壁を乗り越えるための自殺予防の論拠について考えたい。
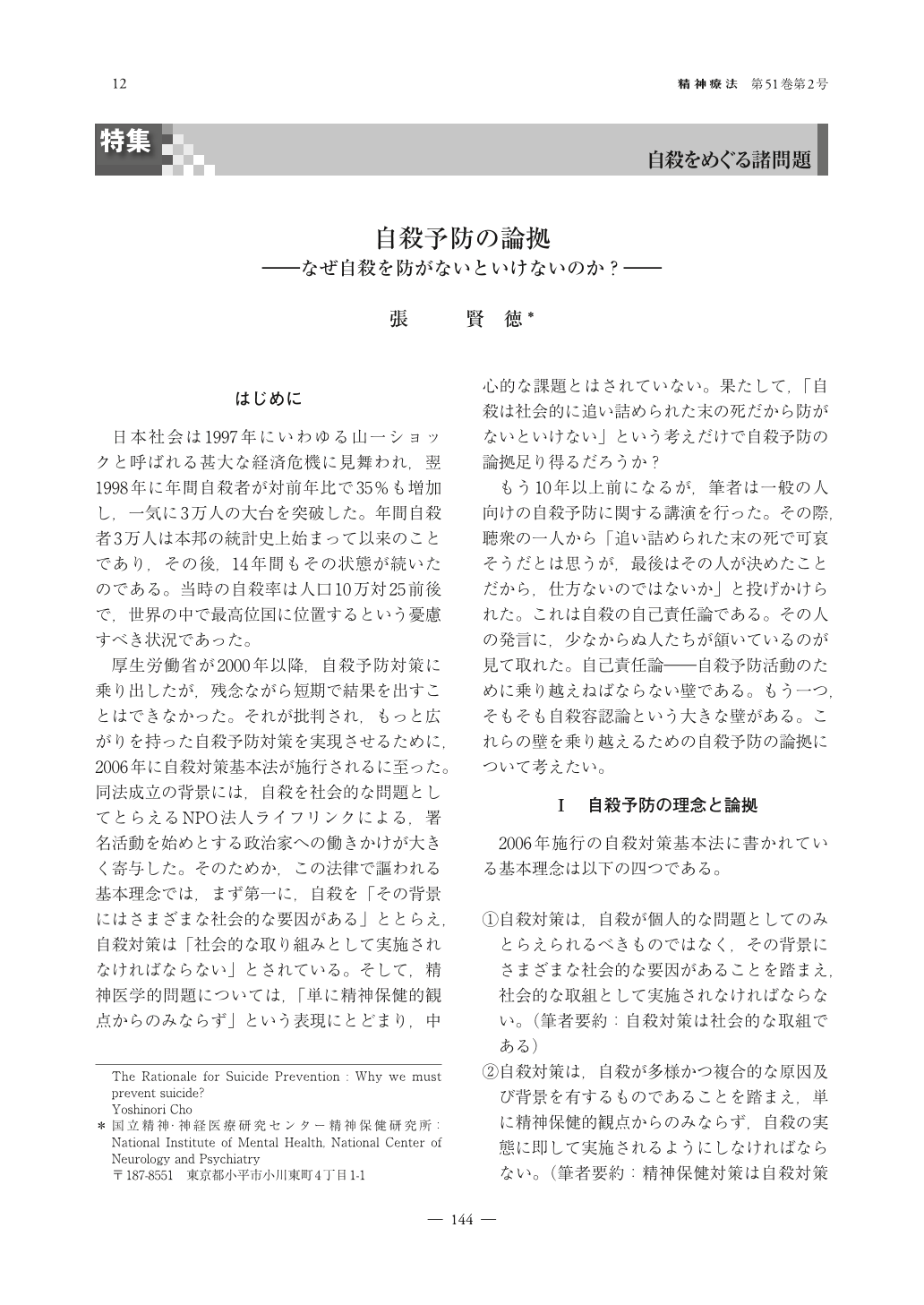
Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.


