- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
森田療法というと,権威的で,厳しい修行的精神療法として長い間認識されてきたようである。入院森田療法の創始が,1919年であるから,当然その時代の心性を反映していた。この治療システムは,症状を個別に取り上げないこと(症状不問)と治療の場の行動的体験の重視(作業の重視)と森田の講話などからなっていた。そして見逃してはならないのは,当時は,自宅を使って,家庭的な雰囲気のなかで,家族と一緒に治療に当たったことである。
そして大正から昭和にかけて,このような治療システムは極めて有効で,多くの当時の青年たち(多くは男性)が回復し,社会で活躍していった。
その時代は,大正デモクラシーの時代から,次第に軍国主義へと日本の政治的な進路が大きく変化しつつある時代である。そこでは,それが当時の社会的なシステムに支えられていたにせよ,権威を持つ「先生」がさまざまな領域で存在した。
それは1945年の日本の無条件降伏と翌年の日本国憲法公布によって終わりを告げると共に,「民主主義」,あるいは「民主教育」が強調されるようになる。森田療法に対する批判も,戦後の時代精神を反映しているように思われた。
この入院森田療法のシステムは,森田の直弟子たち,さらにはその後継者によって継承された。一部の森田療法施設では,禅的森田療法と呼ばれ,不問の徹底と行動的体験の促しが組み合わされていた。そこでは,森田の時代もそうであったが,患者は修養生と呼ばれた。そこでの治療者は,まさに先生であり,師であった。
この当時の森田療法への批判は,(1)権威的で,説得的である,(2)そこには技法論もなく,ただ「あるがまま」と治療者は唱えているだけ(理論的不整備),(3)戦前から引きずっている(?)日本人の権威に対して従順であることを利用した精神療法である(当時は,日本人論が大流行であった),(4)個の確立,あるいは自立ということに対して明確な指針を持っていない(あるいは逆の方向に向かっている),(5)そこでは患者は,権威に従順になることで,とりあえずの症状治癒をもたらしている,(6)治療的関係,あるいは治療者の機能,役割が明確にされていない,などであった。
それらの批判を念頭に,本論では,森田のなかでの「先生」,あるいは治療的権威性ということについて,述べてみる。
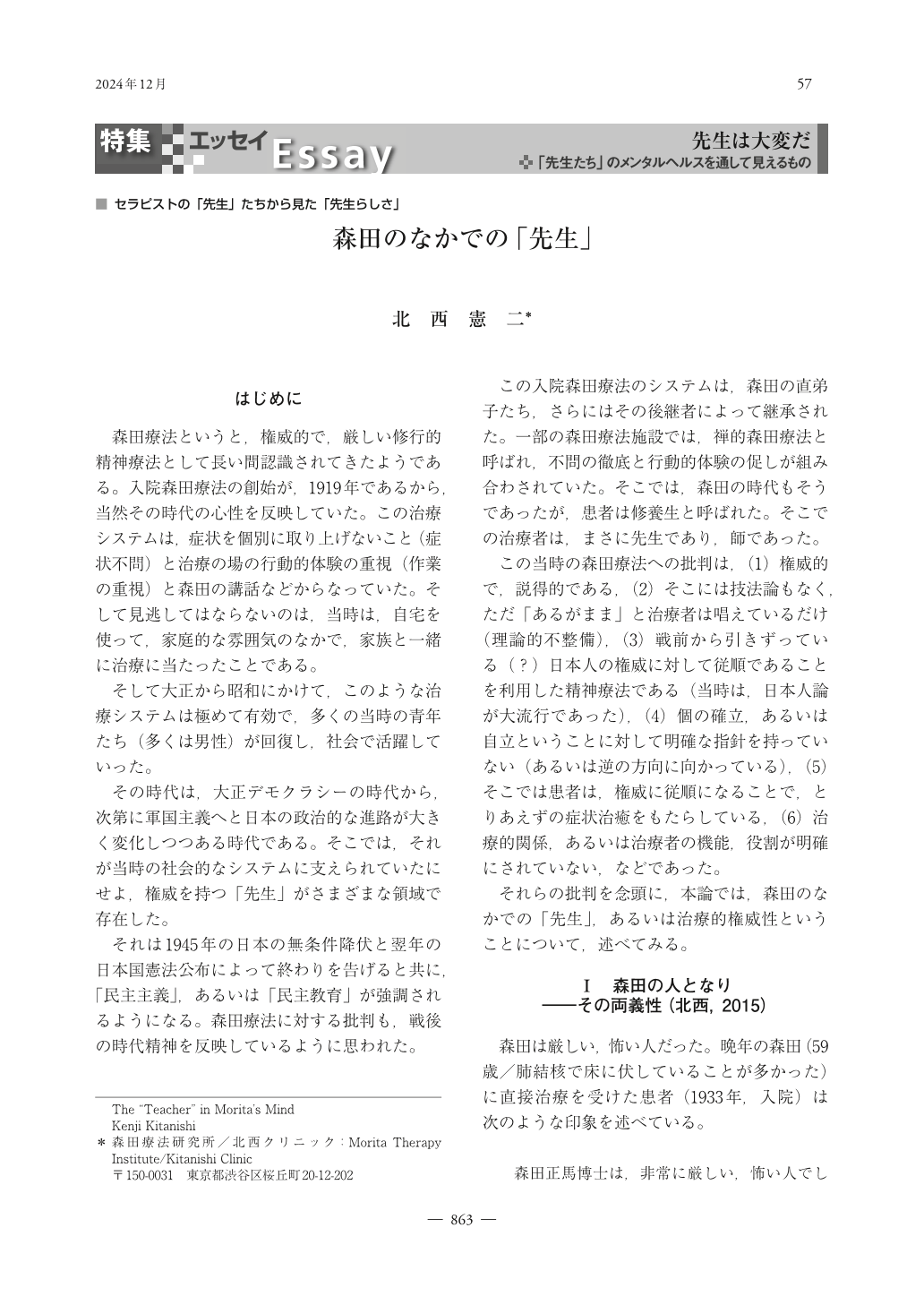
Copyright© 2024 Kongo Shuppan All rights reserved.


