特集 精神療法における治癒とは
森田療法の立場から
北西 憲二
1
1森田療法研究所
pp.646-651
発行日 2024年10月5日
Published Date 2024/10/5
DOI https://doi.org/10.69291/pt50050646
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
病状(主訴)とは,悪循環に入り込んでしまい,そこに止まり,抜けられない状態と理解する。そして精神療法における治癒とは,この悪循環を抜けて,その人としての人生を歩み出せた状態とする。ここではある思春期事例Aさんを素材に(プライバシーに配慮して,大幅に改変している),前思春期から青年期にかけての治癒に至る道のりを述べてみる。そこにはある一貫した治療的介入とそれに対応した変化のプロセスがあった。 まず悪循環について述べる。
そこには「適応不安」(高良,1976)が見いだせる。
適応不安とは,「自己の心身の状態が自己の生存をまっとうするうえに,不利の状態にあると思う不安気分」である。
これは二律背反,自己撞着に陥りやすい不安のあり方であり,綱引き状態,悪循環を引き起こす。
(1)自己の状態は何ともならないのではないか,という不安気分があり,
(2)一方ではそれを何とかしなくてはならない,という健康な力(生の力/生存をまっとうしたい)が働いている。
(3)さらに「こうあってはならない」「こうあるべきだ」と不安気分(とそれを感じている自己自身)を受け入れられずに葛藤する思考のありかた(自己撞着的で,「べき」思考と呼ぶ)が関与している(森田,1926/1995)。
(1),(2),(3)が連鎖し,悪循環を作る(北西,2021)。それは単に内的な動きだけでなく,対人関係においても見いだせる。児童,思春期の多くの事例では,家族を巻き込んだ悪循環が存在し,それが問題を拡大する(玉井・他,1991;北西,2012)。親子の相互作用による悪循環で,その把握なしに,児童,思春期の回復の援助は難しいと考えている。
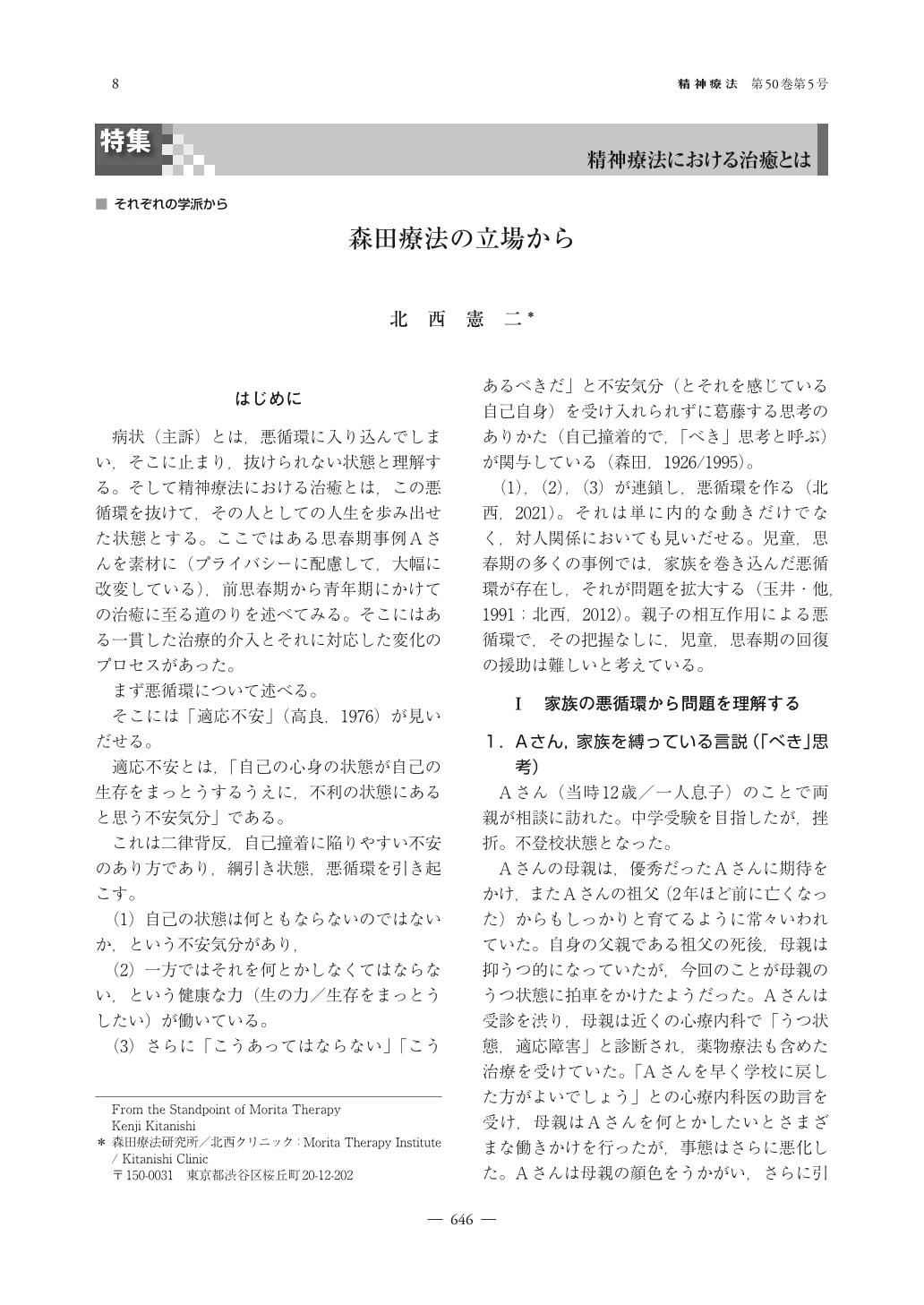
Copyright© 2024 Kongo Shuppan All rights reserved.


