- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
I はじめに
2000年前後から,主にビジネスシーンで「個の時代」という言葉が盛んに使われ始めている(太田,2003)。伝統的な序列主義であっても能力重視の選別主義であっても,お金や物をたくさん所有すること,組織での業績や豊かな生活を手に入れることなどに価値があるとされていた時代から,情報や体験の共有,フリーランス,仲間とのつながりや助け合いなど,自由で柔軟なものの価値が大切にされる時代になったというのである。それは,画一的・効率的で「個」を後回しにして組織の成果を向上させるスタイルから,「個」が活躍する創造的で革新的な時代への転換であり,上意下達の社会からフラットな関係性を重視する社会への移行であるともいえる。このような変化のなかで,以前ならば,強固な組織内で黙殺されてきた個人の痛みや苦悩が顕在化しやすくなり,これまでよりも,少しは関心を持たれ,丁寧に扱われるようになってきたのかもしれない。
トラウマインフォームドケア(Trauma-Informed Care : TIC)も,権力勾配をフラットにしようとする試みから始まった。1990年代の米国では,レイプ被害やDV被害など,さまざまな暴力に曝され深いトラウマを負った女性たちの声を聴く会議が複数回開催された。なぜなら,薬物依存に陥り司法の場に登場する女性のほとんどがトラウマ的出来事を体験しており,トラウマの影響を無視した薬物依存の支援は効果がない,という気づきがあったからだ。ところが会議で彼女らは,医療・保健・福祉・司法などのサービスを受ける時に,再び傷つけられている(再トラウマ化)と訴えている(Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2014a)。たとえば,精神科医療の非自発的入院時の強制力によって,あるいは,心身の健康不全が怠けや甘えに起因するという自己責任論によって,さらには,司法の場における命令や個人を無視した扱いによって。一方,過酷な貧困のなかで力を奪われホームレスになった人たちの多くも,さまざまなトラウマ的出来事を体験していることが明らかになった(Hopper et al., 2009)。
このようにTICは,それまで社会のなかで弱者として半ば無視されてきた人たちが,実は,過去のトラウマ的出来事に起因する心身の健康不全や機能障害に苦しんでいると認識されるところから始まった。そして,過酷な状況で孤軍奮闘しながら生き延びてきた人たちに敬意を払い,目には見えないトラウマの痛みを少しでも理解しようとし,彼らに再びトラウマを負わせることがないように配慮しようとすることこそがTICの本質なのだ。
国民の半数以上が最低一つのトラウマ的出来事を体験している現代(Kawakami et al., 2014),そして,一人ひとりの「個」を尊重することを目指す現代は,まさに,TICが求められる時代であるといえる。2010年頃に初めて日本に紹介されたTICの概念は,ここ10年あまりのうちに,医療・保健・福祉・教育・司法など,さまざまな領域で,着実に普及し始めている(亀岡,2024:亀岡ほか,2018)。最初にTICの概念を学んだ各領域のパイオニアたちは,TICの重要性と有用性を確信し,熱意をもって普及啓発に尽力してきた。しかし,当初は,他の新しい概念の導入時と同様に,TICへの抵抗があったことも事実である。
そして今,「こころのケガ」という用語の広がりとともに,TICの概念が多くの人たちに知られるようになり,TICをテーマとした研修会も盛んに開催されるようになった。日本全体でみると,組織的にTICに取り組むべく地道に活動を続けている先進的な機関が注目される一方で,これからTICを学ぼうとしている臨床家や組織もまだまだ多く,取り組みの格差が広がっている段階かもしれない。
そこで本特集では,各領域の第一線でTICに取り組まれている臨床家や研究者にご執筆いただき,改めてTICについて再考する機会を提供したい。それに先立ち,ここでは,TIC実践に伴う障壁や課題についてまとめておく。
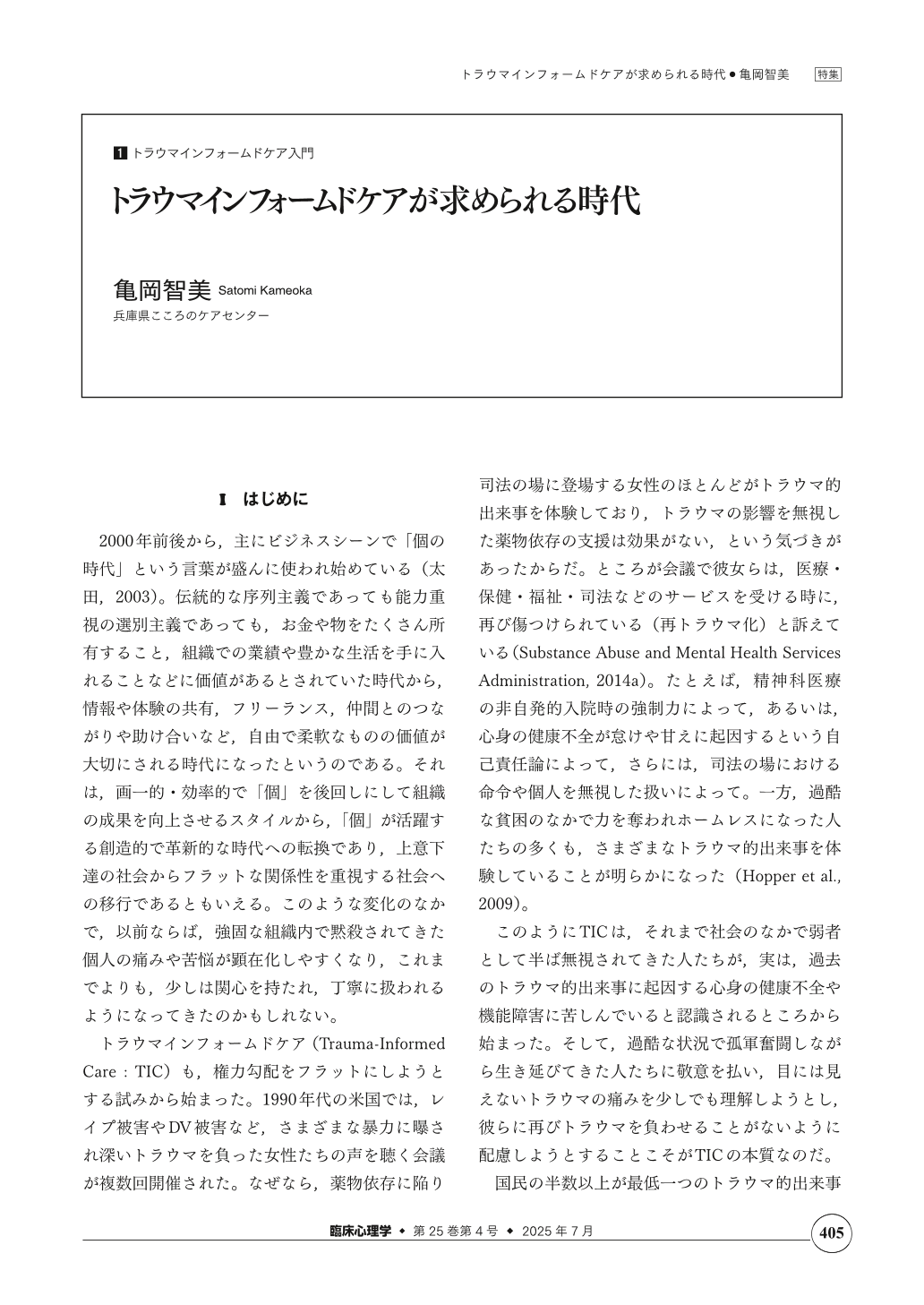
Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.


