Japanese
English
特集 小児リハビリテーションの5W1H─超少子時代を迎えて
第3章 小児リハビリテーションの実践
脳原性障害による肢体不自由児への対応
Management of Children with Motor Disabilities of Cerebral Origin
藪中 良彦
1
Yoshihiko Yabunaka
1
1大阪保健医療大学保健医療学部
キーワード:
脳原性障害
,
肢体不自由
,
小児リハビリテーション
,
目標設定
,
多職種連携
Keyword:
脳原性障害
,
肢体不自由
,
小児リハビリテーション
,
目標設定
,
多職種連携
pp.1348-1354
発行日 2025年11月25日
Published Date 2025/11/25
DOI https://doi.org/10.32118/cr034131348
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
- 参考文献 Reference
内容のポイント Q&A
Q1 What? 脳原性障害による肢体不自由とは?
「脳原性障害」とは,脳の先天的・後天的な損傷,形成異常,代謝異常等に起因して,運動機能や姿勢制御に持続的な障害を生じる状態を指す.
Q2 Who? リハビリテーション診療を要する子どもにはどのような特徴があるのか?
脳原性障害による肢体不自由を有する子どもは,障害の原因や時期,障害部位の広がりにより多様な特徴を示すが,発達の遅れを共通の特徴として示し,随意運動障害,筋緊張異常,不随意運動,協調運動障害等の運動障害とてんかん,知的障害,感覚障害,摂食障害やコミュニケーション障害等の合併症を呈する.
Q3 When? Where? いつから,いつまで実施するのが適切か(時間と場所)?
介入は,新生児期から老年期まで続き,各年齢帯における主要な特徴と課題,介入目的,主要な実施機関,連携のポイントがある.
Q4 How? どのように評価し,リハビリテーション診療を行うべきなのか?
子ども主体で子どもと家族を含む協働目標設定が有効である.介入は,子どもの能力だけでなく,課題や環境に対する介入が必要である.効果的な介入のためには,運動学習の段階を把握しコーチング手法を使い,多職種との連携が重要である.また,ICT(情報通信技術)機器やAAC(補助代替コミュニケーション)機器の活用支援も行っていく.
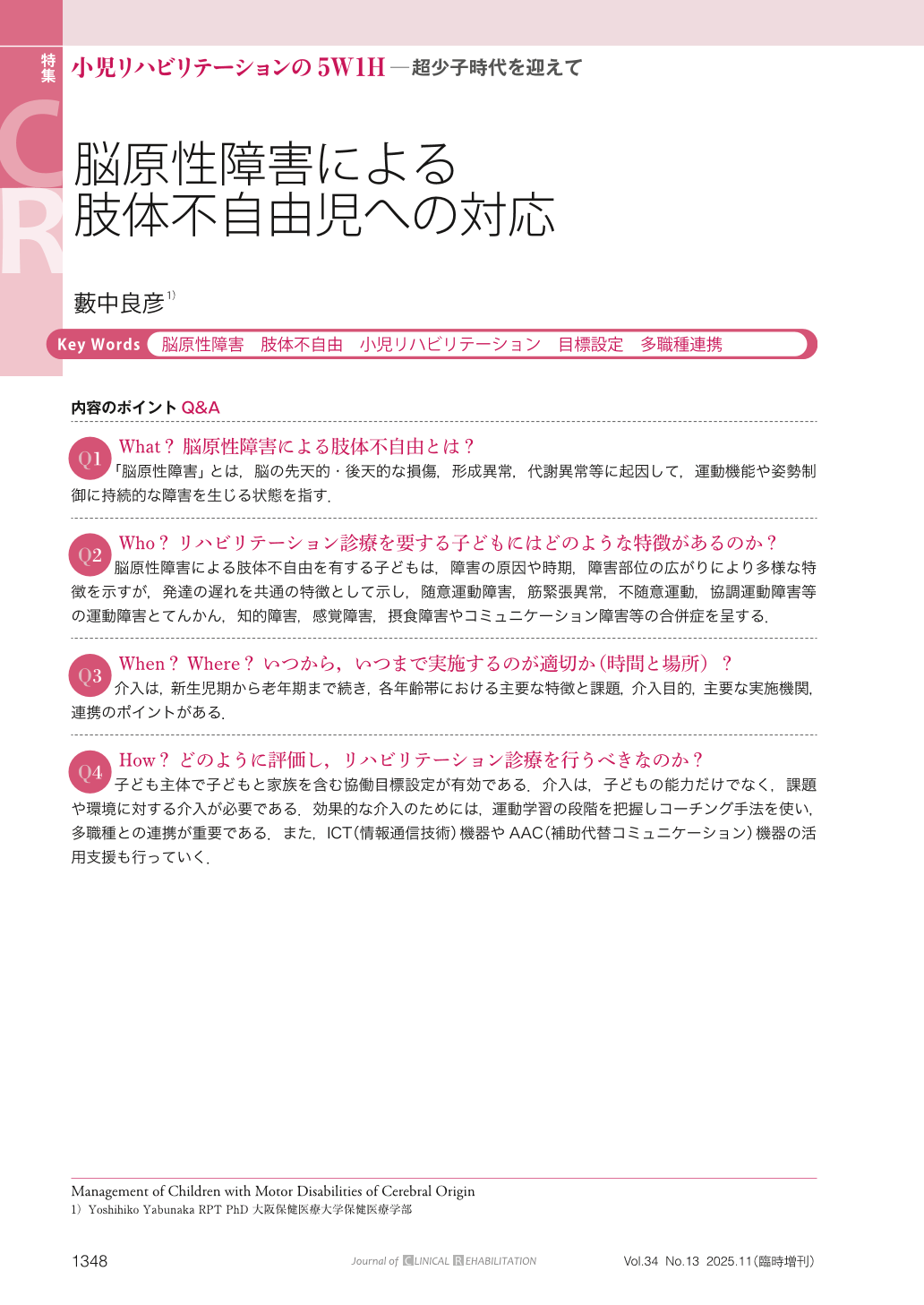
Copyright© 2025 Ishiyaku Pub,Inc. All rights reserved.


