Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
- 参考文献 Reference
内容のポイント Q&A
Q1 What? 子どもの発達における痙縮の位置づけは?
脳性麻痺の約80%は痙直型麻痺である.それに伴う痙縮は新生児期ではまだ現れないが,生後6カ月頃から錐体路の髄鞘化が進むにつれて徐々に顕在化する.小児期の痙縮は,正しい姿勢・運動学習を阻害し,脳の可塑性や運動発達を遅らせる.また,筋肉の粘弾性の低下・線維化と骨の成長抑制によって,二次的な骨格変形の要因となる.
Q2 Who? 痙縮が疑われる子どもにはどのような特徴があるか?
痙縮は,錐体路系の障害による運動麻痺に伴って現れるので,随意運動の減少,筋力の低下,動作の緩慢や巧緻性の低下を背景にした運動発達の遅れを認める.また,Babinski反射の陽性を伴う.痙縮の本態は,速度依存性の筋伸張反射の異常亢進であり,腱反射の亢進やクローヌスが特徴的所見である.痙縮は屈筋群や内転筋群に強く現れるため,内反尖足等の特徴的な異常肢位を引き起こす.
Q3 When? Where? いつから・いつまで痙縮治療を実施するのかが適切か?
痙縮によるADL・QOLの低下があれば,重症度を問わず,早期から痙縮治療を開始し,その効果が続く限り成人期以降も治療を継続する.広範な痙縮には,乳児期から経口筋弛緩薬,幼児期からバクロフェン髄腔内持続投与療法が適応となる.局所的な痙縮には,おおむね2歳からボツリヌス療法,就学前後には脊髄後根切断術が適応となる.
Q4 How? どのように痙縮を評価し,リハビリテーション診療を行うべきなのか?
痙縮の程度や関節可動域だけでなく,ADL・QOLへの影響(姿勢・運動障害や日常生活活動の自立度・介護負担度等)を合わせて評価する.また,合併症や二次障害についても痙縮との関連を精査する.そのうえで痙縮治療の必要性を検討し,治療後には客観手法によって効果を判定する.リハビリテーション訓練計画を治療効果に応じて見直し,達成し得る到達目標や訓練方法を再設定しなければならない.
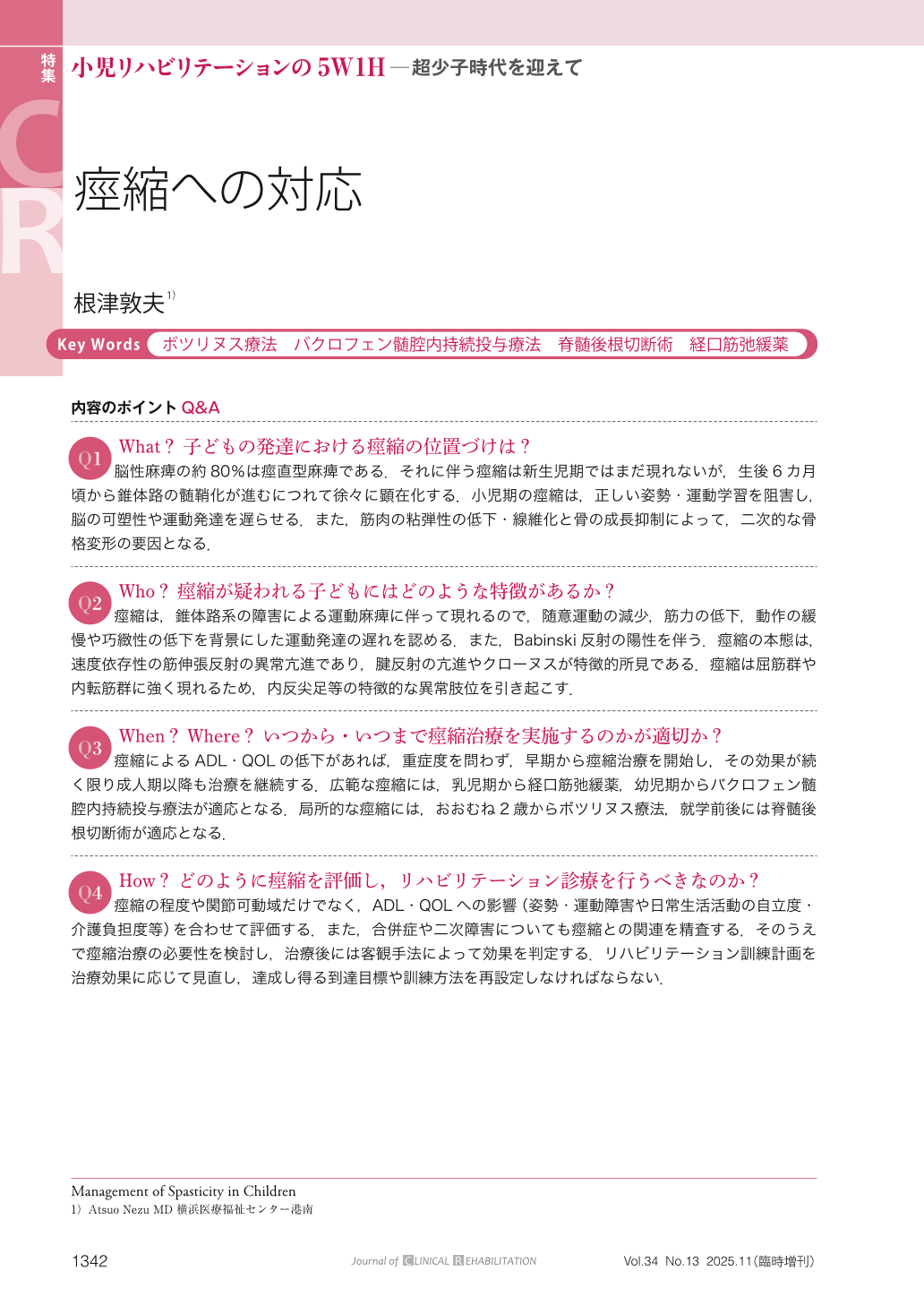
Copyright© 2025 Ishiyaku Pub,Inc. All rights reserved.


