Japanese
English
特集 腎性貧血の最新動向―2025年版CKD患者における腎性貧血治療ガイドラインの要点と実践
各論
CKD患者の貧血管理 JSDTガイドラインと国内外ガイドラインとの比較
Comparison of JSDT guidelines with national and international guidelines
土谷 健
1
,
川口 祐輝
2
TSUCHIYA Ken
1
,
KAWAGUCHI Yuki
2
1東京女子医科大学腎臓内科
2横浜労災病院腎臓内科
キーワード:
フェリチン
,
HIF-PH阻害薬
,
腎性貧血
,
TSAT
Keyword:
フェリチン
,
HIF-PH阻害薬
,
腎性貧血
,
TSAT
pp.319-325
発行日 2025年9月25日
Published Date 2025/9/25
DOI https://doi.org/10.24479/kd.0000002021
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
- 参考文献 Reference
はじめに
腎性貧血管理は,遺伝子組換えヒトエリスロポエチン(recombinant human erythropoietin:rEPO)の臨床応用以降,Hb値の管理が容易となり,当時の大規模試験では,2006年および2009年に,CREATE,CHOIOR,TREATの結果は大きなインパクトとともに腎性貧血管理のガイドライン(GL)に反映された。当時,Kidney Disease Outcomes Quality Initiative(K/DOQI),European renal best practice(ERBP),United Kingdom Renal Association(RA,現UK Kidney Assosiation:UKKA),Canadian Society of Nephrology(CSN)など,海外のGLが発表され,わが国でも2004年に日本透析医学会(JSDT)より腎性貧血の治療GLが作成され,その後2008年,2015年にGLの改訂が,2012年には日本腎臓学会からCKD診療ガイド2012が発行された。さらに,長時間作用型の赤血球造血刺激因子製剤が加わり,現在はESA(erythropoietin stimulating agent)として総称されている。また,2019年からは,HIF-PH(hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase)阻害薬が登場,内服薬である点,単にエリスロポエチン(EPO)作用のみならず,鉄代謝環境の改善などの効果をもつ特色がある。
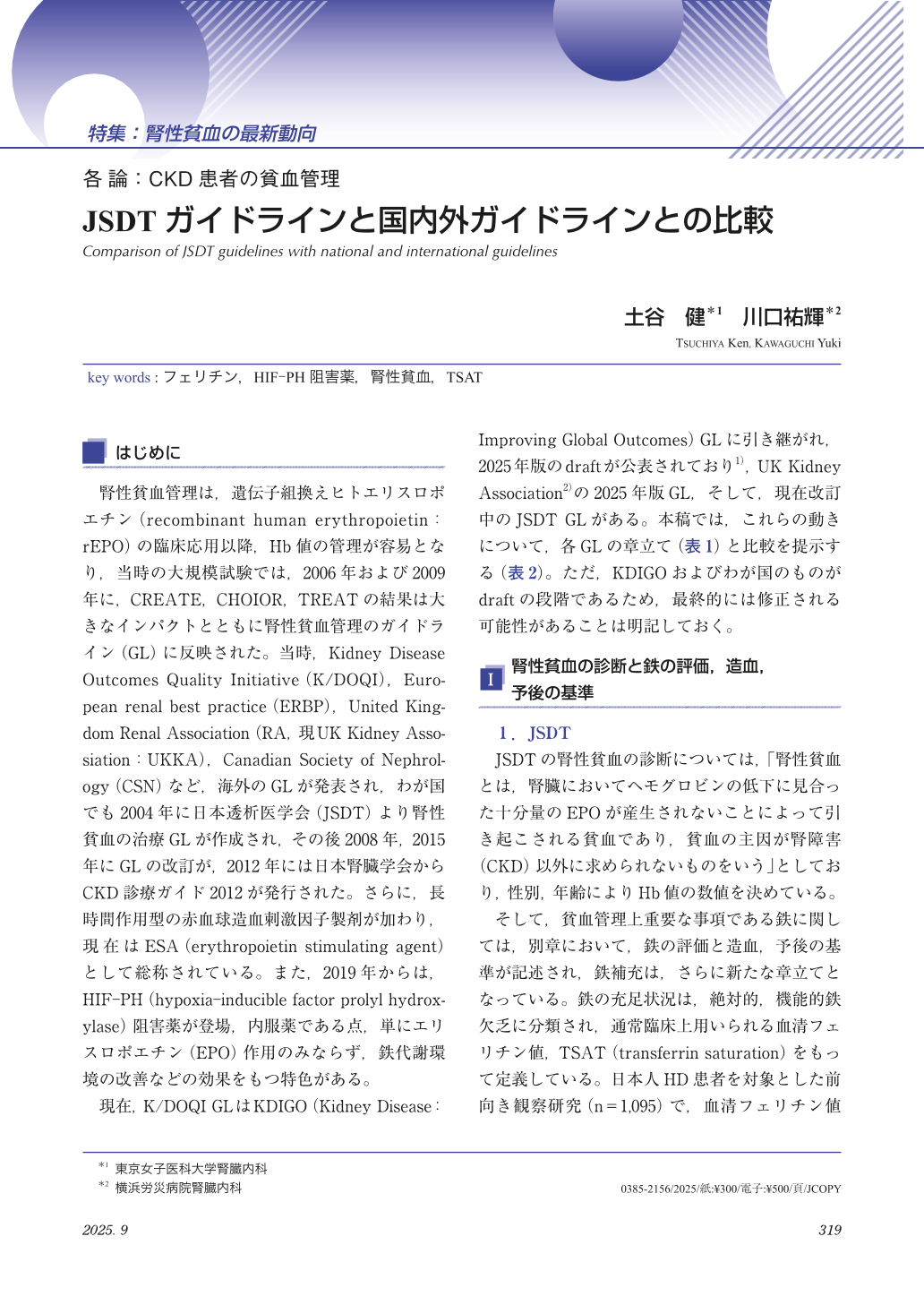
© tokyo-igakusha.co.jp. All right reserved.


