Japanese
English
特集 透析療法の課題,展望
各論
腹膜透析
腹膜生検
Peritoneal biopsy
本田 一穂
1
HONDA Kazuho
1
1昭和大学医学部顕微解剖学
キーワード:
腹膜硬化症
,
終末糖化産物(AGE)
,
血管病変(vasculopathy)
,
被囊性腹膜硬化症(EPS)
,
新生膜
Keyword:
腹膜硬化症
,
終末糖化産物(AGE)
,
血管病変(vasculopathy)
,
被囊性腹膜硬化症(EPS)
,
新生膜
pp.83-88
発行日 2025年1月25日
Published Date 2025/1/25
DOI https://doi.org/10.24479/kd.0000001749
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
- 参考文献 Reference
はじめに
1980年代に持続携行式腹膜透析(continuous ambulatory peritoneal dialysis:CAPD)が普及するにつれ,各施設で腹膜透析(peritoneal dialysis:PD)患者が増えてきた。90年代に入ると長期PD患者が多くなり,そのなかで除水不全をきたす患者がみられるようになった。除水不全でPDを離脱せざるをえない症例に対して,その病態を解明する目的で,PD離脱時の腹膜生検がはじまった。同じころ,除水不全でPDを離脱した患者のなかに,重篤な合併症である被囊性腹膜硬化症(encapsulating peritoneal sclerosis:EPS)を発症する患者が現れ,PDの臨床現場に激震が走った。何とかして患者を救うため,腸管癒着剝離術が行われ,この時に採取される腹膜組織の病理学検討がなされた。2000年以降,中性透析液が臨床に導入されると,除水不全やEPSの患者は減少し,現在に至っている。本稿では,PD臨床において,これまでに腹膜生検が果たしてきた役割を歴史的に振り返り,腹膜生検からみたPD療法の安全性についての課題と,今後の取り組みについて考察する。
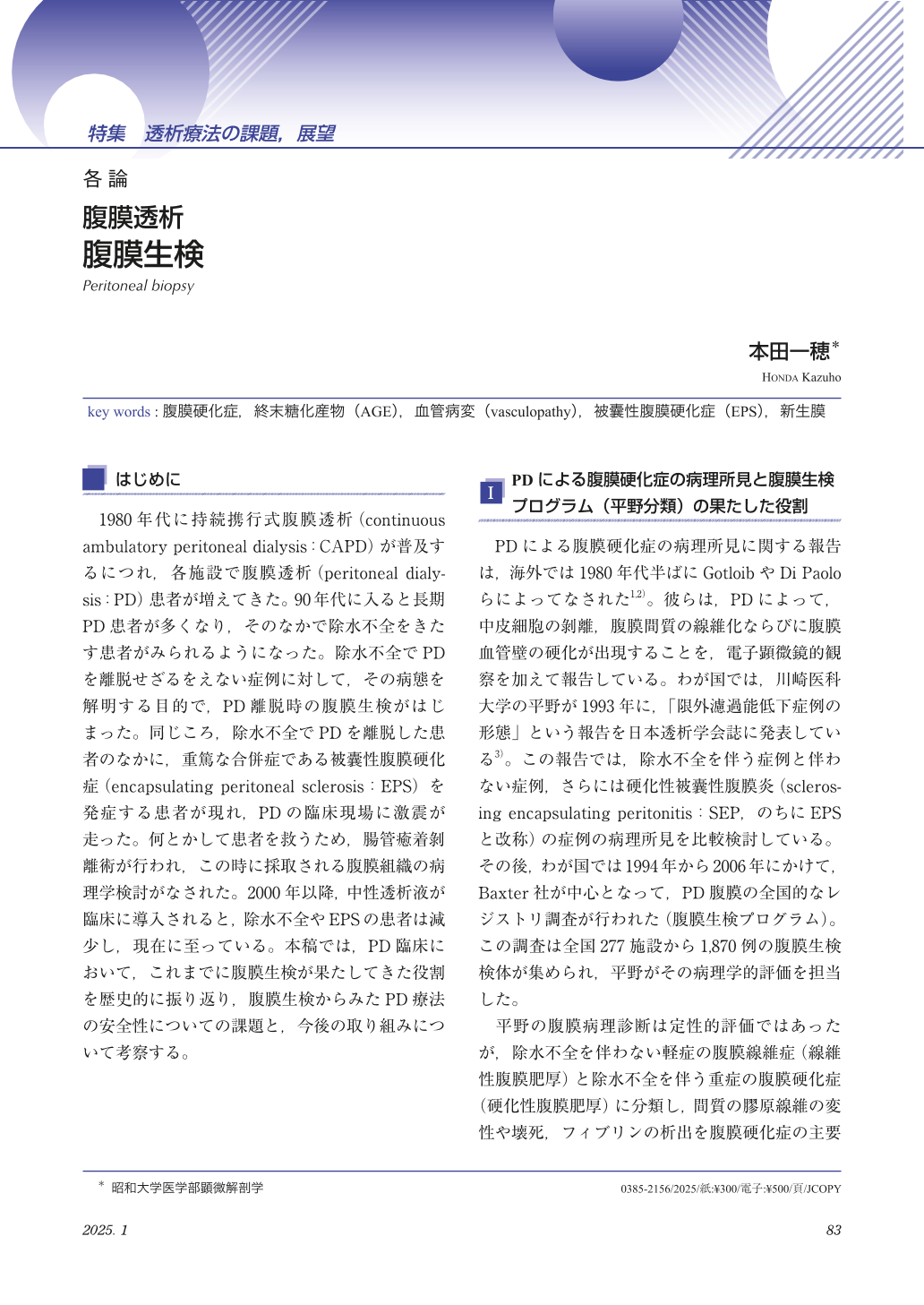
© tokyo-igakusha.co.jp. All right reserved.


