- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
目的
緑内障患者において,点眼に関する経験や意識を明らかにすること。
対象と方法
本調査は,点眼手技評価および失敗に関連する因子を推定するVideo-Recorded Assessment of Medication Skill and Questionnaire-based evaluation of Perception in Glaucoma(VRAMS-QPiG)Studyとして実施した。島根大学医学部附属病院眼科緑内障外来に新規に紹介された緑内障患者60名を対象として,点眼状況に関するアンケートAを施行した。その後,点眼指導を実施し,点眼指導後に点眼手技に関するアンケートBを実施した。アンケート調査内容は,正しい点眼以外の点眼操作の経験の有無,点眼時の困りごと,点眼指導を受けた経験の有無,指導した正しい点眼の理解度および正しい点眼実施への意欲等とした。統計解析は,各アンケート回答の集計とした。
結果
60例(男性30例,年齢68.4±11.3歳)が,アンケートAおよびBともに回答した。点眼指導前のアンケートAでは,点眼時の経験として「点眼位置がずれやすい」「1回で成功せず何回も点眼してしまう」と回答した患者はそれぞれ32例(53.3%),30例(50.0%)であり,その際に困ったとの回答はそれぞれ32例中24例(75.0%),30例中18例(60.0%)であった。「目やまつげやまぶたに点眼容器の先がつくことがある」「2滴以上でる」との回答はそれぞれ26例(43.3%),24例(40.0%)であったが,それに対し困っているとの回答はそれぞれ26例中10例(38.5%),24例中8例(33.3%)であった。点眼指導後のアンケートBで,医師,看護師や薬剤師による点眼指導については,「1度も指導を受けた経験はない」との回答が42例(70.0%)であった。点眼指導後に正しい点眼をしたいと回答した患者は60例(100%)であった。また,選択肢のなかから正しい点眼方法はどれかを選ぶ設問では,95%以上が正しい点眼方法を選択した。点眼指導を受けた前後で,自身の点眼評価を変更した患者が12例(20.0%)存在した。
結論
正しい点眼手技で点眼できていない患者は多いが,医師,看護師や薬剤師による点眼指導を受ける機会が少なく,正しく点眼できていなくても困っていないことが明らかとなった。正しい点眼方法を理解させ,実際に起こっている状況を把握したうえで,適切な点眼を指導することが重要であると考えられた。
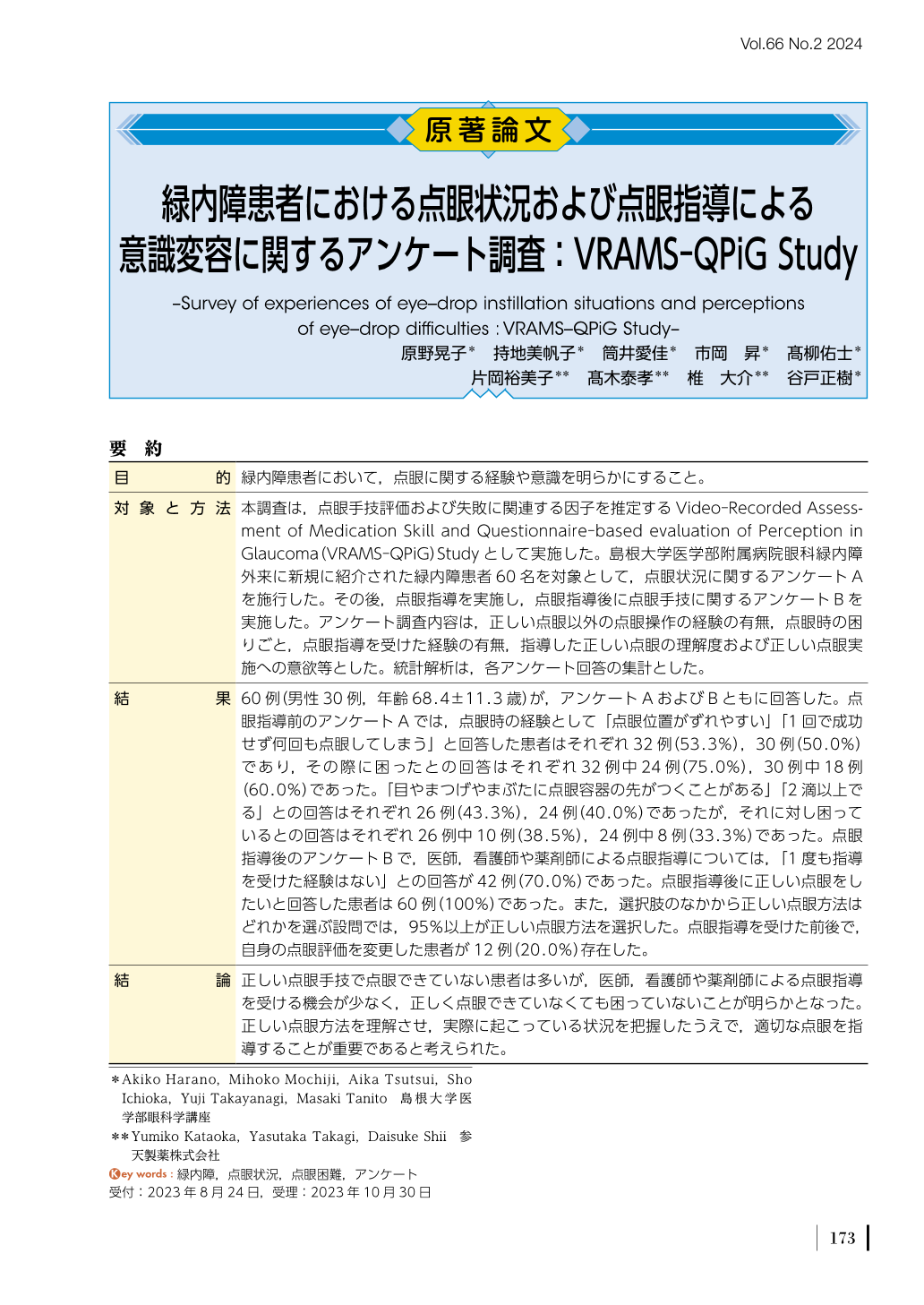
Copyright © 2024, KANEHARA SHUPPAN Co.LTD. All rights reserved.


