連載 がん―家族の肖像 第8回
終末期の大事なときに「語り合えなくなる」患者と家族
柳原 清子
1
Kiyoko YANAGIHARA
1
1金沢大学保健学系 がん看護/家族看護
pp.681-685
発行日 2019年9月1日
Published Date 2019/9/1
DOI https://doi.org/10.15106/j_kango24_681
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
- サイト内被引用
はじめに
宮澤賢治の詩「永訣の朝」にこんな描写がある.肺結核で高熱にうなされる妹‘トシ’が最期に《あめゆじゅとてちてけんじゃ(雪を取ってきてほしい)》と所望し,賢治は《青い蓴菜のもやうのついた/これら二つのかけた陶椀に/おまへがたべるあめゆきをとらうとして/わたくしはまがったてっぽうだまのやうに/このくらいみぞれのなかに飛びだした》とある.「じゅんさい模様の2つの陶椀」とは,兄妹が幼い時から使ってきた茶碗なのであろう.
死ぬ間際に甘える妹と,精一杯のことをしてやりたくて,早朝のまだ暗い霙降る外へ飛び出していく兄の姿がある.
がん終末期臨床でも看護師たちは,宮澤賢治とトシにあったような,逝く人と看取る家族の濃い時間をサポートしたいと強く願う.それは,“グッドデス(peaceful death:平穏な死)”の構成概念には,「自分にとって大切な人が近くにいると感じられること」があり1),こうした患者・家族の関係調整は終末期ケアの必須要件であることをよく知っているからである.
しかし現実は,これまでの本連載の事例で紹介してきたように,自分の殻にこもって語ろうとしない/語れない患者と,近い「死別」の現実に圧倒されて,かける言葉が見つからない家族の姿があり,さらに医療者には知り得ない家族の歴史が両者の関係性に絡んでくるとき,「何をどうサポートすればよいのか」との看護師のとまどいは大きくなる.
なぜ,終末期の大事なときに患者と家族は,語り合えなくなるのだろうか? そこにはいくつかの様相があるように思う.その様相を,事例を通して紹介しながら考えてみたいと思う.なお,提示する事例はフィクションである.
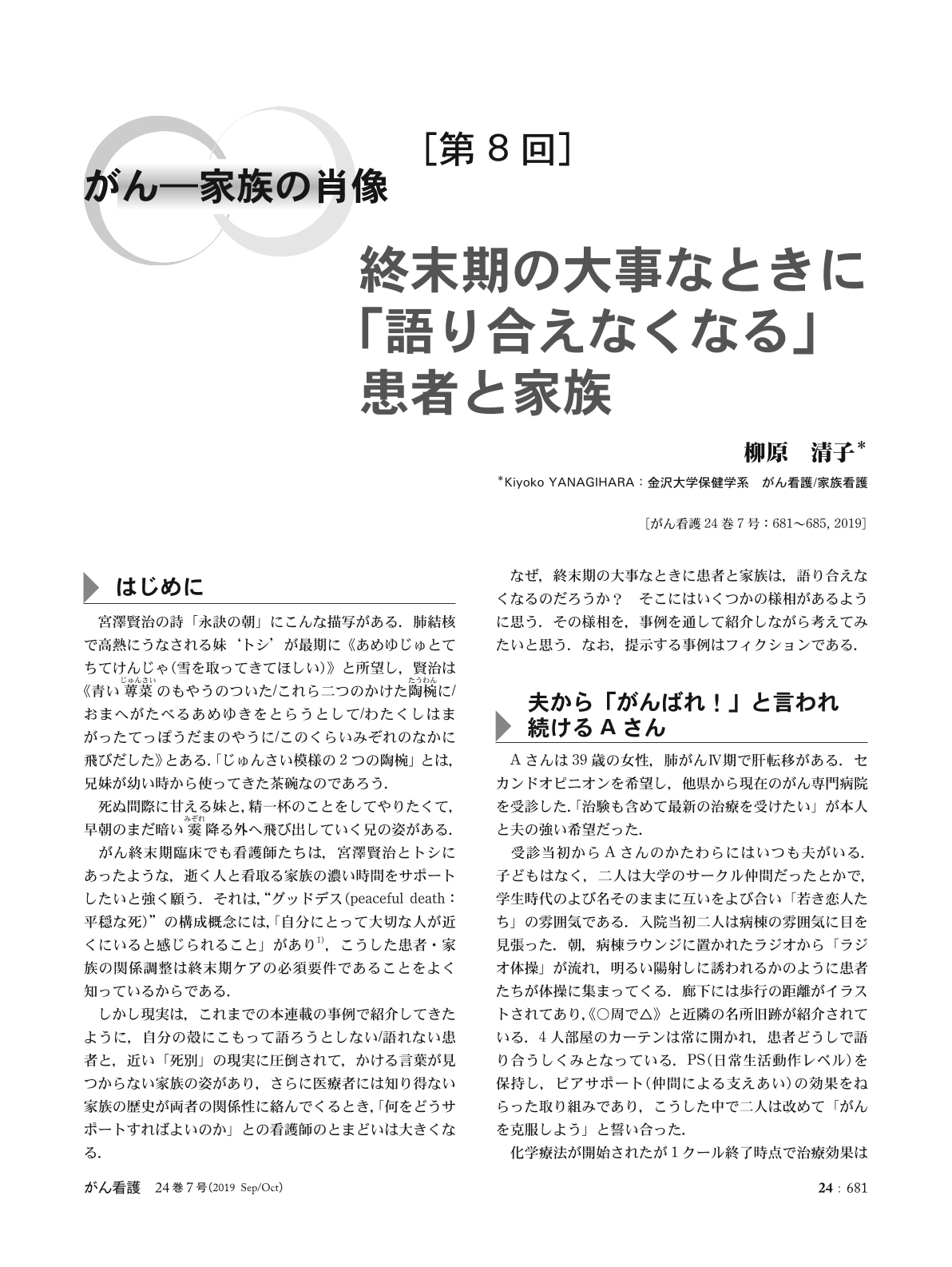
© Nankodo Co., Ltd., 2019


