Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
- 参考文献 Reference
はじめに
頸椎症性神経根症は脊髄症と比較し頻度が高い病態である21).一般的に,上肢の疼痛,しびれといった感覚障害をきたし,多くの場合,保存的治療で改善する.このため,実際の発生頻度は把握しきれず,高位診断もされないまま改善している症例も多い.重症の神経根症の場合,高度の疼痛や,疼痛が遷延することで日常生活に支障をきたしたり,運動機能障害をきたす.疼痛改善時に高度の運動機能障害を生じた際には速やかに手術治療を行う必要がある.内服治療で効果が得られない強い疼痛に対しては超音波ガイド下,透視下の神経根ブロックが有効であり,侵襲的治療を行う際には高位診断が必須となる.
日本は経済協力開発機構(OECD)加盟国内で人口あたりのMRI保有台数が最多であり,人口100万人あたり57台(2位韓国36台,3位米国28台,メキシコ3台,コロンビア0.2台)を保有している10).このため,比較的MRI診断を受けやすい環境にある.X線で骨性の椎間孔狭窄は確認できるが,椎間板ヘルニア,肥厚靭帯などの軟部組織で実際に神経根が圧迫を受けているかどうかの診断にはMRIが有用である.MRI導入当初は所見として「椎間高の低下,椎間板変性,正中を含む椎間板組織の脱出」程度しか評価の対象とはならなかったが8),近年では椎間孔内外の神経根自体を評価できる.しかし,脊椎変性疾患は画像上の所見と神経症状が必ずしも一致するわけではなく,画像上神経圧迫が疑われても発症しない部位もあれば,MRI,CTでは圧迫所見を呈していなくても動態による圧迫により発症することも一般的である.また,頸椎のdermatomeは比較的バリエーションが少ないが,必ずしもdermatome通りとばかりはいえない症例に出合うこともある.従来より画像と神経所見のみで診断することに対して問題提起されており,解決法として生理学的検査の有用性が報告されている14).最近では画像で神経障害部位を同定しようとする機能画像評価も応用されている.本稿では頸椎症性神経根症のMRI診断に関係する解剖,問題点を考察する.
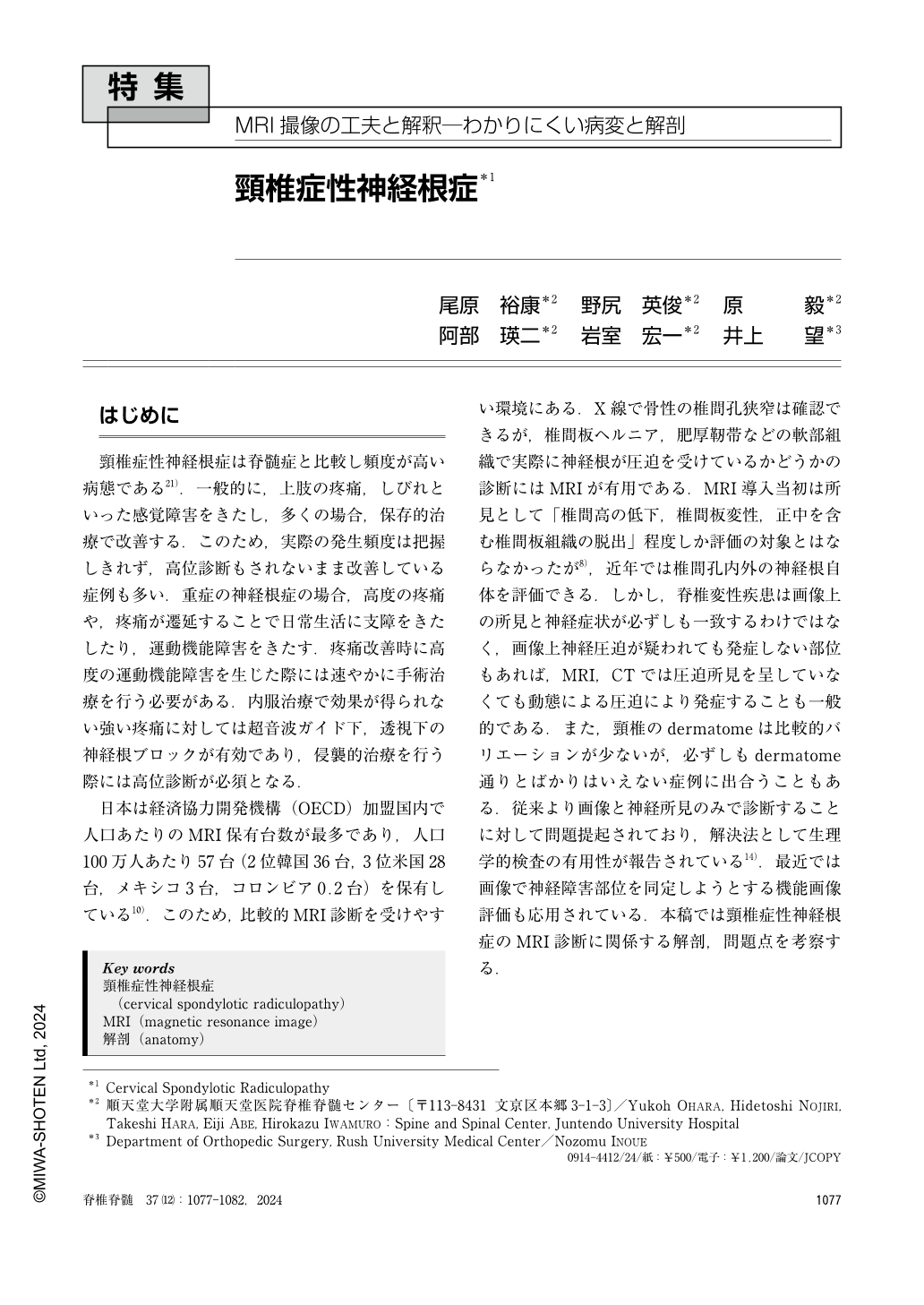
Copyright © 2025, MIWA-SHOTEN Ltd., All rights reserved.


