- フリーアクセス
- 文献概要
- 1ページ目
脊髄動静脈奇形の分類については現在まで数多く提唱され,時代とともに変遷してきましたが,このことは画像診断の発達によりなされてきました.すなわち,まず歴史的には血管造影による異常血管の形態的な把握がなされ,MRIにより異常血管の描出が容易になり,脊髄の浮腫の有無と範囲,出血の有無の把握ができるようになり,高速DSAによるAV shuntの局在の把握が可能となり,3DCTAにより周囲の脊椎との関係も容易に把握できるようになりました.さらにはfusion imageで,これらの画像情報をintegrateした情報が,術前に理解できています.また,最近では血管内手術の発達により,以前では治療不可能であったAV shuntも治療可能となりました.さらに,観血的手術の際でも術中のICGの活用によりAV shuntの的確な同定が困難となり,従来は治療困難な髄内動静脈奇形に対しても最近では定位放射線治療が試みられてきています.
ただし,脳の動静脈奇形では,nidusの外科的摘出の際の難易度の指標としてSpetzler-Martin分類が有名であり,nidusの大きさ,部位がeloquentか否か,導出静脈の部位によりgradeが示されていますが,脊髄動静脈奇形ではどうでしょうか.脊髄自体は脳とは異なり,ほぼeloquentな組織であり,nidusあるいはAV shuntが大きく発達する前に重篤な症状が出現するので,脳の動静脈奇形とは違う考えで行かねばなりません.脊髄動静脈奇形ではやはり前脊髄動脈の関与の有無,AV shunt数,AV shuntの位置,脊髄の腹側か,背側か,さらには複数の動静脈奇形が存在するmetamericなものでは,やはり難易度が高いと思われますが,このことについては今後の課題として若い先生方に考えていただこうと思っています.
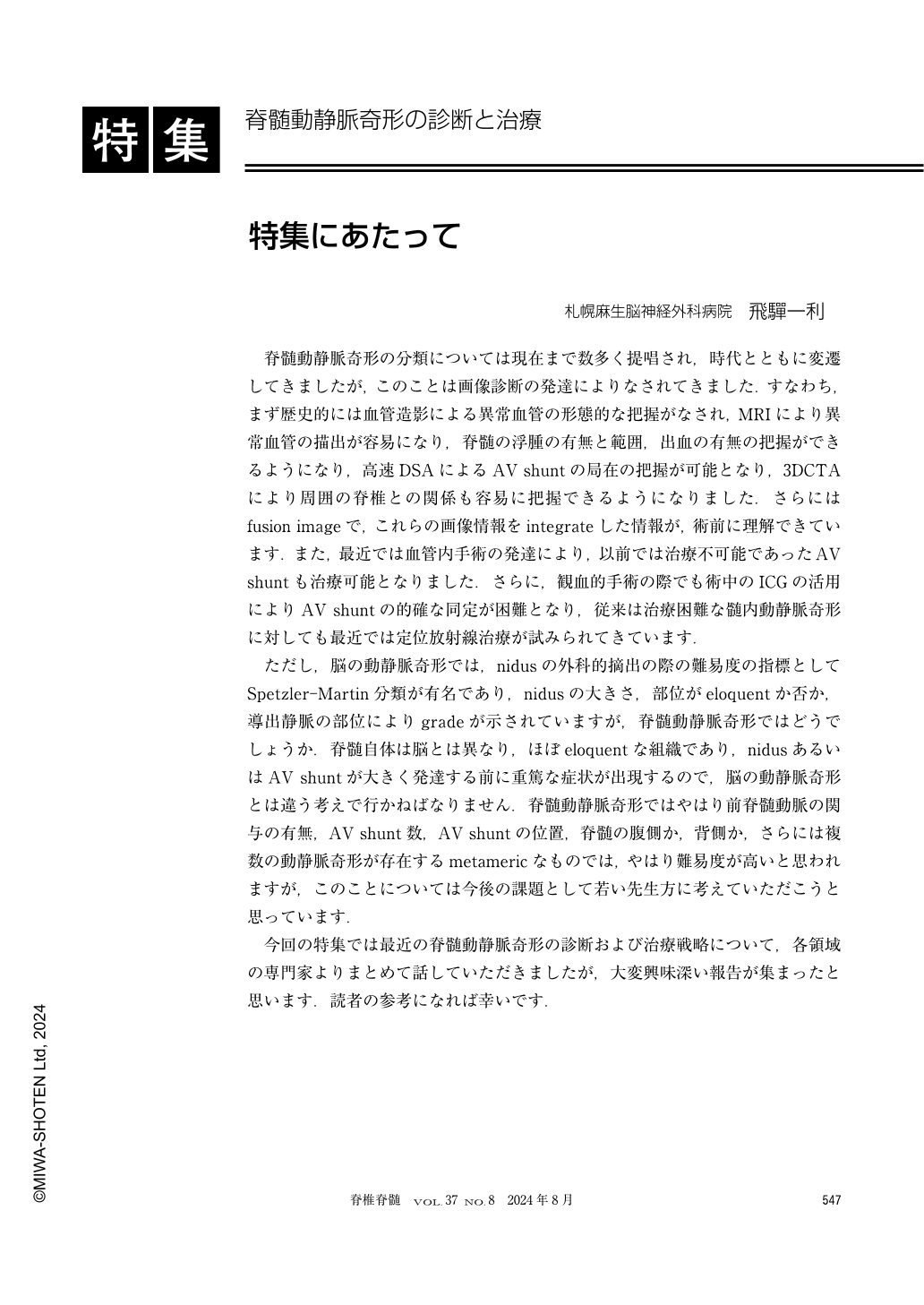
Copyright © 2024, MIWA-SHOTEN Ltd., All rights reserved.


