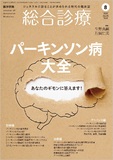- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
パーキンソン病、パーキンソン病関連疾患の認知症については、さまざまな文献や資料があり、❶パーキンソン病進行期には高頻度にみられること、❷アルツハイマー型に比べて、記憶の障害は軽度であること、❸症状の変動が激しいことなどが特徴として挙げられている1)。こうした症状が「皮質下性痴呆」と呼ばれ、それは当時「痴呆」と呼ばれていたアルツハイマー型認知症が海馬を中心とした大脳皮質障害2)であるのに比べ、基底核の病変から生じるということで、皮質とのネットワークの障害と考えられたためである。そうした認知症のカテゴリーの代表とされたのがハンチントン病とパーキンソン病である。その後、認知症を主体とする病型として、進行性核上性麻痺(progressive supranuclear palsy : PSP)と大脳皮質基底核変性症(corticobasal degeneration : CBD)が分けられ、パーキンソン病で認知症を呈する場合も同様のメカニズム、基底核〜大脳皮質(前頭葉)連関が想定された。さらに、パーキンソン病はα-シヌクレインが、PSPとCBDはタウが細胞内に溜まる別の病型に分けられ、遅れて、認知症が先行するα-シヌクレイン病としてのレヴィ小体型認知症(dementia with Lewy bodies : DLB)が提唱され広く受け入れられていくなかで、かつて考えられていたパーキンソン病認知症の皮質下性痴呆としての側面は、DLBの幻視・幻覚、誤認や妄想といった皮質機能障害のアスペクトに組み込まれていった。
しかし一方、PSPの病型は多彩で、また、CBDという病理学的カテゴリーに替えて使われるようになった大脳皮質基底核症候群(corticobasal syndrome:CBS)は、病理診断ではCBDの他に、アルツハイマー病、パーキンソン病、PSPなど、多様な原因が知られている。加えて、α-シヌクレインとタウは分子的に関係しやすいもので、高齢になれば、シヌクレイノパチー、タウオパチーという線引きはオーバーラップしてくる。さらにはアルツハイマー型のアミロイドや血管病変もここに絡んでくる。どちらかといえば、DLBは幻視・幻覚・誤認からの、PSPは衝動性制御の低下からの心理行動症状が、CBSは自発性低下が目立つといえるが、進行期のパーキンソン病にみる認知症では、そのどちらも認められる。
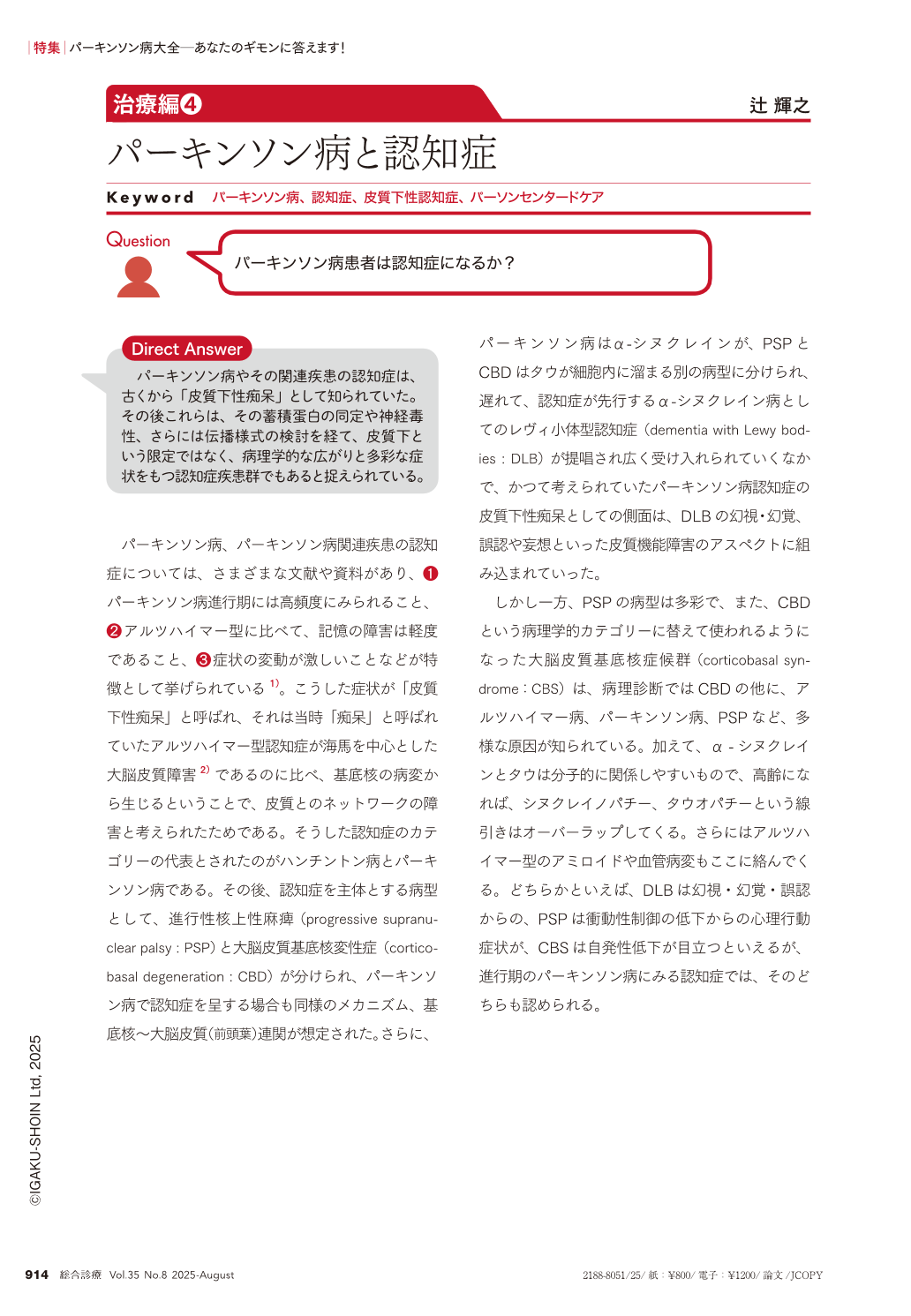
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.