特集 患者の死後,看護婦は……
患者の臨終,家族へのフォロー
人間らしい,安らかな臨終を迎えられるように—末期癌患者とのかかわりを通して学んだこと
鹿野 卓子
1
1東北年金病院内科病棟
pp.982-984
発行日 1990年10月1日
Published Date 1990/10/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1661900232
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
初心に立ち戻らせた一文
「いよいよ臨終というその時,家族はみな病室の外に出され,医者と看護婦だけが1分でも長く生命を保たせようと懸命の努力を始めました.モニターはすでに心臓機能の停止を明示しているのにもかかわらず,なぜこのようなことを…….言い表わしがたい悲しみと憤りのような熱いものが私の胸にこみ上げてくるのでした.息子や孫たちは病人の手を握ってやることも,最期の言葉を聴きとってやることも許されず,ドアの外から,ただじっとみつめるほかはありません.家族にとっては死んでいく人の胸にすがって思いきり名を呼び,声をあげて泣くことができたら,むしろ慰められるであろうものを」(菊地多嘉子:看護のなかの出会い,日本看護協会出版会,1987).
この一文を読みながら,私は10数年の看護婦生活の中での数えきれない臨終の場面を思い起こしました.就職して間もない頃,病室を訪れた時にはすでに息絶えていた患者には誰1人身寄りがなく,最後の納棺も看護婦が行なったこと.その後,癌で最後まで痛みを訴え続け若くして亡くなった患者,浮腫や腹水の貯留で全身の苦痛を訴えた患者等々,軽快退院した患者さん以上に,亡くなった患者さん1人1人を鮮明に思い起こします.そして「こんなこともしてあげればよかった.あの時にもっと優しくしてあげればよかった」と後悔したものです.
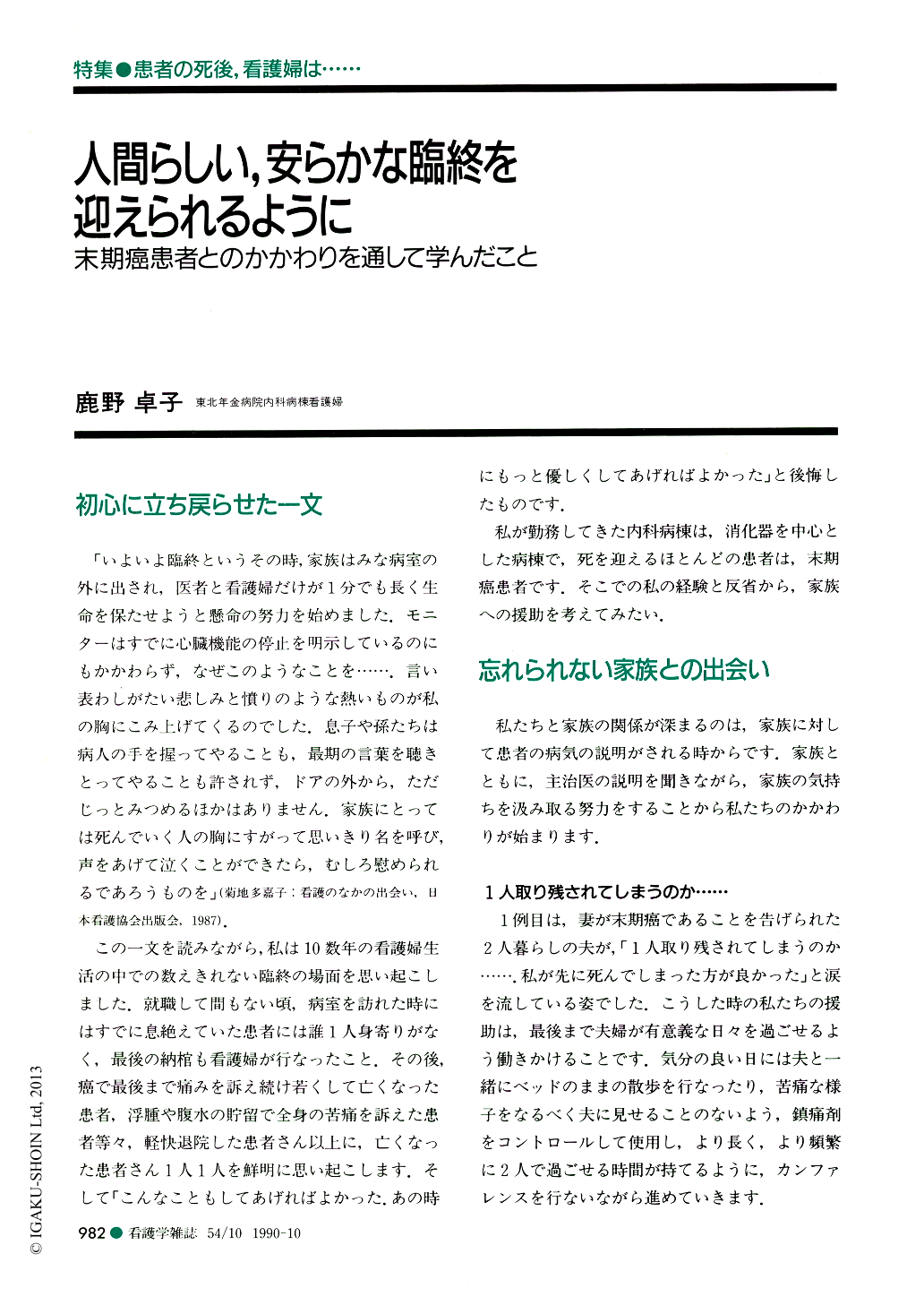
Copyright © 1990, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


