Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
はじめに
本症に対してはJ.L. Down(1866)の症候学的研究にはじまり,Lejeune(1950)らの遺伝学的研究をエポックとして,内外にわたり多くの研究がなされている.わが国では,1963年厚生省特別研究班の発足により,医学的,教育学的に幅広い障害を持つ本症候群児に対しても,その治療と教育と社会的処遇についての本格的なとりくみが示され,教育界からは1973年に出版された「ダウン症状群」1)に見られるように,しつけ,心理面からの考察,ことばの問題などに重点がおかれたとりくみが行なわれてきている.また,1964年に発足した,ダウン症親の会「小鳩会」は,早期訓練に目を向け,4~5歳よりはじめて,現在では全国30ヵ所近くで,2歳前後からの幼児訓練学級を実施して効果をあげている2).
一方,医学界からも,生物学的アプローチを通して,本症に関するいろいろな事実が明らかにされており,過去5年問の研究から拾ってみると,疫学的には「ダウン症とその他の染色体異常の発生率は,ここ5年間に2倍近くまで増加している」3)という発表があり,「ダウン症児の出産母年齢の若年化傾向」4)があるという現象とあわせると,人によってはこれを「環境汚染,生態系の破壊,人類の生物学的生命枯渇」3)の一現象としてとらえる事さえなされている.総論的には,寺脇らの南九州地区のダウン症児についての疫学的,発達・発育学的研究があり5),その他にも,臨床診断6)について,医学の知識7)として,また最近の話題8)として,臨床講義9)として,ダウン症は積極的にとりあげられるようになった.しかし,この中で全体的発達に対する取り組みに関しては,ほぼ同様に「医学的には,根本的な治療法は現在のところないので,特殊教育に期待するところが大きい」7),「乳幼児期には,一般的養護に配慮し,年長児になれば本症患者の身体機能や精神的特性に基礎を置いた訓練,学習,生活療法をみる」8)などとされ,これが医学界の平均的態度であるように思える.
しかし,このような医学的とりすまし方に反発を覚える人も多く,長年,本症児の医学的管理・生活指導にあたってきた栗田は,「ダウン症児に対しては,医学と医療のへただりが厳然として存在し,その間隔が一向に縮まらない」事をなげきながら10),このような子供達に対する家庭や社会の適切な指導と,十分な理解11),ある年齢までは専門職員の完備した一定の収容施設内での,医学的管理下における医学的・教育的・心理的庇護の下での社会復帰をめざした集団管理を提案している.
このように,あらためてダウン症児治療の方向性を考えてみると,これは私どもが十数年前から少しずつ取り組んできた肢体不自由児療育の歴史に良く似ている事に気づく.しかも残念ながら,発達という面からみると,ダウン症児に対するこの療育の現状は,脳性麻痺を主体とする運動発達障害児の療育の現状に比して,まだまだ低いレベルに沈滞している事にも,また気づくのである.この子供達が,運動発達も精神発達もすぺてダウンであり,精薄であるからというきめつけ方をされたままで,一生の間で,発達学的に一番可能性のある時期を,むざむざと放置されたままでいる事は,子供,家族はもとより,障害児の発達に介入(intervention)すべき立場にある私どもにとっても不幸な事であるといえる.かくしてダウン症児は依然としておおかたのイメージを変える事なく現在にいたっているわけである.
このようなダウン症児療育の現況には,次の二点に反省すべき問題があると考えられる.
①今まで,全体的発達学的立場での医学的参加が極めてすくない.
②2~3歳からという療育開始年齢は,発達という概念からでは遅すぎる.
そこで私どもはこの反省に立って,1975年末からダウン症乳児の療育に組織的に取り組んできたが,今回機会を得,この結果をまとめて短期経過として発表し,ご批判を仰ぎたいと思う.
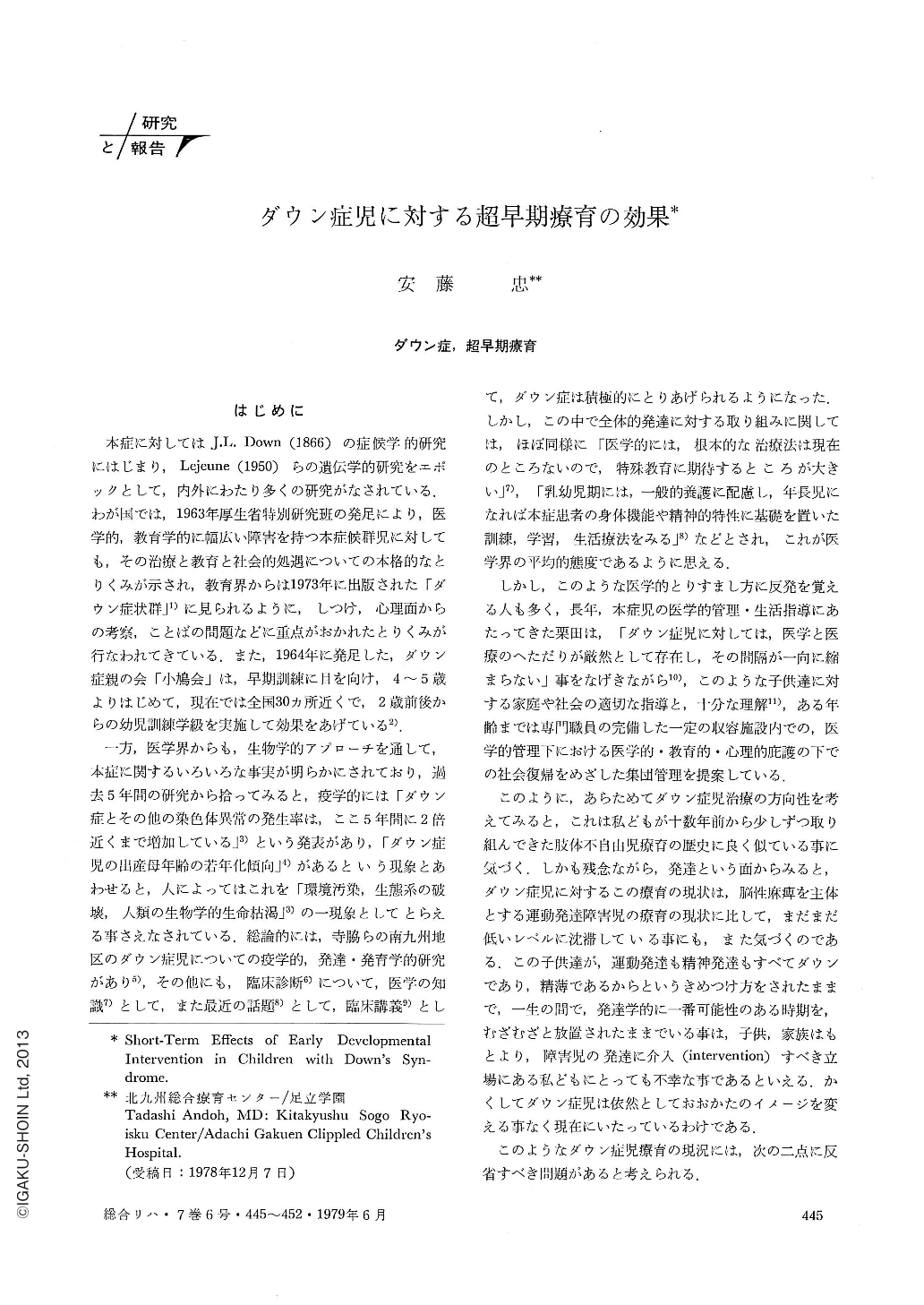
Copyright © 1979, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


