- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
現在化学療法の発達によるも尚慢性副鼻腔炎の治療は根治手術に依らざるを得ない場合が多い。然し根治手術を行つても毎常根治を期待する事が出来ないものや再発を来すものが尚相当ある事は否定出来ない。手術に依るも難治である原因は種々あるであろうが何よりも副鼻腔の如く外界と交通を有し,且つ病巣の徹底的除去の困難なところの手術に於て術創の経過を殆ど直接観察する事が出来ず,概ね自然の経過に委ねている事にその原因の大半があるのではないかと考える。西端教授はこの点に留意され上顎洞に就て松本・西端式対孔を作製して洞内を直視して処置する事を考案された。この点篩骨蜂巣開放術創に就ては中鼻道に交通孔をつける事が行われており或程度は術創を観察治療する事も出来るが尚充分でない場合が多い。そこで中甲介の中鼻道側半分或は前端切除等が行われているが尚充分でない場分が多い。この際中甲介の大部分を切除する事が出来,篩骨蜂巣鼻腔側壁を除去するならば篩骨蜂巣の開放は充分出来ると共に術創を充分観察しながら術後処置をする事が出来る訳である。然し現在のところ大多数の学者2)3)は鼻腔生理及び頭蓋内合併症の危険等の理由の下に中甲介切除は可及的避け度いと云う考えが支配的である。然し楔状洞炎の手術の際は中甲介切除も止むを得ないとする者もあり,又中甲介の大部分を切除した場合の実際上の機能障碍或は危険等の報告は余り見られないにも拘らず,臨床上は高度の筋骨蜂巣炎で篩骨蜂巣鼻腔側壁より中甲介全般に亘り殆ど茸状変化を来し止むなく之等を殆ど除去した症例や,又篩骨蜂巣開放時誤つて中甲介を殆ど除去した症例に遭遇するのであるが,此等の症例に於て自他覚的に鼻腔機能障碍を殆ど認めず,却て良好な治癒状態にある事を見るのである。
茲に於て吾々は現在の中甲介手術に余り大事を取り過ぎている事に疑問をいだいた次第である。村井氏4)に依れば中甲介には約14%に中甲介蜂窠を有し,之に炎症が波及する事があると述べて居り,又稲葉氏は慢性副鼻腔炎の際の骨病変に就て中鼻道側壁に於ては特に骨変化が甚だしいと述べており,中甲介には言及していないが之が茸状変化を来している時は骨変化も当然予想されるところであり,従つてこの病的部分を可及的除去する意味から云つても中鼻道附近より中甲介に亘り変化の甚だしいものは可及的除去する方がよいと考えられる。
Akaike and associates note that removal of the middle turbinates as well as the medial wall of the ethmoidals failed to result in causing disturbances in the nasal functions such as the sence of smell, delivery of speech and the effect on lower respiratory tract. Such a removal affording a large space facilitates the procedure of after treatment with better healing.
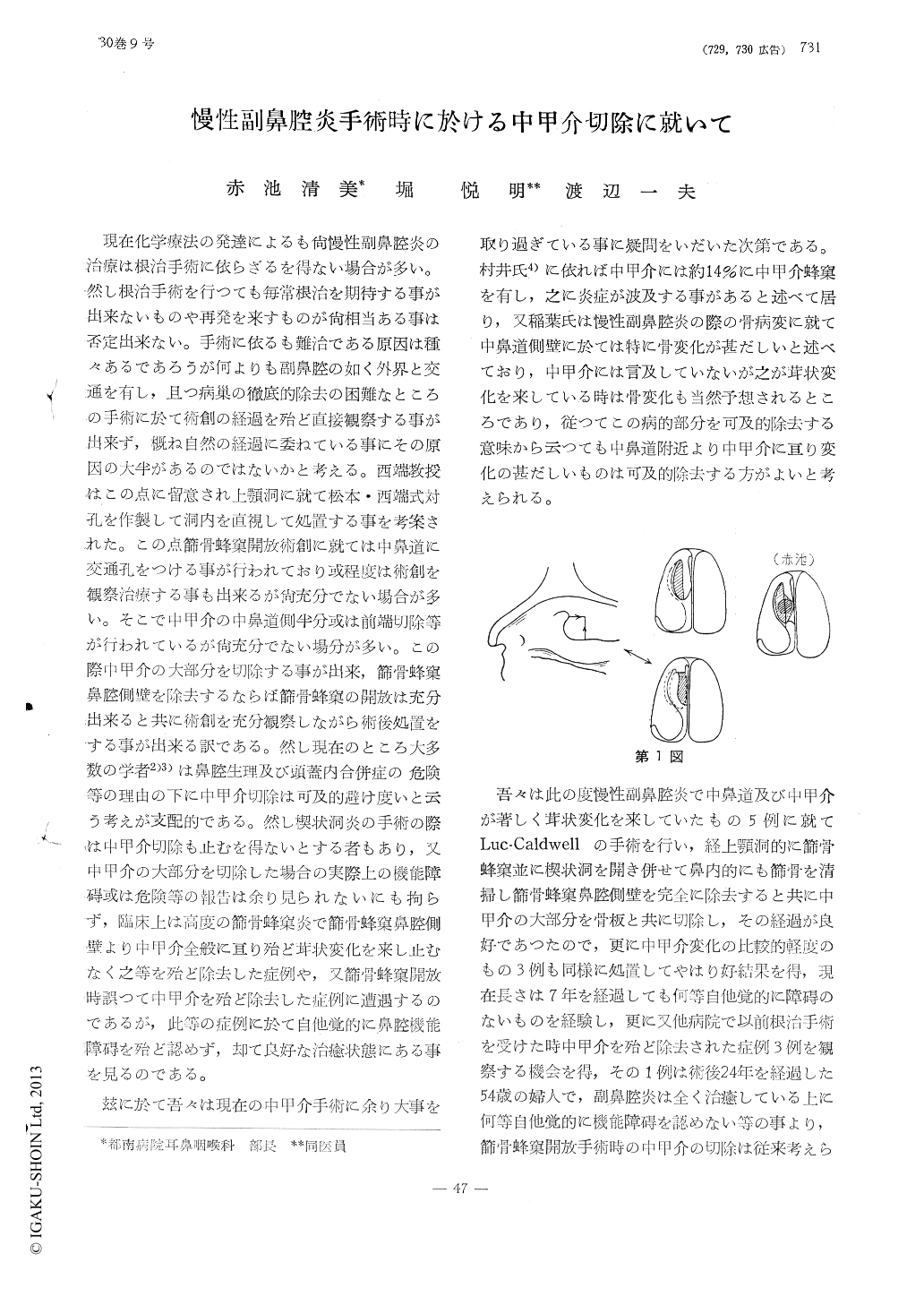
Copyright © 1958, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


