Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
- 参考文献 Reference
Ⅰ.はじめに
パーキンソン病(Parkinson disease:PD)に対する機能外科治療には長い歴史がある33).1920年代に錐体外路の概念が提唱され,線条体,淡蒼球,視床下核,黒質などを含むこの系が種々の運動障害疾患に関わっていることが示唆された.1940年にはPD患者に対して脳室経由で前部尾状核を切除する手術が行われ,麻痺を来さずに振戦や固縮を改善させることに成功した.しかし,こうした手術法は侵襲が大きく合併症率も高かったことから,その後は安全で正確な定位脳手術が行われるようになった.1947年にSpiegelとWycisによりヒト用の定位脳手術装置が開発され,PD患者に対する淡蒼球破壊術(pallidotomy)が行われた.本邦でもすでに1950年代より楢林らがpallidotomyや視床破壊術(thalamotomy)を行っている35).1960年代にL-dopaが導入されるとPDの治療は薬物療法が主体となった.しかし,1990年代になりLaitinenらが難治例に対して再び後腹側淡蒼球をターゲットとするpallidotomyを行い,良好な結果を得た26).一方,神経毒であるMPTPによるPDモデル動物が開発されるとPDの病態研究が急速に進み,PDの外科治療のターゲットとして視床下核(subthalamic nucleus:STN)が注目されるようになった7).1993年にフランスの脳神経外科医Benabidらのグループは,STNに対して脳破壊を必要とせずより安全性の高い脳深部刺激療法(deep brain stimulation:DBS)を行い大きな成果をあげた36).こうした経緯により現在のPDに対する機能外科治療はDBSが主流となり,特にSTN DBSが世界中で広く行われている.
PDに対するDBSの最もよい適応は,L-dopaによる運動合併症(日内変動,ジスキネジア)によりADLが著しく障害された患者である.STN DBSでは振戦,固縮,寡動など,特に薬剤オフ時の運動症状やADLを改善し,症状の日内変動やジスキネジアを軽減する.さらに術後はドパミン作動性薬剤の服用量を大幅に減量できる25).欧米で行われたいくつかのランダム化比較試験(randomized controlled trial:RCT)により,進行期PDに対する運動症状,QOLの改善において,DBSの併用は薬物療法単独に比べて有意に治療効果が高いことが実証されている17,45,48).STN DBSのこうした効果は5〜10年の長期的にもかなり持続する.症状別にみると,四肢の振戦,固縮,無動などに対する効果は長期的にもある程度維持される.一方,発声,嚥下,歩行(すくみ足),姿勢反射障害などの治療抵抗性の体軸症状は病気の進行に伴って徐々に悪化し,認知機能の低下とともに長期治療におけるADL悪化の要因となることから,体軸症状への対策が今後の課題であるといえる5,38).
これまで世界で14万例ものDBSが行われており,DBSの効果や問題点についての膨大な臨床的知見が蓄積されている44).しかしPDの運動症状に対するこのような効果は明らかであるものの,DBSの作用機序についてはまだ十分に解明されていない.一方,DBSの発展はそのデバイスの技術的進歩に支えられており,新しい技術が徐々に臨床応用されつつある.本稿ではPDに対するDBSの最近の話題として,作用機序に関する知見およびデバイスの技術的進歩について解説する.
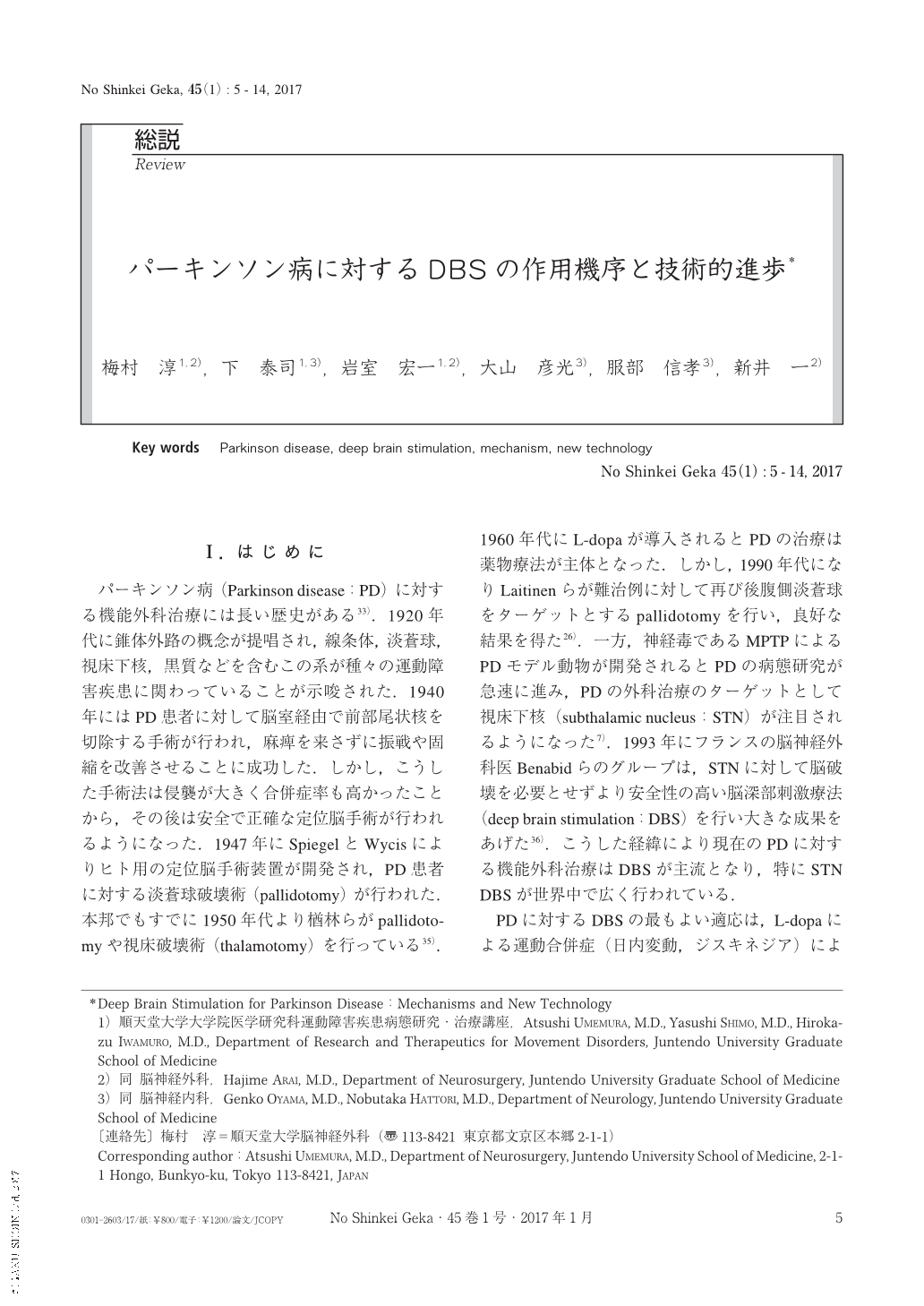
Copyright © 2017, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


