特集 泌尿器腫瘍の機能温存手術―知っておくべき適応と限界
企画にあたって
近藤 幸尋
1
1日本医科大学医学部泌尿器科学講座
pp.631
発行日 2020年8月20日
Published Date 2020/8/20
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1413206989
- フリーアクセス
- 文献概要
- 1ページ目
癌をはじめとした悪性腫瘍の外科療法は,時代とともに大きく変化をしています.小職が学生だった頃の外科の講義では,胃の早期癌であっても胃全摘術が基本であることを教わり,「小さな癌でも大きな手術を」が悪性疾患の手術の基本であると教えられていました.その後,内視鏡手術や腹腔鏡手術の進歩により低侵襲手術が良性疾患で広まり,その技術を悪性疾患でも応用し治療成績の非劣性を確認したうえで,適応が広がっています.
こういった低侵襲手術の目的は,手術創を小さくするということのみに留まらず,手術を行う臓器の機能温存にも広がっています.腎癌における手術の変遷が最もわかりやすいかと思います.以前は,腎門部をきちっと露出するようなChevron切開を用いて手術を行うことが多かったわけですが,これは今では腫瘍塞栓を伴う手術で利用されています.確かに腫瘍塞栓を伴った症例では大きく展開することが重要ですが,過去においては「親指大の腫瘍でもこのような手術は必要なのか?」と疑問を持ちつつ,せっせと大きく切っていたわけです.1990年代に入り腹腔鏡が用いられ始め,大きな手術創と別れを告げることとなりました.その後,腎機能温存を目的とした部分切除が小径腎癌に用いられていましたが,技術の進歩やロボット支援手術を用いることで,現在では比較的困難な腎門部腫瘍やT1b症例に関しても行うことがあるようです.
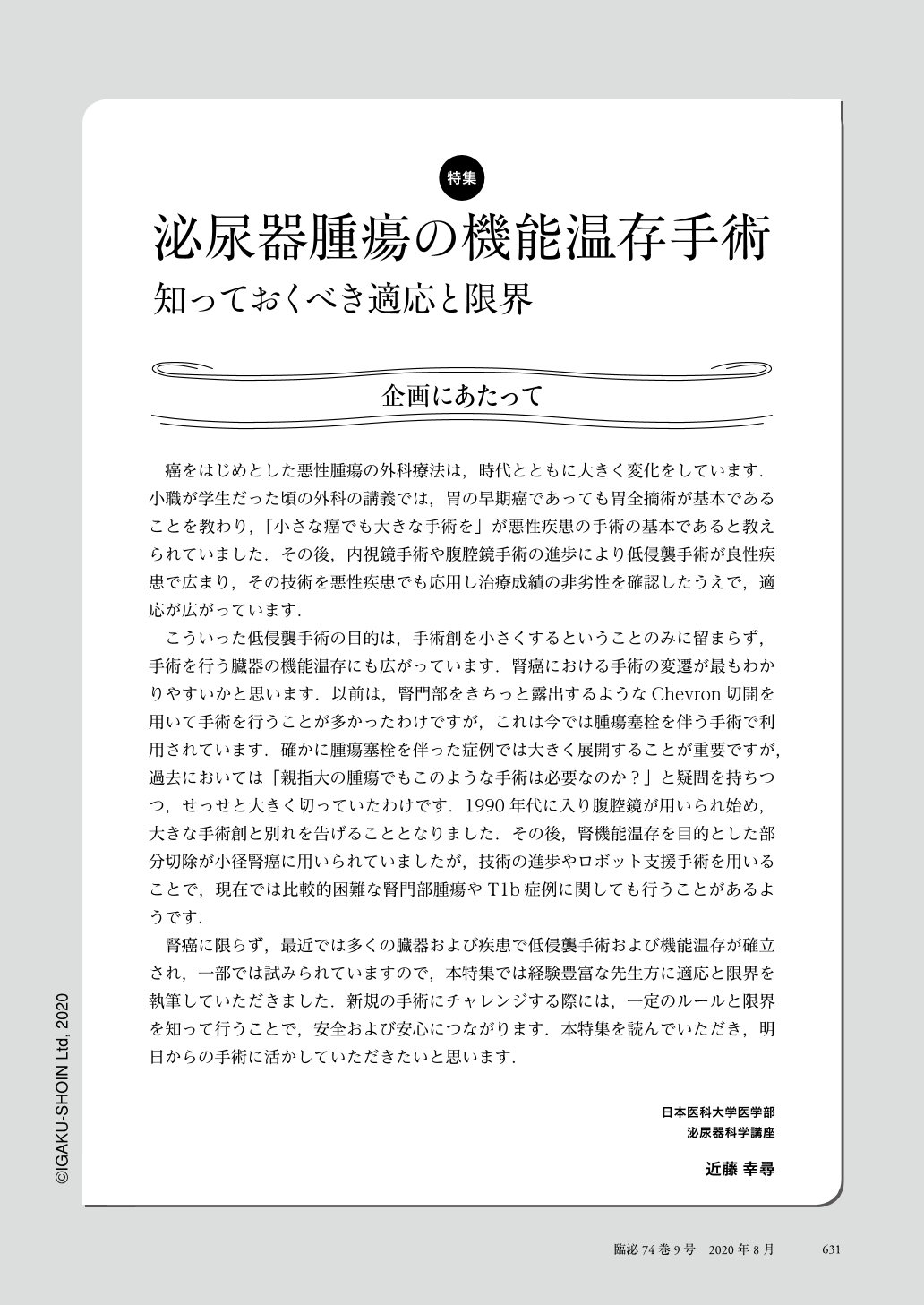
Copyright © 2020, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


