特集 流早産の治療--最近の焦点
流早産の手術療法
官川 統
Osamu Hirokawa
pp.35-40
発行日 1972年1月10日
Published Date 1972/1/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1409204546
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
はしがき
私どもが産婦人科の医局に入つた昭和27年頃では流早産の治療法は黄体ホルモン(その投与量は5mgが普通であつた),および阿片チンキの投与であつた。その後数年はその治療法の効果は疑うことさえもせず,金科玉条と実施を続けていた。しかも流早産の原因として成書には系統立つて示されるものをそのまま信じていたわけであつた。しかし昭和32年の暮頃から習慣性流早産の患者を集め始め,5〜6年経過し,その数が1,000例を超えるに至つて,そしていろいろな原因をできる限りチェックし,治療とともにその経過を観察することを半ば強制的に余儀なくさせられる状況になつて,次第に成書の分類(原因の),治療法が実地に適合しないことに当惑を感じるようになつた。
当時の原因追究のための検査項目は(1)夫婦間のRh, ABO, MN,などの血型不適合の有無,および抗体の力価の測定(2)妊娠中の尿中各種ホルモン(プレグナンヂオール,17KS,エストロゲン) P.B.I.など(3)非妊時の子宮造影であり,トキソプラズマの抗体価は昭和36年頃より,夫婦間の染色体分析は40年に入つてからであつた。そして患者の既往妊娠歴および,爾後の妊娠経過の追跡などの点から信頼すべき流早産原因を探つていくと,僅かの例外(定型的な頸管無力症,高度な子宮奇形)を除いて大半が不明(すなわち原因が判らない)の項目に入つてしまうことに気がついた次第である。
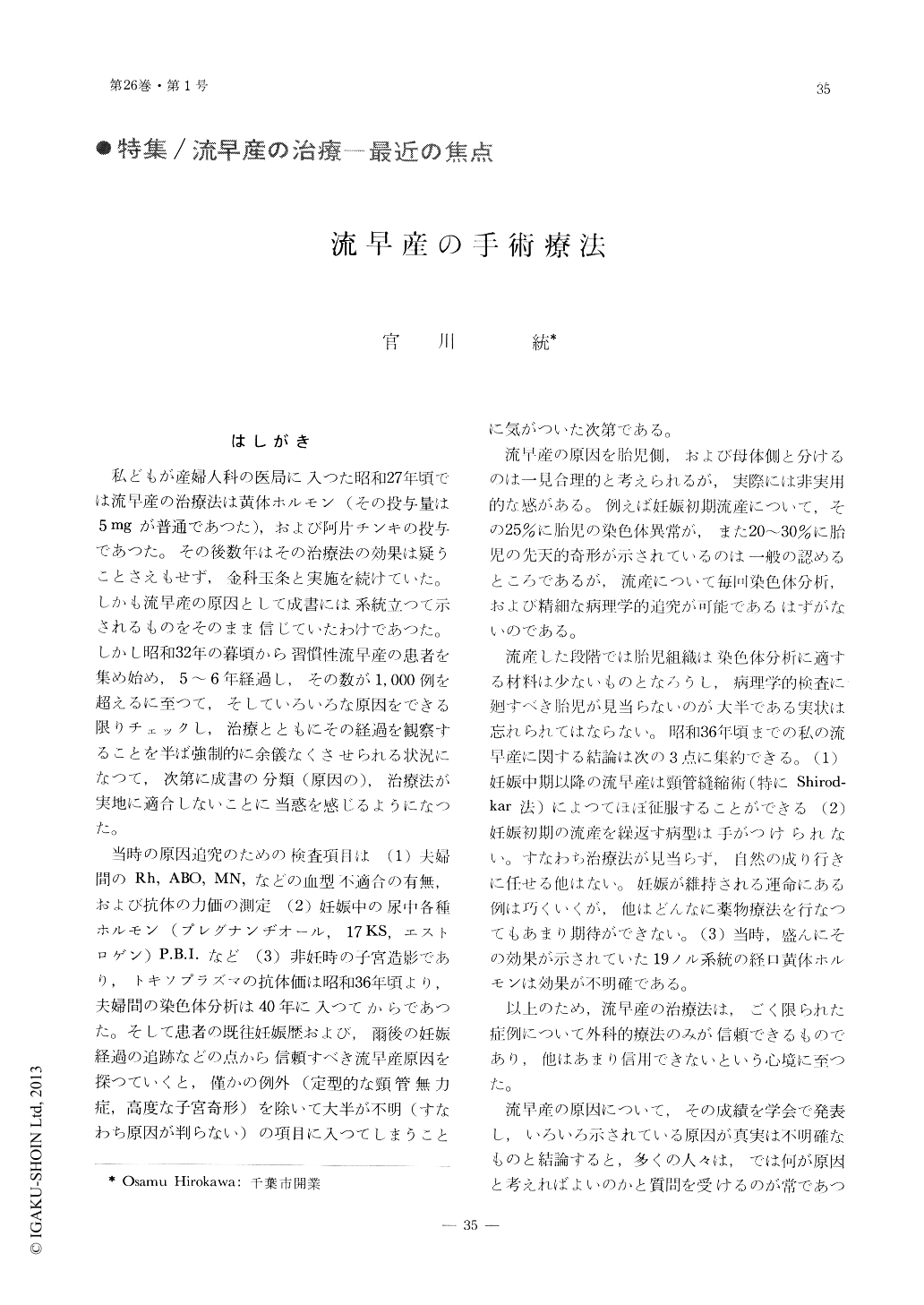
Copyright © 1972, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


